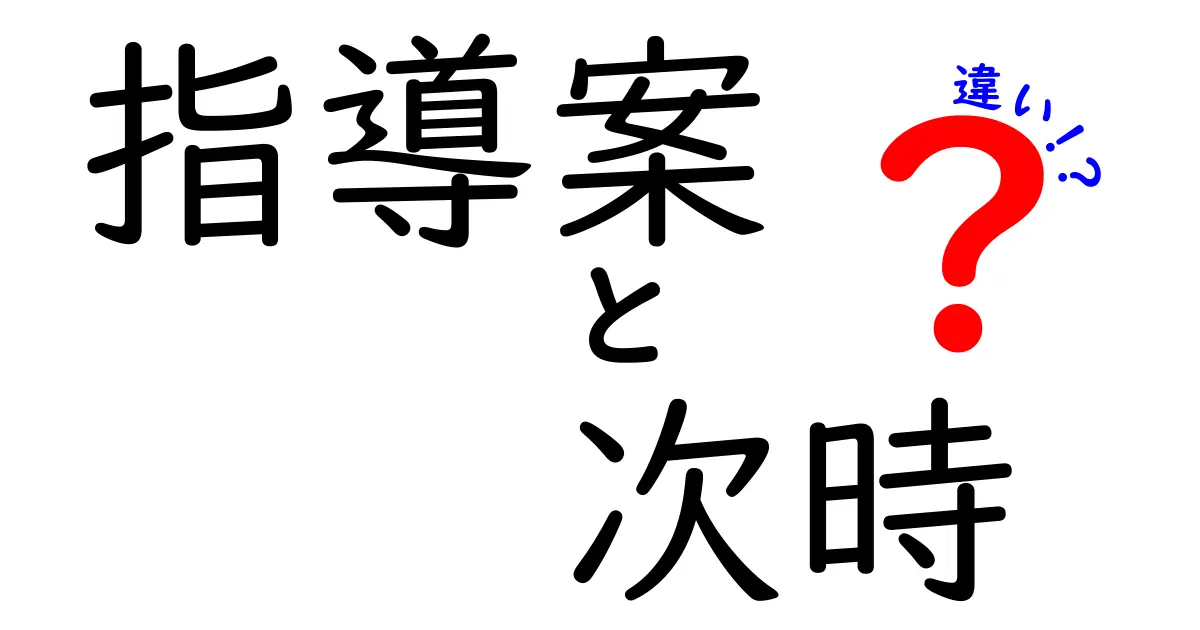

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
指導案とは何か?基本を理解しよう
指導案とは、学校の先生が授業を行う前に作る計画書のことです。授業でどんな内容を教えるか、どのような方法で教えるか、使う教材は何か、時間の配分や生徒の理解度を確認する方法などが書かれています。
つまり、指導案は授業全体の設計図として先生を助けるものです。
指導案を書くことで、先生は授業の流れをしっかり考え、生徒がわかりやすく学べる工夫をすることができます。
この指導案は、学習指導要領に基づいて作成するのが一般的で、教育現場ではとても重要な役割を持っています。
次時とは?授業の時間ごとの区切りに注目
「次時」は、授業の中の次の時間帯や次の回を指します。例えば、1時間目の授業のあとに続く2時間目の内容や、同じ教科の次の授業日の内容のことです。
授業は長い期間にわたって進むため、1回の指導案で全てをカバーしきれません。そこで指導案は、各授業時間ごとに分けて計画されます。この各回の計画が「次時指導案」と呼ばれることもあります。
つまり、次時は指導案内の一部分であり、授業の区切りを意味する用語です。次時単位で計画を練ることで、先生は毎回の授業をより効果的に進められます。
指導案と次時の違いをわかりやすく比較しよう
ここまでの説明をもとに、指導案と次時の違いを表にまとめてみます。
| ポイント | 指導案 | 次時 |
|---|---|---|
| 意味 | 授業全体の計画書 | 授業の1回分の時間やその回の内容 |
| 内容の範囲 | 複数回分の授業を含むことが多い | 1授業分または次の授業回の内容 |
| 役割 | 授業全体の設計図として活用 | 指導案の中で細かく区切った単位 |
| 使い方 | 授業準備や指導方法の計画に使う | 次の授業を計画したり振り返りに使う |
このように指導案が全体の計画であるのに対して、次時はその中の1回分の授業のことを指すのが大きな違いです。
教育現場では、これらをうまく使い分けて授業の質を高めています。
まとめ:指導案と次時の違いを知って授業をもっとよく理解しよう
今回の記事では、指導案と次時の違いについて詳しく解説しました。指導案は授業全体の詳しい計画書であり、次時はその指導案の中の1回ごとの授業を意味します。
先生がきちんと計画を立てることで、生徒はわかりやすく授業を受けられるようになります。
この違いを理解することは、将来先生になりたい人や学校の授業をもっとよく知りたい人にとって、とても役立つ知識です。
ぜひこの機会に「指導案」と「次時」の意味の違いを覚えて、授業の仕組みをしっかり理解しましょう!
指導案という言葉はよく聞きますが、その中にある“次時”が実はとても大事なポイントだって知っていましたか?授業は一回で終わるのではなく、何回かに分けて行われますよね。次時とは、まさにその次の授業回のことなんです。例えば1時間目の授業が終わったら、次の時間に何をするか?それが“次時”になります。だから次時の計画をしっかり考えることは、授業をうまく進めるコツにつながります。指導案は全体の地図で、次時はその中のひとつひとつの道のようなイメージです。授業の面白さはこの設計によるところも大きいんですよ。
次の記事: 自由科目と選択科目の違いとは?中学生にもわかるわかりやすい解説 »





















