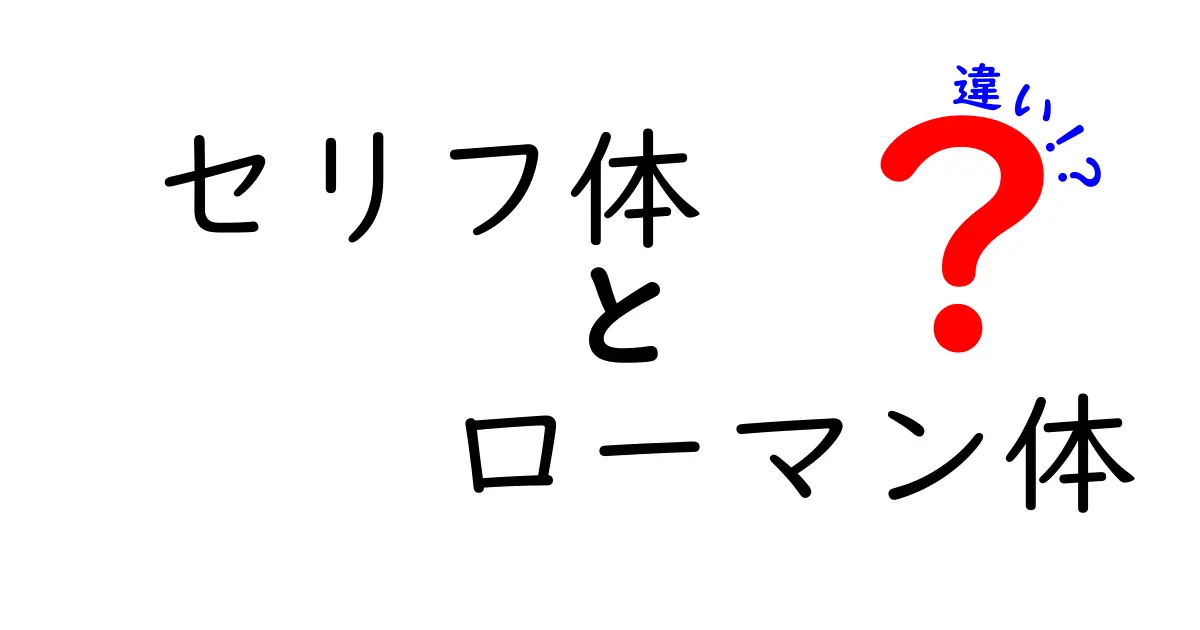

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
セリフ体とローマン体の基本を押さえよう
セリフ体とは、文字の末端に小さな装飾(セリフ)がつく字体のことです。読みやすさを追求するために長文の印刷物で昔から使われてきました。日本語では「明朝体」が代表的なセリフ体で、横組みの文字の上下に短い線が走るデザインです。セリフには目の導き手としての役割があり、文と文のつながりを視覚的にひとつの流れとして感じさせます。長い文章をじっくり読むときに効果を発揮しますし、行間を広くとれば文字同士の間が読みやすくなります。
一方、ローマン体と呼ばれる字体は、セリフのないタイプが多く登場します。英字の世界では、すっきりとした直線と角の美しさが特徴で、ウェブや画面の表示に適したデザインとして使われやすいです。日本語でも「ローマン体」と呼ぶ場合がありますが、これは英語のローマンシリーズを指すことが多く、モダンで清潔な印象を与えるのが特徴です。デジタルの世界では、本文をサンセリフ系で統一することで、情報の見やすさを高める工夫が一般的になっています。
ここまでをまとめると、セリフ体は伝統と読みやすさを、ローマン体は現代的でシンプルな印象を与えるというのが基本の違いです。印刷物を作るときはセリフ体を選ぶと高級感や読みやすさの両方を狙えます。ウェブやスクリーン表示ではローマン体系を使うと、情報がすっきりと伝わりやすい性質があります。
ただし、実際には用途・対象・媒体・デザインの雰囲気によって選ぶべき字体は変わるので、場面に応じた組み合わせを覚えておくのがコツです。
実務での使い分けとポイント
実務でセリフ体とローマン体を使い分けるときは、まず読み手の環境を意識します。紙の印刷物ならセリフ体が長文の読みやすさを高めます。例として教科書や小説、雑誌の記事にはセリフ体が選ばれることが多いです。対してウェブサイトの本文やニュース系のUIなど、スクリーンでの可読性を重視する場面ではローマン体(サンセリフ系)を用いると良い場合が多いです。画面解像度が高い現在でも、セリフ体を本文に使うと疲れを感じづらい人がいることも覚えておきましょう。
また、見出しと本文の組み合わせも重要です。見出しには力強さを与えるセリフ体、本文には読みやすさを重視してローマン体を使うなど、対照をつくると情報の階層がはっきりします。フォントサイズ、行間、文字間(字間)の設定も大切です。セリフ体の本文は小さくなると読みづらくなるので、1000~1200px程度の可読行幅を意識して、行間を1.4~1.6倍程度に設定すると読みやすさが向上します。
また組み合わせのコツとして、色や背景とのコントラストを高く保つこと、長文は段落ごとに1つのアイデアを明確にすること、などが挙げられます。
セリフ体は文字の端に小さな装飾が付く伝統的で読みやすい字体です。授業でノートを読み比べると、セリフがあるおかげで段落の入り口と終わりが分かりやすく、長文でも目が疲れにくいと感じました。最近はデザインの自由度が高く、セリフとサンセリフを組み合わせる技が重要になっています。私の友人は、提出物の本文にセリフ体を使い、注釈にはサンセリフを使うことで読みやすさと見栄えを両立させていました。結局、コツは用途と媒体を合わせること。
次の記事: 改行と行間の違いを徹底解説!中学生にも伝わる読みやすさの秘密 »





















