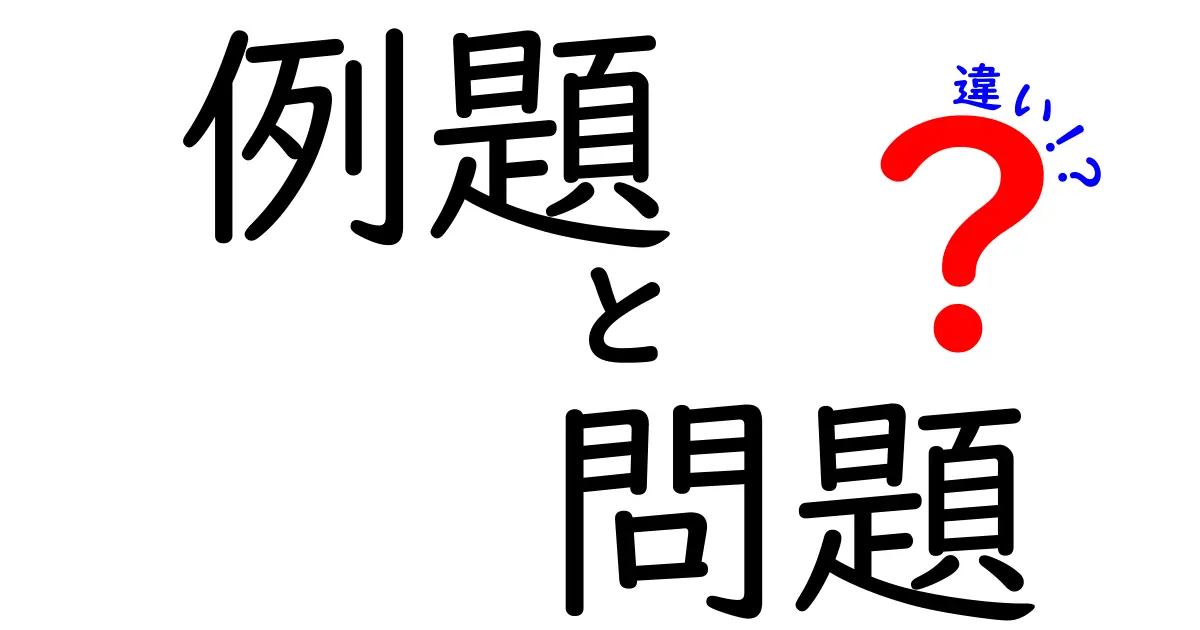

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
例題と問題の違いを完全解説!学習効率を爆上げする使い分けのコツ
例題と問題、それに違いを理解することは、学習の設計を大きく変える第一歩です。ここでは、中学生にも分かりやすい言葉で、それぞれの役割と使い分けのコツを丁寧に説明します。まず覚えておくべきは、例題は概念を実際の数値や状況に落とし込む「手本」であり、問題はその手本を自分の力で再現する「挑戦状」だという点です。違いを意識するだけで、授業ノートの読み方、宿題の取り組み方、テスト対策が自然と変わります。例題を使って考え方の筋道を覚え、それを自分の力で再現していく過程で、解けない問題が減り、考える力が身についていくのです。
この違いを理解することは、学習計画を作るときの羅針盤にもなります。目的に応じた設計をすることで、時間をムダにせず、着実に力をつけることができます。
そもそも「例題」と「問題」の定義を分けて考える
「例題」と「問題」の定義を正しく分けて理解することが、学習設計の第一歩です。例題は、概念を具体的な場面に落と込み、解法の筋道を追いやすくする材料です。数式の意味、公式の使い方、基本の考え方の順序などを、具体例を通じて頭の中に刻みます。例えば、二次方程式の解の公式を学ぶとき、最初は一つの式と一つの例題で道順を覚えるのが効果的です。反対に問題は、覚えた道筋を自分の力で再現する場です。ここでは、各ステップを自分の言葉で再構成する力、すなわち「説明する力」が試されます。練習問題をこなしながら、自分の言葉で解法を語れるようになることを目標にすると、理解が定着します。
実践的な使い分けのコツと具体例
使い分けのコツは、学習の段階と目的をはっきりと分けることです。初期段階では概念を押さえる、例題で手順を覚える、そして自分の言葉で説明するという順序を意識します。中盤以降は、短い形式の問題で反復練習を行い、解けなかった箇所を必ず解説とともに振り返ります。ここで重要なのは、単に答えを暗記するのではなく、なぜこの解法が正しいのかを言語化する練習を繰り返すことです。最終的には、例題の解法を新しい問題にも適用できる応用力を身につけます。
この章では、例題と問題の両方を組み合わせた学習計画を作る際の具体的なステップを紹介します。
表で整理して理解を深める
理解を深めるには、言葉だけでなく視覚的にも整理すると効果的です。以下の表は、例題と問題、そしてそれらの違いを端的に比べたものです。表を眺めるだけで、役割の違い、使い方のコツ、そして学習設計のポイントが一目でわかります。慣れてきたら、教科ごとにこの表を自分の言葉で埋め直していくと、さらに確実に定着します。
最後に、日々の学習にどう落とし込むかの一例を挙げます。
1日目は「例題の解法の言語化」を中心に練習し、2日目は同じテーマの問題を使って練習、3日目以降はその組み合わせで自分の問題を作って解く、という循環を作ると、読み書き解く三位一体の力が自然と育ちます。
今日は友達と雑談する感じで『例題と問題の違い』を深掘りします。例題は授業の地図のようなもので、道順を示してくれる手本です。解法の筋道を自分の言葉で説明できるよう練習すると、考え方が頭の中に定着します。一方、問題はその地図を使って自分で道を選ぶ「挑戦」そのもの。答えを出すまでのプロセスを丁寧に追うことで、解けなかった理由が分かり、次に活かせます。違いを意識するだけで、学習計画が現実的になり、遠回りせずに力をつけられると感じるはずです。





















