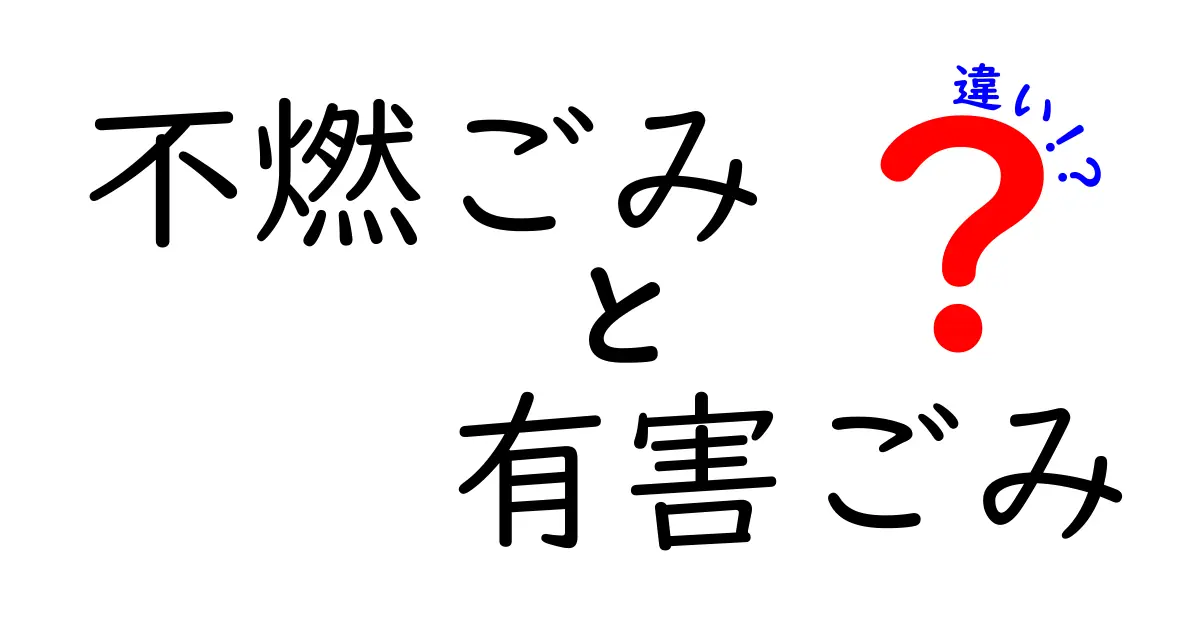

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
不燃ごみと有害ごみの違いを正しく理解するための基本のポイント
まず理解しておきたいのは、不燃ごみと有害ごみは同じゴミの中でも役割と処理の目的が全く違う点です。
不燃ごみは“燃えにくい素材”として分類され、家庭から出る日用品のうち焼却炉の燃焼工程で問題を起こしにくいものを集めます。具体的には金属製の小物、空き缶、空き瓶、ガラス、陶器、壊れた器、硬質プラスチックの固形品などが該当します。これらは燃やしても油分が残る、燃焼時に溶融が進むと機械を傷つける可能性があるといった理由で、有害性は比較的低いと判断されることが多いのです。
一方で有害ごみは“有害な物質を含むゴミ”で、処理の過程で化学反応を起こしたり、人体や環境に悪影響を与えたりする危険性があります。乾電池・ボタン電池、蛍光灯・水銀を含む電気製品、塗料・シンナー・薬品類、廃油・農薬・消毒薬などが典型的な例です。これらを誤って不燃ごみとして出すと、焼却過程で有害物質が拡散したり、回収作業員の安全にリスクを与えたりする恐れがあります。したがって有害ごみは専用の回収日や指定の袋・容器、場合によっては店舗回収や行政の集積場を使う必要があり、自治体ごとに細かなルールが設けられています。地域によっては「有害ごみは透明袋」「一点ごと分別」などの細かな運用が異なるため、必ず公式の情報を確認することが大切です。
日常生活の中で最も混乱するのは、危険性を伴う品物の扱いと、再度の使用が可能かどうかの判断です。例えば、長く放置されていた塗料やシンナーは「有害ごみ」として扱われ、独自の受け渡し方法が必要です。反対に金属の缶や壊れたガラスは、不燃ごみとして出せる場合が多いですが、底に液体が残っていないか、ラベルが剥がれているか、汚れがないかを確認することが大切です。
自治体ごとのルールと自分でできる確認ポイント
自治体の分別ルールは全国共通ではなく、地域ごとに細かな差があります。新しく引っ越してきた地域では、ゴミの袋や回収日、出し方がこれまでと違うことが多いです。確認のコツとしては、自治体公式サイトの“ごみの分け方”ページを見る、広報紙の回収カレンダーをチェックする、区役所・市役所の窓口に電話で問い合わせる、などがあります。実際の現場では、表示シールの有無、分別区分の名称、袋の色分け、出し方の順序などが詳しく説明されています。初めての回収日には、前日までに最終確認を済ませておくと安心です。
また、分別に迷ったときは「とりあえず危険性が高い・危険性が低いの2択」に分け、危険性の高い方を有害ごみと想定して扱うとミスが減ります。分別は家族全員で共有する習慣をつくり、誰が何を出すのか、どの袋を使うのかを日程表とともに見える場所に貼っておくと効果的です。
ねえ、有害ごみって難しく感じるけど、結局は“扱いづらい危険物”の集合体なんだよね。去年の学校の清掃で、乾電池を普通のゴミ袋に入れてしまう子がいて、回収員さんが危ないと止めていた。実は乾電池は水銀や鉛などを含み、燃えるかどうかよりも安全性が最優先。だからこそ、地域のルールをきちんと守ることが、みんなの安全を守る第一歩なんだよ。蛍光灯やスプレー缶も同様に扱いを間違えると大事故につながる危険性があるから、出す前に必ず有害ごみの回収日と出し方を確認する癖をつけよう。身近なものほど、ちょっとした心がけで安全性が大きく変わるんだ。みんなで正しく分別して、地域のゴミ処理を支えていこう。





















