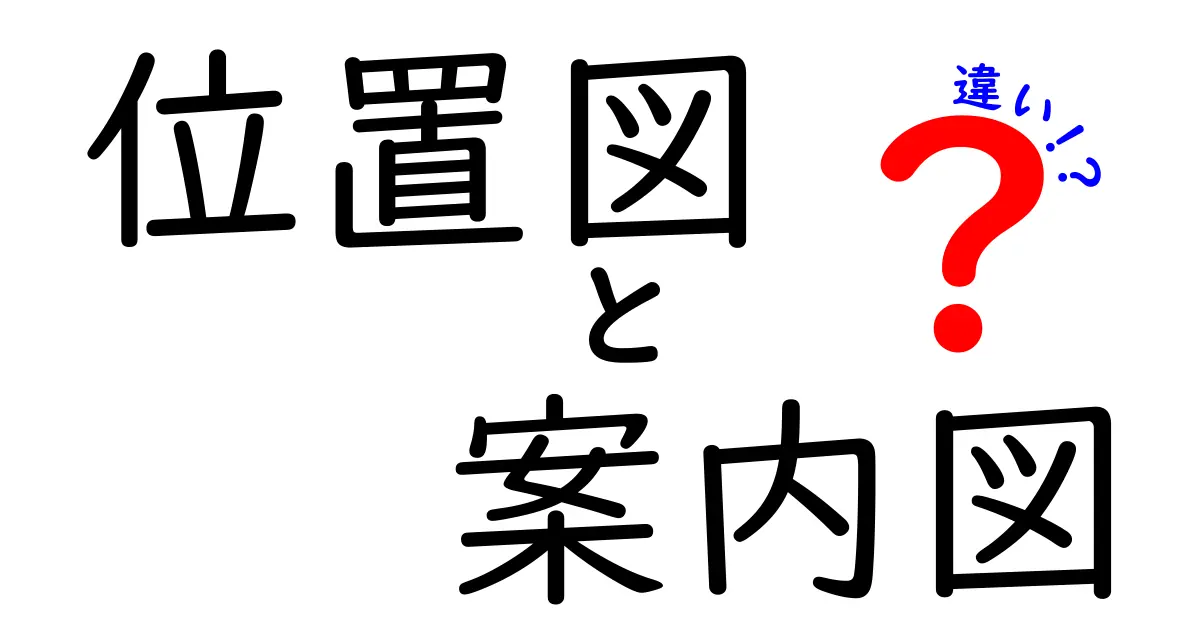

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
位置図と案内図の基本的な違いを知ろう
位置図とはある場所の位置関係を基準に描いた地図のことです。どの地点がどの場所にあるのかを、相互の距離感や方角とともに示します。日常生活では住宅地の配置や駅周辺の広がりを把握する際に役立ちます。緯度経度よりも“ざっくりとした位置感覚”を重視することが多い点が特徴です。縮尺は広域を一枚の紙や画面に収めるためにやや大きめに設定され、道路の細かな看板や建物の形を省略することが普通です。
このような性質は都市計画の現況把握や地域のボリューム感を伝えるのに向いており、観光のパンフレットよりも“どこにあるか”の情報を先に伝えたい場面で活躍します。
案内図は目的地へ到達する道順を示すことを第一の目的とした図です。駅の構内案内、ショッピングモールの案内板、観光地のルートマップなどが代表例で、矢印や路線の接続、入口の位置、距離感の目安を分かりやすく示します。案内図は一般的には少し簡略化されたデザインで、地物の正確な配置よりも“この道を進めばよい”という直感を重視します。看板のような現場で使われることが多く、地図記号は国や自治体の規格に沿って決められています。
この2つの図は目的が異なるため、作るときの前提条件も変わります。位置図は測量データに基づき、建物の正確な位置関係を表すことが求められます。一方案内図は利用者の動線を想定して作られ、視認性を最優先してアイコンや文字の大きさ、色のコントラストを工夫します。結果として、同じ場所を表していても、位置図は広い視野の把握、案内図は現場での素早い誘導に向くものになるのです。
使い分けのポイントと実例
実務でどう使い分けるべきかのポイントを整理します。まず、目的が“場所の理解”なら位置図、目的が“目的地までの誘導”なら案内図を選ぶのが基本です。場所の学習や地理の入門教材では位置図を、案内板や地図アプリの解説には案内図を使うのが多くの人の共通認識です。見やすさを最優先にするなら案内図、正確性と位置関係の理解を重視するなら位置図と覚えておくと混乱が少なくなります。
実例を挙げると、地下鉄の路線図は案内図に近く、駅と改札の位置関係を人が迷わないように示します。行政の防災マップは位置図の要素を取り入れつつ、避難経路を強く示すため案内図的な要素を持っています。学校の地図教材では、まず位置図で地域全体のイメージを掴み、その後に案内図で日常の移動を練習する流れが一般的です。
| 項目 | 位置図 | 案内図 |
|---|---|---|
| 目的 | 位置関係の理解 | 導線の提示 |
| 縮尺 | 広域重視 | 適度な縮尺で直感性を重視 |
| 特徴 | 現地の配置を正確に表す | 直感的な判断を促す |
ある日、学校の図書室で友だちと地図の話をしていた。私は位置図と案内図の違いをうまく説明できず、ノートに例を描いて説明した。位置図は広い視野で“この場所がどこにあるか”を示し、周囲の地物との関係性を伝える道具だと伝え続けた。一方で案内図は手早く目的地へ誘導する道筋を示す地図で、矢印や道順が見やすさの中心になる。私たちは街の地図の話題で大いに盛り上がり、気がつけば歩きながらも自分たちの町を違う視点で眺められるようになっていた。





















