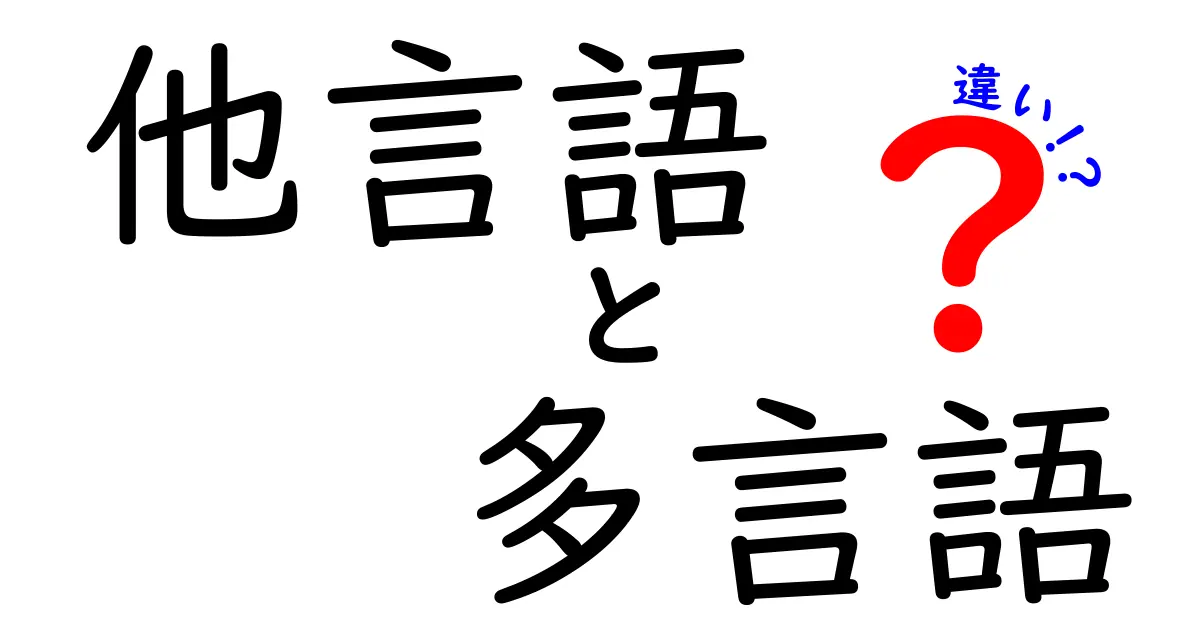

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
他言語と多言語の違いを理解する基本
「他言語」と「多言語」が日常の日本語でどう違うかを理解するには、まず語源と意味のズレを意識します。他言語は「自分の母語以外の言語」を指す言葉として使われるのが一般的です。例として「この授業では他言語話者のための補講を用意します」や「英語を母語としない他言語話者」といった表現があります。ここでは言語そのものを指す場面が多く、会話の焦点は“どの言語が使われているか”です。
一方、多言語は「複数の言語を使える」という能力や環境を表す語として使われるのが特徴です。例として「彼女は多言語を話す」「多言語教育」など、能力・教育・社会的な状況を描写する際に頻繁に登場します。
このように、他言語は“言語そのもの”を指し、文や場面の中でどんな言語が使われているかを示す点が特徴です。多言語は“人の能力・状態”を示す語であり、複数の言語を扱えるかどうかという能力の側面が強いのがポイントです。文章を作る際は、主語が誰で、何をどう伝えたいかをはっきりさせると、混乱を避けられます。
例えば、教育の場面で「他言語話者向け資料を作る」か「多言語教材を作る」かを判断するとき、目的が相手の言語の種類を指すのか、話者の能力そのものを指すのかで言い換えが変わってきます。
また、日常生活でも「このスマホアプリは多言語対応だ」と言えば、複数の言語を扱える機能を指します。逆に「他言語を学ぶ」になると、目標言語の習得や学習プロセスに焦点が移ります。ここでのポイントは、形や語感だけでなく、文の意味と文脈を見て正しく選ぶことです。
本記事を読む人が特に知りたいのは、学校の授業・海外旅行・仕事の場面での使い分けです。実際の場面を想定して、二つの語を混同せずに伝えられるよう、例文をいくつか紹介します。
実生活での使い分けと注意点
実生活の場面での使い分けは、言語的な感覚だけでなく、社会的な配慮も関係します。他言語は主に相手が使う言語を指す表現として使われ、紹介や説明の導入で「この地域の他言語は〇〇です」といった具合に、話題の焦点が言語そのものになります。これに対して多言語は自分や組織、社会全体の能力や状態を指すことが多いです。たとえば「当校は多言語対応の教育プログラムを提供する」「このアプリは多言語対応を拡張し続けている」といった使い方です。
次に、具体的な場面別の使い分けのコツを整理します。
1) 学校・教育の場面では、“学習者がどの言語を使えるか”よりも、教材の対象言語が何かを明確に伝えるのが大切です。
例文:「この課題は他言語話者向けの補足資料を用意します」
あるいは「このクラスは多言語教育を取り入れ、英語と母語の両方で学べます」。
この違いを理解しておくと、教師と生徒の双方が混乱せず、目的がはっきりします。
2) 海外旅行・生活の場面では、現地の言語状況を説明する際に他言語と表現することがあります。
例:「この場所は主に現地の他言語が使われます」
しかし現地で自分が複数の言語を使えるという意味を伝えるときは、多言語を使います。「私は現地の人と多言語でコミュニケーションを取れます」。
このように場面での意味の切り替えを意識すると、英語だけでなく現地語の理解・協力が深まります。
3) ビジネスの場面では、相手の立場や業界用語に合わせて言い換えが必要です。
例:「この資料は他言語の版も用意します」
「このプロジェクトは多言語対応を進めています」
4) メディアや文章表現の場面では、読み手の想定言語を意識することが重要です。
読者が多数の言語を母語としない場合には「多言語対応」「他言語の案内」といった表現を用いると、伝わりやすくなります。
このように、他言語と多言語は使い分けのコツがあり、場面・相手・目的によって変わります。大切なのは、情報を受け取る人が理解しやすい言い方を選ぶことです。
最後に、表現の練習として自分の日常の文章を声に出して読んでみると、感覚のズレに気づけます。
何度も繰り返すことで、他言語と多言語の違いが自然に身につき、正確な言葉選びができるようになります。
ねえ、最近「多言語」という言葉を聞くと、私はつい自分の成長の道具箱を思い出します。言語は道具で、複数の道具を揃えるほど世界の扉は広がる。多言語を身につけるには、似た音の言葉をグループ化して覚えると楽です。学校の授業だけでなく、友達との会話やオンラインのコメントでも、多言語という現実感が増してきます。私は日々、音やリズム、文化の違いを感じながら、少しずつ覚えることを楽しんでいます。そんな取り組みが、いずれ大きな力になると信じています。





















