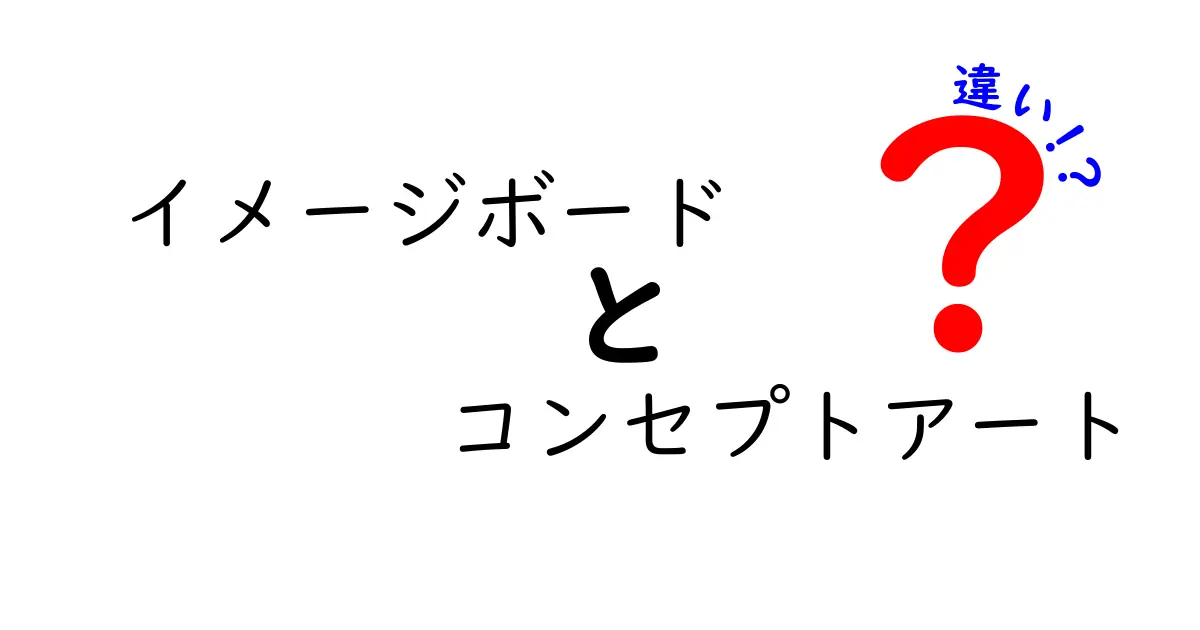

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
イメージボードとコンセプトアートの基本的な違い
両者は似ているようで、実は目的と使われ方が違うデザインのツールです。
「イメージボード」は主に雰囲気を伝えるための視覚集約で、写真や素材を並べて色味や感覚の連なりを直感的に共有します。
「コンセプトアート」は作品世界の核となる視覚案を描く作業で、キャラクターの形、世界の風景、光の当たり方、素材の質感までを具体的に検討します。
この違いを理解しておくと、企画の初動で誰が何を理解すべきか、どの段階に何を提出すべきかが見えやすくなります。
また、制作現場では両者を同じレベルの詳細さで扱うことは少なく、意思決定の粒度も異なります。
ここからは定義と役割、作成の順序、使い分けのコツを順番に見ていきましょう。
ポイントの要点は「雰囲気と方向性を共有するのがイメージボードの役割」「世界観と設計を具体化するのがコンセプトアートの役割」です。これを頭に置くと、初期段階での情報のズレを減らすことができます。
以下の表と例で、違いをさらに理解していきましょう。
| 用語 | 目的 | 主な特徴 | 使われる場面 |
|---|---|---|---|
| イメージボード | 雰囲気・方向性の共有 | 写真・素材の寄せ集め、 collage 的 | 企画・初期検討、デザイン指針の共有 |
| コンセプトアート | 世界観の具体化 | オリジナルの描画、色味・光・形の設計 | ゲーム・映画・アニメの世界設定作成 |
用語の定義と役割
このセクションでは、まず二つの用語を分解して、それぞれの役割を日常の場面でイメージできるようにします。
イメージボードは、作る側の直感を共有するツールです。写真・素材・パターンを切り貼りして、色相の傾向、質感の方向、世界のむずかしさを視覚的に示します。
一方、コンセプトアートは、作品の「何を描くのか」という核心を形にする作業です。キャラクターの体格や衣装、風景の奥行き、光源と色の関係性を絵で具体化します。
この二つを混同しやすい場面もありますが、結論としては「誰に向けて何を決めたいか」が最初に決まっているかどうかで使い分けが生まれます。
プロジェクトの初期段階では、イメージボードは方向性を素早く共有するための地図、コンセプトアートは方向性を具体的なビジュアルとして落とし込む地図と考えると分かりやすいでしょう。
作成の流れとポイント
作成の順序としては、まず企画チームがコンセプトの核を議論し、次に雰囲気や色味を確認するためのイメージボードを作成します。
この時、素材選びは現場の実務に合わせて行い、著作権や出典の整理を忘れずにします。
重要なポイントは以下の通りです。
1. 目的を明確に、2. 伝えたい感覚を設定、3. 関係者の視点を揃える、4. フィードバックを回す、5. 版式と納品形式を揃える。
これらを踏まえると、情報の粒度のズレが減り、後の修正コストも抑えられます。
また、実作業の手順として、ラフスケッチ→カラーのラフ→細部描写という順に進むことが一般的で、段階ごとに提出物の粒度を変えることが成功の鍵になります。
以下の表は、作業の流れの目安を視覚化したもの。
| 段階 | 目的 | 成果物 |
|---|---|---|
| ラフスケッチ | アイデアの整理 | 紙面またはデジタルの落書き |
| カラーラフ | 雰囲気の確認 | カラーパレットと近似カラー |
| 細部描写 | 実装可能なビジュアル | 完成版に近い絵 |
実務での使い分けの実践例
実務の現場では、広告、ゲーム、映画、アニメなどジャンルごとに使い分けが変わります。例えば、ゲームの開発では、初期の世界観設定にコンセプトアートのアウトラインが必要で、以降の段階ではイメージボードを使って美術表現の方向性を全体に広げます。
また、映画のプリビジュアル作成では、コンセプトアートが先行してキャラクターの重量感や素材感を表現し、イメージボードが全体の雰囲気や色温度を整え、美術監督が全体の統一感を監修します。
このように、現場では「両方を組み合わせて使う」が基本となり、誰が何を受け取るかを前もって決めておくことが成功の秘訣です。
実務の現場での具体的な運用は、以下のポイントを押さえると分かりやすくなります。
1) 関係者ごとの納品条件を明確にする
2) 出典とクレジットの取り扱いを統一する
3) フィードバックの回し方を決めておく
4) 実制作の版式・ファイル形式を共有する
ねえ、さっきのキーワード、イメージボードとコンセプトアートの話を友だちと雑談風に深掘りしてみよう。まず結論から言うと、二つは“似て非なる道具”です。イメージボードは現場の空気を伝えるための写真や素材を貼り付けたコラージュで、色の傾向や素材感、世界の雰囲気を一目で伝えられるのが魅力。対してコンセプトアートは世界観を具体的に描く絵です。形や陰影、光の方向、素材の質感の連携を試し、作品の核となるビジュアルを設計します。僕の経験では、企画初期にはイメージボードをまず作って方向性を共有します。そこから、必要な要素を絵として描き起こしていくと、関係者の想像と現実の差が縮まるんです。だから、会議での反応が悪いなと思ったら、まずは雰囲気を変えずに素材の組み合わせを変えるだけのイメージボードを回してみるのが有効です。このやり方なら、文と絵のギャップを減らして、後の修正回数を減らすことができます。





















