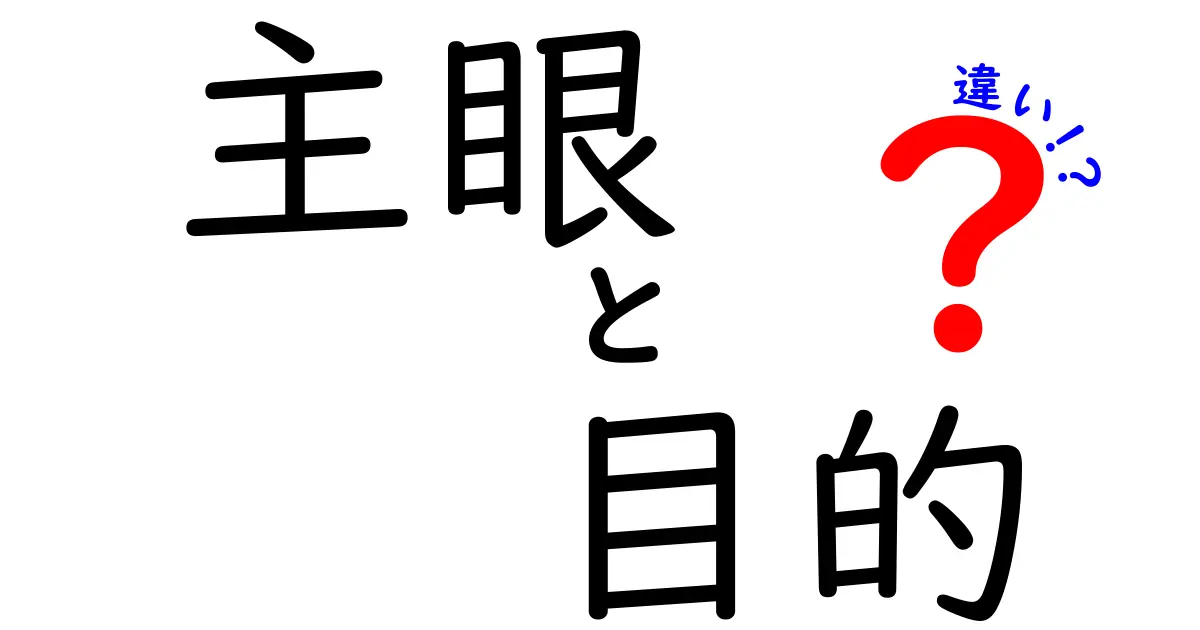

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
主眼・目的・違いを正しく理解するための基礎知識
まず前提として、文章を作るときには「何を訴えたいのか」を決めることが第一歩です。ここで重要になるのが「主眼」と「目的」です。言葉は似ているようで意味が異なります。混同して使うと伝えたいことがぼやけてしまい、読者が何を信じればいいのか、どこに着地するのかが見えなくなります。この記事では、主眼、目的、そしてその差を丁寧に解説します。読者が理解しやすく、実務にも活かせる具体例を取り入れていきますので、ぜひ最後まで読んでください。
準備として、日常の会話や学習・プレゼンの場面を想定して、主眼と目的がどう動くのかを見ていきましょう。
まずは、用語の定義をそろえておくことが大切です。
主眼は「中心に据える焦点」、目的は「到達したいゴール」と覚えると混乱が減ります。
この理解を深めるために、次の章でそれぞれの概念を詳しく見ていきます。言葉の意味だけでなく、実務の場面でどう扱うのか、そして読者にどう伝わるかを具体的な例とともに示します。くり返しになりますが、主眼と目的は異なる役割を持つ二つの設計軸です。
正しく使い分けると、文章の流れが自然になり、読者は話の筋を迷わず追えるようになります。
今回は特に、学校のレポート、ビジネスの企画書、SNSの投稿といった日常的な場面を想定して解説を進めます。主眼と目的を適切に設定することで、最初の一文で読者の関心を掴み、最後の結論で明確な行動を促す、という理想的な構成が作りやすくなります。
また、主眼・目的・違いを理解することは、他者と協力して成果物を作る場面でも強力な武器になります。読者のニーズを把握し、伝えたいポイントを要約して伝える力が自然と身につくのです。
この段階で覚えておきたいのは、主眼と目的は“設計図の二つの柱”だということです。設計図を描くときには、まず主眼を決め、その上で達成したい目的を設定します。これを逆にしてしまうと、文章全体の方向性が定まらず、読者に届くメッセージがぼやけてしまいます。正しく使い分けることが、読み手に伝わる文章づくりの基本です。
最後に、主眼と目的を決める際には次のコツを覚えておくと良いでしょう。読者の立場に立ち、彼らが何を知りたいのか、何を感じ取ってほしいのかを先に考えます。そこから、主眼を中心に据え、目的をその中心軸に乗せる形で全体を組み立てると、筋道の通った、説得力のある文章になります。
主眼とは何か
主眼とは、取り組みの中で最も重視する点、つまり「何を一番伝えたいか」という観点のことです。たとえば、学校の作文であれば「読者に共感してもらうこと」が主眼の場合が多いです。企業のプレゼンでは「新しい技術の優位性を理解してもらうこと」が主眼になることがあります。主眼を決めると、文の順序、語彙の選び方、例え話の選択まで大きく変わります。主眼が決まると、説明の軸が一本化され、読者は話の筋を追えるようになります。
この時、主眼を狭く設定しすぎると全体の幅が狭くなり、逆に広すぎると伝わりづらくなるので、適切なバランスを探すことが重要です。さらに、主眼は読者の立場やニーズに応じて微調整することが必要です。例えば、保護者向けの説明文では「安全性の向上」を主眼にするなど、聴衆に合わせた焦点の調整が効果的です。
主眼を決める際には、結論だけでなく、導入部分で読者が何を得るかを明確にします。導入で「この話の主眼は何か」を短い文で提示すると、読み手が話の筋を掴みやすくなります。例えば、ニュース記事なら「現状の課題とそれをどう解決するか」が主眼になることが多いです。教育コンテンツでは「学ぶ過程での理解の深まり」が主眼になるケースもあります。結局、主眼はその文章全体の「方向性」を決める羅針盤のようなものです。
主眼を決めるときには、文章の核となる問いを設定します。問いが定まれば、以降の段落はその問いに答える形で配置され、読者は迷うことなく話の流れをたどれます。主眼は文章の初動を決める重要な要素であり、読者の興味の持ち方にも影響します。
つまり、主眼は「この話の核となる焦点」を指します。焦点が明確だと、説明の順序・例え話・データの選択が自然と定まります。文章作成の際には、まず主眼を一本の柱として立て、その柱を軸に話の全体を組み立てると理解が深まり、読者の理解を妨げる要素が減っていきます。
総じて、主眼は「何を最も伝えたいか」を決める設計の中心です。これがあると、読者は話の要点をすぐに掴み、次に説明される内容がどう結びつくのかを自然に理解します。
目的とは何か
目的は、最終的に達成したい結果のことを指します。文章における目的は、読者の行動を促すこと、情報を伝えること、あるいは意見を承認してもらうことなど、さまざまです。目的が明確であれば、段落の順序や具体例、使うデータの種類まで変わってきます。例えば、商品紹介の記事の目的が「購入してもらうこと」であれば、価格情報やメリットを前面に出し、購入ボタンへ誘導する動線を作ります。一方で教育的な文章の目的が「理解を深めること」なら、概念の説明や例え話、反対意見の整理までが重視されます。
このように、目的は「何を読者に持ち帰ってほしいか」「どの行動を促すか」という最終到達点を示します。
目的は、主眼と連携して動くと効果的です。主眼が中心の焦点であるのに対し、目的はその焦点に到達するためのゴールです。たとえば、スポーツイベントの広報文なら、主眼は「興味を引くストーリー」で、目的は「チケットを購入してもらう」ことです。こうした組み合わせが適切なら、読者は話の流れに沿って論点を理解し、最後に望む行動へと進みます。目的は定量的にも定性的にも設定可能です。定量的には「売上○○円」「登録者数○○人」、定性的には「信頼感を高める」「理解を深める」などの表現になります。
もう少し具体的なイメージを持つために、日常の場面を例に挙げます。学校の発表なら、目的は「聴衆に理解してもらい、質問の機会をつくること」です。企業の新製品説明会なら「製品の魅力を伝え、デモを体験してもらうこと」が目的になるでしょう。目的をはっきりさせると、プレゼンの流れも自然になり、聴衆が最後に取るべきアクションが明確になります。目的は数値化できる場合と、言葉で表すだけの場合があります。数値化は“売上増”、“問い合わせ件数増”など、言葉で表す場合は“理解の促進”、“信頼の醸成”といった表現です。
最後に、目的が曖昧だと、提案が現実的かどうかの判断基準も曖昧になります。目的を明確にすることで、計画の妥当性を検証するための指標が生まれ、進捗の測定もしやすくなります。目的を達成するための行動を具体的に描くことが、実務での成功につながるのです。
違いを理解して使い分けるポイント
最後に、主眼と目的の違いを“実務でどう使い分けるか”という観点で整理します。重要なポイントは次のとおりです。
1. 何を伝えたいのかを最初に決めるのが主眼、2. 受け手にどんな行動を起こしてほしいかを最初に決めるのが目的、3. その二つを協働させ、矛盾が出ないように設計する、という順序です。これを守ると、文章の「軸」がぶれず、読者は情報の全体像をすばやく掴めます。具体的な実践としては、企画書なら「提案の核となる主眼」を文頭に置き、その後に「実現の道筋(目的)」を配置する、あるいは、ブログ記事では「主眼を最初の見出しで示し、目的を最後の結論部でまとめる」などの工夫が効果的です。
また、読者のレベルに合わせて難易度を調整することも忘れないでください。子ども向けには例え話を増やし、専門的な言葉を使う場面では注釈を添えると理解が深まります。
さらに、実務では次のようなチェックリストを使うとよいです。まずは「主眼は文章全体の核になっているか」を確認します。次に「目的が各段落の役割に対応しているか」を検証します。最後に「導入・本論・結論の順序が論理的につながっているか」を読み直します。これらの作業を通じて、主眼と目的の矛盾を防ぎ、読者に伝わりやすい構成へと整えることができます。
総じて、主眼と目的は似ているようで異なる目的を持つ二つの設計軸です。主眼が「何を中心に伝えるか」、目的が「どのような結果を得たいか」を指します。両者を適切に組み合わせることで、読み手が話の筋を追いやすく、行動へとつながる文章が完成します。文章設計の第一歩として、まずはこの二つを紙に書き出してみると良いでしょう。
主眼は、会話の雑談でもよく使う考え方だよ。例えば友達に新しく始めたゲームの魅力を伝えるとき、主眼を“体験の楽しさ”に置くと、つい説明全体が体験談中心になる。目的は、その体験をどう伝え、どう行動につなげるかを決めるゴール。私が雑談をするときは、先に主眼を決めてから目的を設定して話を組み立てると、相手にも伝わりやすくなるんだ。
前の記事: « 役割・立ち位置・違いを徹底解説—場面別に使い分けるコツと実例





















