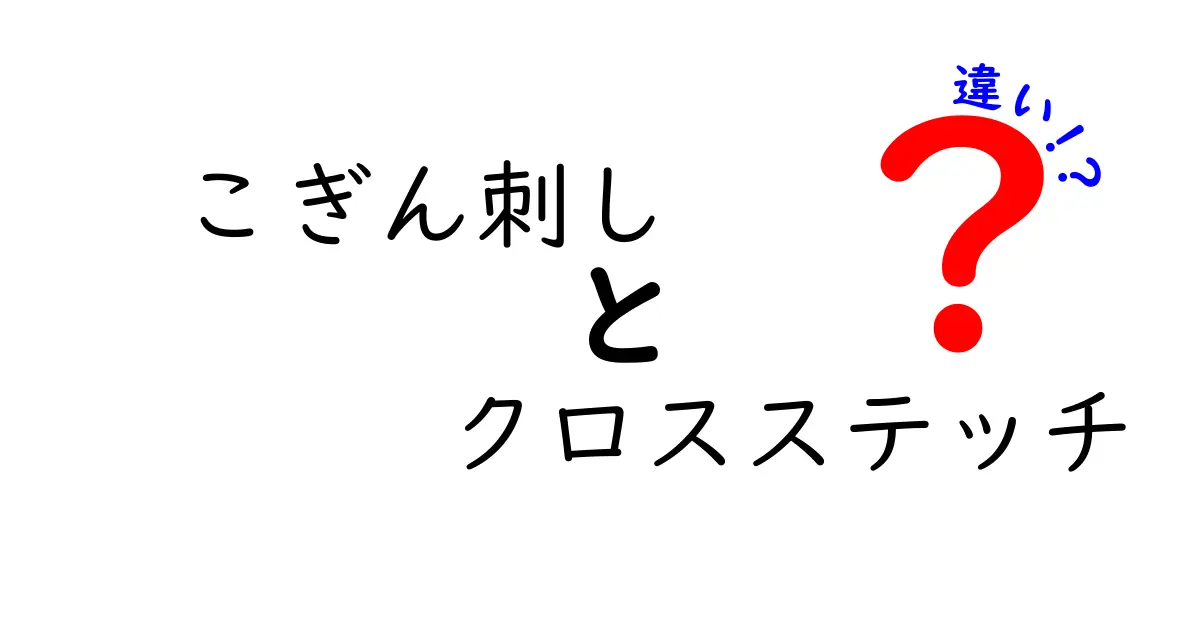

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
こぎん刺しとクロスステッチの基本的な違い
ここでは、まず両方の技法がどう生まれ、どのような材料で作られ、どんな模様が主流かを比べます。こぎん刺しは日本の東北地方、主に藍染め布に白糸の小さなステッチを積み重ねて模様を作る伝統的な刺繍です。その特徴は、布地の織り目を数えながら作る“カウント刺繍”の一種である点、柄が幾何学的で、ダイヤモンド・三角・四角などのモチーフが多い点、そして背中の仕上がりも美しく、糸の密度で温かさや質感が変わる点にあります。こぎん刺しでは、白い糸を使って濃淡を出し、布の色を生かして作品を完成させるため、材料選びと糸の太さ・長さの組み合わせがとても重要です。対してクロスステッチは西洋の伝統で、Aida布やリネンといった均等に並ぶ格子状の布を使い、X形の十字刺しを一つ一つ丁寧に打つことで絵柄を描きます。糸は通常、カラフルで細いものを選び、モチーフは風景・動物・文字など幅広いデザインが可能です。こぎん刺しは幾何学模様を中心に据え、陰影の出し方が鍵となるため、糸の色選びと刺し方のリズムが作品の表情を決めます。クロスステッチは色の自由度が高く、写真や絵画の再現性が高いのが魅力です。完成後の仕上げにも差があり、こぎん刺しでは布の端の始末と縫い合わせ方が難しい場面もあり、丁寧な仕上げを要します。反対にクロスステッチは、パターン通りに進めやすく、初心者にも取り組みやすい点が大きなメリットです。続いて、刺繍を始める際の準備として、どんな布・糸・針を選ぶべきか、初心者の視点で具体的な選び方を挙げていきます。まず布地は、こぎん刺しでは綿や麻の藍染め布、クロスステッチではAida布やリネンのような均等織りが一般的です。糸はこぎん刺しが白糸の密刺しになることが多く、クロスステッチはカラフルな糸が映えるよう細さを選びます。針は細目で尖りの適度なものを選ぶと刺しやすいという基本原則があります。練習として、簡単な幾何模様から始めると、両技法の違いが体感でき、どちらが自分に合うか判断しやすくなります。最後に、作品としての完成度を高めるコツとして、糸のテンションを均一に保つこと、布の裏側もきれいに見せる工夫、モチーフを小さく区切って段階的に進める方法などを紹介します。これらのポイントを押さえると、初心者でも着実に上達し、両技法の魅力を同時に楽しむことができるようになります。
こぎん刺しの雑談をひとつ。藍染めの布に白い糸を細かく刺すこの技法、ただの装飾ではなく寒い地方の暮らしの知恵が詰まっています。今日は、その“小さな星のひとつ”に注目。糸の太さ、刺す間隔、布目の数え方—どれも均等に保つと模様が呼吸を始めます。私たちが見るきれいな幾何模様は、実は「繋がりの美学」だと感じます。おばあちゃんが教えてくれたように、針先を布の目にきちんと入れること、裏側も美しく見せるコツ、そして失敗を恐れず繰り返す姿勢が成長を生み出します。こぎん刺しは難しく見えるかもしれませんが、始めは小さな模様から。少しずつ糸を揃え、布の収縮を考えながら縫えば、誰でも冬の寒さを暖かさへ変える作品を手に入れることができます。
前の記事: « 日本画と油彩画の違いを徹底解説:素材と技法で見る表現の秘密





















