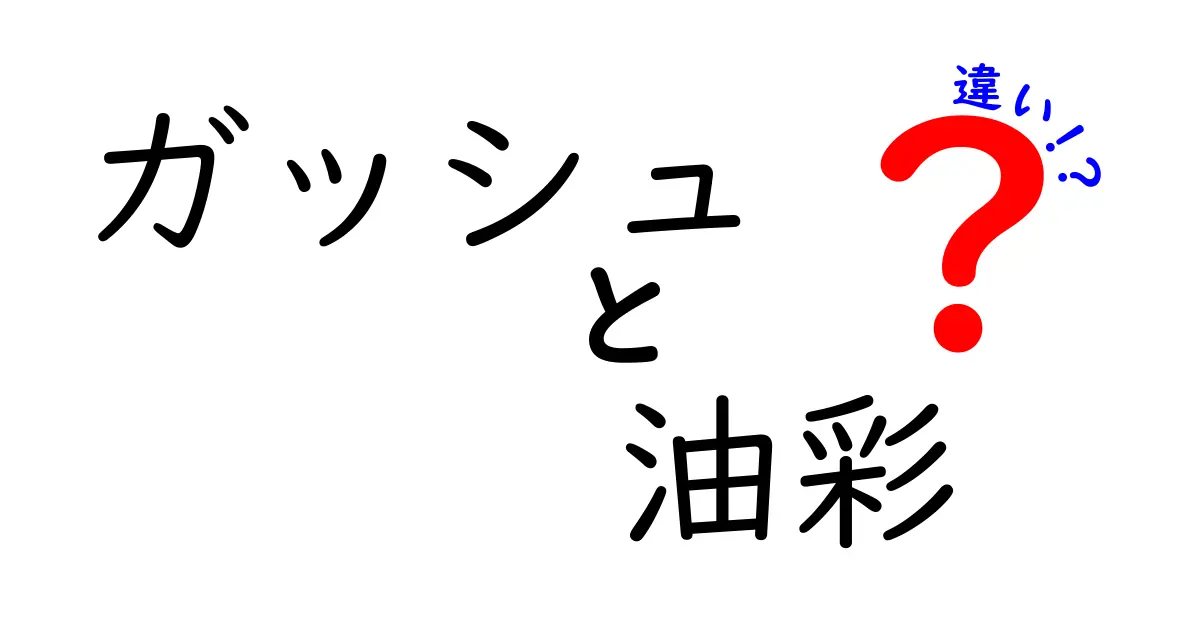

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ガッシュと油彩の違いをわかりやすく解説
絵を描くときに使う絵の具にはいろいろなタイプがありますが、特によく見かけるのがガッシュ(ガッシュ・グアッシュ、通称ガッシュ)は水性、そして油彩は油性の絵の具です。この2つには性質の違いがはっきりあり、それが作品の見た目や作業の進め方に大きく影響します。
まずガッシュは水性で透明感と不透明さを両立させやすい絵の具です。紙の上で色を重ねるとき、下の色を覆い隠す力と、上に塗る色の明るさを出す力が適度にバランスします。一方で水分を多く含むとにじみやすく、重ね塗りの順番によっては意図しない混ざり方をすることもあります。
これに対して油彩は油性で長時間の操作がしやすく、深みのある色味や混色の境界の柔らかさが特徴です。厚塗りや擦り混ぜ、長時間の乾燥待ちの間に描き手の意図をじっくり表現できます。乾燥は遅いので、色をじっくり見ながら調整する時間が作れますが、その分作成過程が長くなることもあります。
この2つの違いを理解することで、作品の雰囲気や完成までの時間、扱う素材の選択が自然と決まっていきます。以下では、両者の基本的な性質、使い分けのコツ、作品の仕上がりを左右するポイントを、できるだけ分かりやすく整理します。
この表は、初心者のうちに把握しておくと絵具選びが楽になる基本比較です。
ただし、実際にはブランドや色の性質、紙質、道具の使い方次第で表現は変わります。同じ色名でもメーカーごとに発色が違うことを覚えておくと、色味の迷いを減らせます。
次のセクションでは、それぞれの絵具の具体的な作業手順を見ていきましょう。
ガッシュとは?油彩とは?
まずは2つの絵具の定義を明確にしておきます。ガッシュは水性の絵の具で、白の成分が混ざった不透明系と、透明度の高い色を組み合わせて使うのが基本です。揮発性の溶剤を使わず、水で薄めて紙の質感を活かした表現が得意です。デザイン画やポスター風の作品、軽やかな色の階調を作る時に力を発揮します。
一方油彩は油脂系のバインダーを使い、乾燥時間が長めで色の滲みや混ざり方が穏やかです。厚塗りの美しい陰影や、長く色を眺めて修正を掛けられる余裕を持つ作品づくりに適しています。
歴史的には、ガッシュは学校やアトリエでの初級者向けの導入絵具として広く用いられ、油彩は本格的な油絵として長い伝統を持っています。素材の性質を理解すれば、作家としての表現の引き出しも自然に増えていきます。
材料・道具・作業の違い
道具はどう違うのでしょうか。ガッシュには水鉢、柔らかめの平筆、コシのある細筆、そして厚みのある紙がセットになることが多いです。水性なので道具の洗浄は水で済み、匂いも穏やかです。作業中は紙の吸水性が色の広がりに影響します。油彩は油性の絵の具用の油、溶剤(時にはブレンド用の溶剤)、堅牢なキャンバスや油絵布、さらに油性の媒体が必要です。筆も硬めの穂先を使い、長時間の作業に耐えられるような道具選びが重要です。
作業のコツとして、ガッシュはまず下地を整えた後、厚塗りを避けつつ段階的に色を重ねるのが基本です。油彩は薄い色を先に塗って徐々に濃い色を重ねるグレージングや、厚塗りで陰影を作る技法が向いています。どちらも乾燥のタイミングを見極めることが大切で、塗料の粘度や紙・布の性質によって微妙にテクニックが変わるため、練習を重ねるほど理解が深まります。
さらに、表現の幅を広げるには、両者の混用も検討できます。例えば、下地をガッシュで塗り、仕上げを油彩で行う「ガッシュ下地+油彩仕上げ」の技法は、発色と深みを両立させる新しい表現を生み出すことがあります。これらの組み合わせは、個々の作品の目的に合わせて試してみる価値があります。
重要なのは、まず自分が描きたい雰囲気をイメージして、それに合う絵具を選ぶことです。初心者のうちは、色のimuを追いかけすぎず、実際に塗ってみて「この感じが好きかどうか」を判断材料にすると良いでしょう。
仕上がりと保存のポイント
仕上がりの印象には、ガッシュはマット寄りの質感、油彩はツヤと深い陰影が挙げられます。ガッシュは白地の紙を活かした表現が得意で、発色をはっきり見せたい場合に適しています。油彩は層を厚く重ねられるため、光の反射や重ね塗りのニュアンスを豊かに作ることができます。保存に関しては、ガッシュは水性ゆえに湿度や水分に敏感な面があるため、湿度管理が大切です。閉域された環境での保管や、作品の周りに換気を避ける配慮が必要です。一方、油彩は油性のため、やや臭いが気になる場合があります。直射日光を避け、安定した室温を保ち、完成後は適切な乾燥時間を十分にとってからケースや額装をするのが安心です。
初心者向けの保存ポイントとしては、作品が完全に乾燥してから額装すること、ガッシュは水分を含む性質上、こもりがちな湿度を避けること、油彩は表面が傷つきやすいのでガラス越しの保護ではなく適切なマットやケースを選ぶことが挙げられます。それぞれの絵具の特性を理解し、適切な湿度・温度・収納環境を保つことで、長く美しい状態を保つことができます。
中学生にも分かるまとめ
ガッシュと油彩は「水で落とせるかどうか」「乾く速さ」「仕上がりの質感」が大きな違いです。ガッシュは水性で紙の上に強く色を乗せやすく、修正は少し難しい場合があります。油彩は油性で時間をかけて色を混ぜられ、陰影の深さが魅力ですが匂いがあって道具の手入れにも時間がかかることがあります。選ぶときは、描きたい雰囲気、作業の時間、保存のしやすさを考えましょう。部活の課題や美術の授業、趣味の作品づくりにおいて、いくつかの練習を重ねるうちに、あなた自身のベストな絵具が見つかるはずです。
最終的には、両方を使い分けるのが理想的です。例えばポスターのような明るくはっきりした表現にはガッシュ、深い陰影と滑らかな色の移行には油彩を選ぶと、作品の幅がぐんと広がります。上手く使い分けるコツを覚えて、楽しみながら練習を続けていきましょう。
ガッシュの話を友達と雑談していてふと気づいたことがある。水性のガッシュは乾燥が速い日もあれば湿度が高い日にはむしろ乾きが遅くなることがあり、同じ色を塗っていても場所や温度で見える色が微妙に変わる。だから練習の時は、同じ色を別の紙に何枚も塗ってみて、乾燥の状況に左右される色の表情を実感するのがいい。薄い色を先に置いてから濃い色を重ねると、透明感と不透明感のバランスが分かりやすくなる。油彩はその逆で、じっくり色を重ねていくと、光の反射が深くなるような陰影が生まれてくる。これを友だちと話すと、“色の重なりが絵の命”という新しい発見につながるんだ。





















