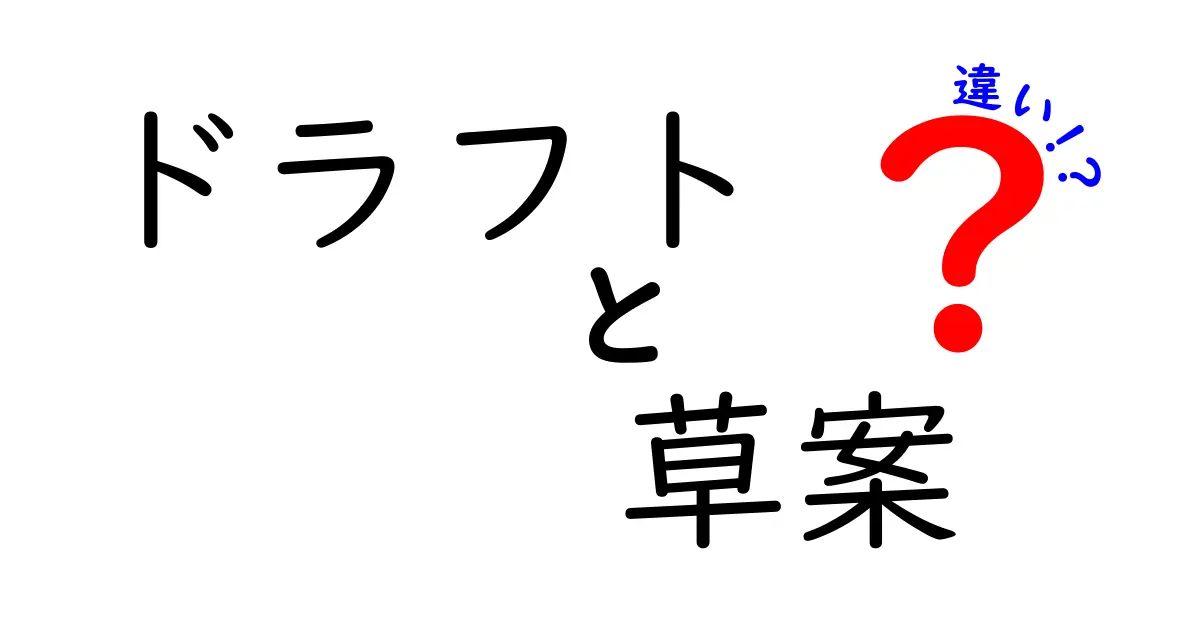

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ドラフトと草案の違いを正しく理解する: 使い分けのコツと実例
ドラフトはまだ完成していない仮の版を指します。学校の宿題や会社の企画書など、どんな場面でも最初に作る文書はドラフトとして扱われることが多いです。ドラフトの特徴は 未確定 な部分が多く、語彙の選択や段落の順序、図表の配置などを大きく変える余地がある点にあります。会議で意見を集めたり、同僚からのフィードバックを受けてアイデアを広げるための土台として使われます。よくあるパターンとして、ドラフトは“仮の形”として公開することは少なく、内部で整備する段階の資料として回されることが多いです。
さらに、ドラフトは語調が カジュアルで、引用をそのまま使うかどうか、文体をどう統一するかといった点も未定義のまま残されることが一般的です。
草案はドラフトより完成度を意識した文書です。公的な提出物や社内の正式な報告書、提案書などで草案という言い方をします。草案には目的、背景、問題点、提案内容が整理され、読み手がすぐに理解できる構成になっていることを前提とします。関係者の意見を反映させるための章立てや説明の順序が整い、表現の揺れを減らす工夫も多く見られます。草案は提出前の最終確認を受けやすく、 厳密な言い回し や専門用語の統一が求められる場面が多いのが特徴です。
要するに、ドラフトは作成の過程で活用する“道具”であり、草案は公開や提出を前提とした“完成形に近い案”です。場面の違いは重要で、先生や客先に見せる時は草案・最終案の方が適切になることが多いです。使い分けのコツは、相手と目的を意識して表現のレベルを決めることです。
実務での使い分けのポイント
実務での使い分けのコツは、事前の設問と読者を決めることです。例えば、上司に提出する草案と、同僚間で修正するドラフトでは求められる内容と表現のレベルが異なります。ドラフトの場合、アイデアの自由さを活かして新しい発想をどんどん書き込むことが重要です。草案の場合は、事実関係の正確さ、引用の適切さ、専門用語の統一、段落の流れを重視します。多くの職場では、ドラフトを複数人で読み、草案として一本化するまでの過程を明確に区分します。最後に、フォーマットや書式の統一を徹底するのがポイントです。
草案という言葉を使うとき、私はいつも友だちと雑談していた出来事を思い出します。草案は名前のとおり“案の草”で、まだ土の上に根を張っていない苗のようなものです。私たちは授業の資料づくりで草案を回して、皆のコメントをもらい、用語の統一や段落の順序を整えました。ドラフトが自由奔放な走り書きだとすると、草案は目的地を示す設計図。何を伝えるべきか、誰に伝えるのかを意識したうえで、情報の順序や根拠の提示を整えます。そんな過程こそ、文章力を磨く近道だと感じました。
次の記事: 図録と目録の違いを完全解説!用途別の使い分けと実例が分かるガイド »





















