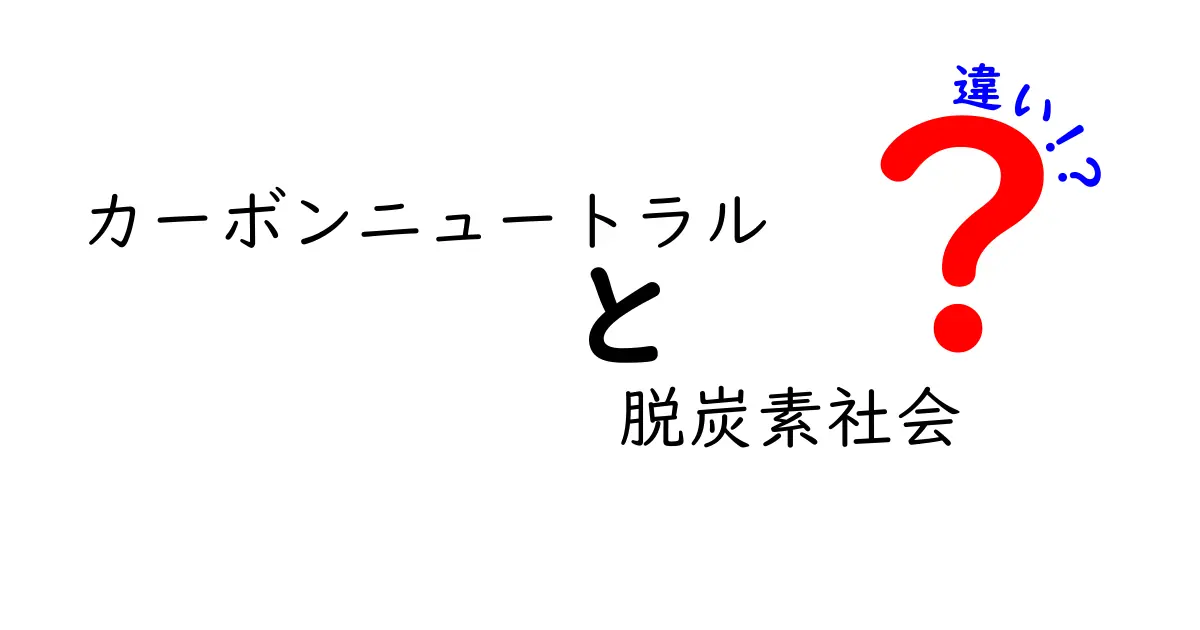

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カーボンニュートラルとは何か?
カーボンニュートラルとは、簡単に言うと『排出した二酸化炭素の量を実質ゼロにすること』を指します。例えば、車や工場から二酸化炭素が出ても、その分を植林や再生可能エネルギーを使うことで同じだけ吸収・削減すれば、結果的に大気中の二酸化炭素の増加を防ぐことができます。
この考えは地球温暖化対策の基本であり、世界中の多くの国や企業が目標に掲げています。発生したCO2を『相殺』し、プラスマイナスゼロにすることが、カーボンニュートラルの意味です。
たとえば、飛行機に乗ると二酸化炭素が出ますが、植林活動にお金を払ってその分を吸収してもらうことで、カーボンニュートラルにすることができます。ただし、それはあくまで全体の収支で見た話です。
脱炭素社会とは?
一方、脱炭素社会とは二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出を大幅に減らし、できるだけ排出しない社会のことです。つまり、もともと排出しない技術や生活方法、エネルギーを使って社会全体で環境にやさしい状態を目指します。
この社会では再生可能エネルギーの利用が広がり、石炭・石油などの化石燃料の使用が減ります。また、省エネや電気自動車、さらには生活様式の変化なども含まれます。排出そのものを抑えることがポイントです。
脱炭素社会はいわば、カーボンニュートラルを達成するための理想的な社会の形そのものといえます。
カーボンニュートラルと脱炭素社会の違いまとめ
二つの言葉はよく似ていますが、意味やイメージには違いがあります。以下の表にわかりやすくまとめました。
| ポイント | カーボンニュートラル | 脱炭素社会 |
|---|---|---|
| 意味 | 排出したCO2を吸収や削減でプラスマイナスゼロにすること | そもそもCO2排出をできるだけ減らし、排出しない社会を目指すこと |
| 手法 | 排出した分を相殺する(植林、カーボンクレジットなど) | 再生可能エネルギー、省エネ、電気自動車など排出抑制 |
| 特徴 | 排出はあるが吸収でバランスをとる | 排出そのものの大幅削減が目標 |
| 目指す姿 | 排出量と吸収量のバランスが取れた状態 | 持続可能な社会・経済の実現 |
まとめると、カーボンニュートラルは排出と吸収のバランスを調整する考え方であり、脱炭素社会はできるだけ排出をしない社会の実現を目指すものと理解できます。
現代の環境問題に取り組むためにはこの両方が重要で、脱炭素社会を進めつつカーボンニュートラルを目標として取り組むことが欠かせません。
カーボンニュートラルという言葉、聞くと何となく難しそうですが、実は身近な例で考えるとわかりやすいです。例えば、あなたがジュースを飲むとき、その容器をリサイクルしたり、ゴミを分別したりするのも広い意味での環境配慮。でもカーボンニュートラルでは、出したCO2を自然や技術で吸収して増やさないようにすることが大事。最近では、航空会社が飛行機のCO2を植林などで打ち消す取り組みも増えています。こうした努力が"実質ゼロ"を作りだしているんですね。ちょっとした行動が未来につながるって、なんだかワクワクしませんか?





















