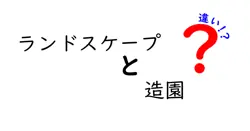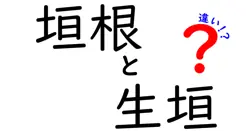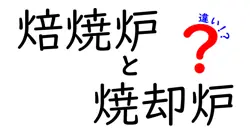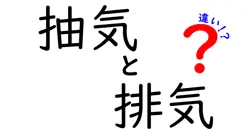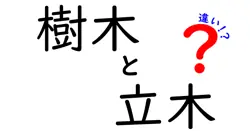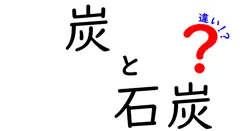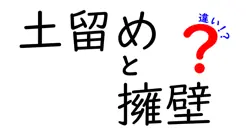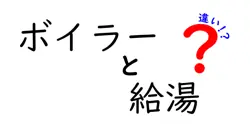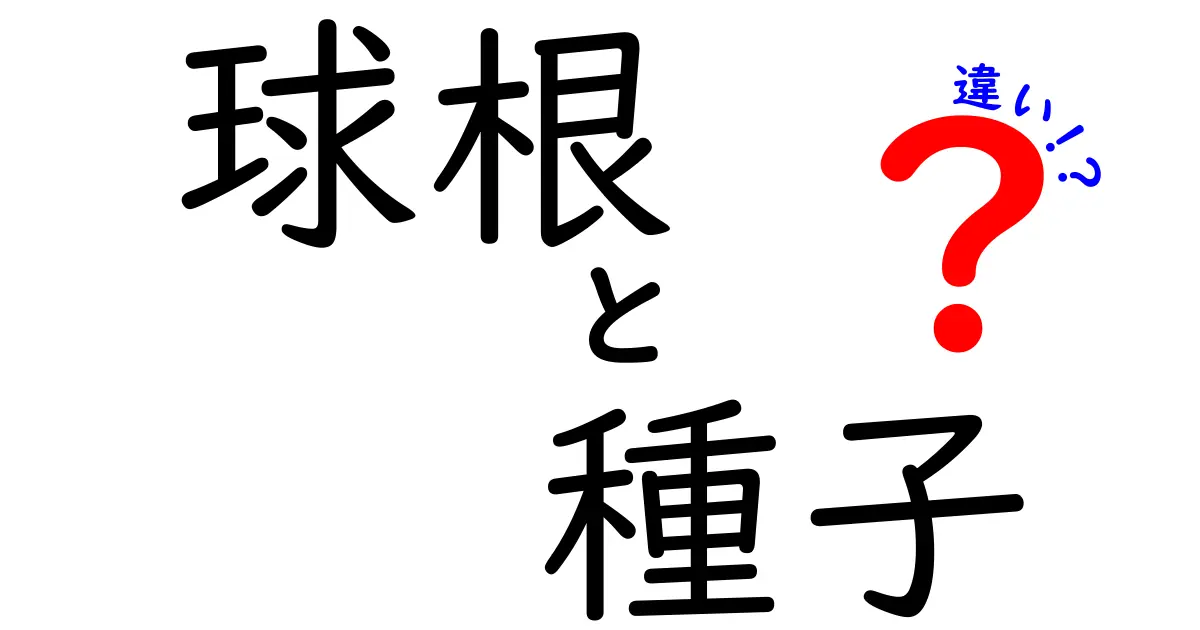
球根と種子の違いとは?基本から理解しよう
植物を育てるときに聞く「球根」と「種子」。どちらも新しい植物を育てるための方法ですが、その仕組みや特徴は大きく異なります。ここでは、まず両者が何なのかをご紹介します。
球根とは、植物の地下部にある茎や葉が肥大してできたもので、そこに栄養がたっぷりと蓄えられています。このため、球根からは直接植物が育つことができます。例えば、チューリップやヒヤシンスなどが有名です。
一方、種子とは、花が咲いた後にできる、小さな新しい植物のもとになる部分です。種子の中には栄養源と胚と呼ばれる未来の植物の小さな姿が入っています。これは発芽してから根や芽を伸ばすことで新しい植物となります。一般的な草花や野菜の多くは種子から育ちます。
このように、球根は植物の体の一部が変化したもので、種子は新しい植物そのもののもとという点が大きな違いです。
球根と種子の育て方や成長の違いを見てみよう
球根と種子はその特徴が違うため、育て方や成長の仕方にも違いがあります。ここで、球根と種子の育て方と成長の違いを詳しく見ていきましょう。
まず球根からの育て方。球根はすでに栄養が十分に蓄えられているため、土に植えると比較的早く芽を出します。水やりや温度管理をしっかりすることが大切ですが、初めから大きな力で成長できるのが特徴です。植えっぱなしで翌年も花を咲かせることができることも多いです。
対して種子から育てる場合は、種子のまま栄養源は少ないため、発芽に適した環境作りが必要です。土の湿度や温度が発芽に大きく影響し、比較的時間もかかります。発芽してからは根をしっかり張り、ゆっくりと植物が成長していきます。
つまり、球根は植えたその年から元気に育ちやすいのに対して、種子は少し手間と時間をかけて育てる必要があるのがポイントです。
球根と種子の違いをわかりやすく表でまとめる
最後に、球根と種子の違いを簡単にまとめた表を作りました。
| ポイント | 球根 | 種子 |
|---|---|---|
| 植物の状態 | 肥大した地下茎や葉の一部 | 新しい植物のもと(胚と栄養を持つ) |
| 栄養の有無 | 栄養がたっぷり蓄えられている | 少量の栄養が胚にある |
| 成長の速さ | 早く芽を出し育つ | 発芽まで時間がかかる |
| 育てやすさ | 比較的簡単で初心者向き | 環境管理が必要で難しいこともある |
| 再利用性 | 翌年も花を咲かせることが多い | 一度成長すると種はできるが同じ種子では繰り返せない |
このように、球根は植物の体の一部で直接育つことができ、種子は新しく植物が育つための材料として別のプロセスが必要です。育て方や目的に応じて使い分けるとよいでしょう。
「球根」って単に植物の一部だと知ると、実はすごく便利な自然の仕組みなんです。植物が冬を越すために栄養と成長の元を地下に蓄えていて、春になるとそこから元気に芽を出すんですよね。つまり、球根は植物の“備蓄食料”のようなもので、園芸初心者にも育てやすい特徴があります。種子に比べて早く芽が出るので、待つのが苦手な人にもおすすめなんです。