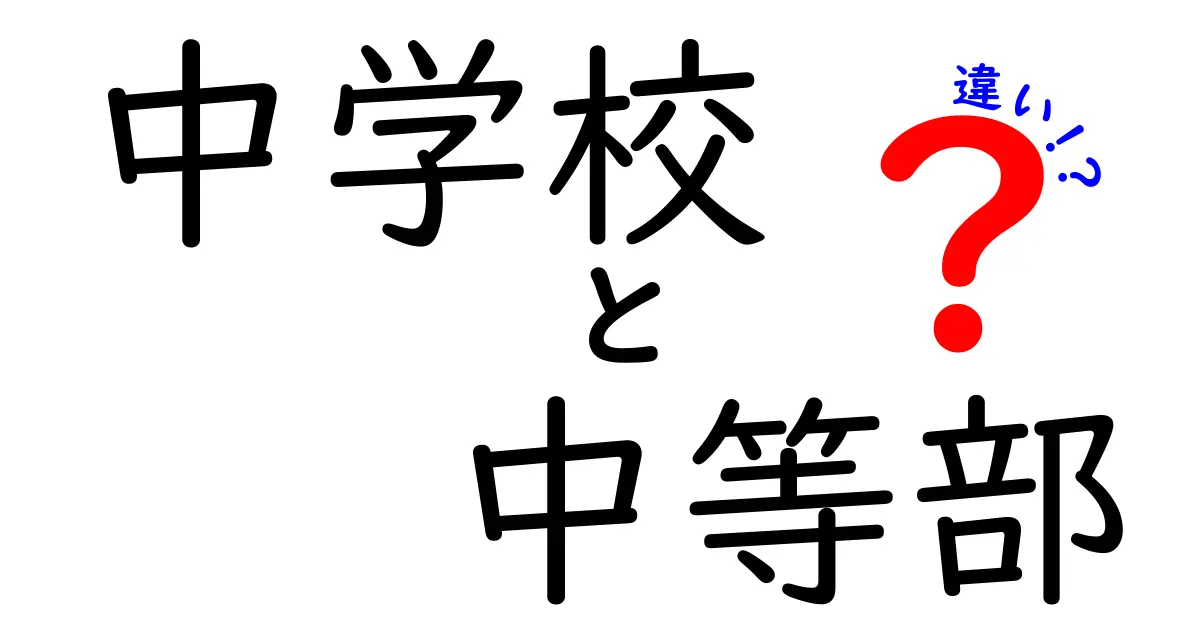

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
中学校と中等部は何が違う?基本の違いを理解しよう
中学校と中等部は、どちらも義務教育の一環として存在している学校ですが、実はその仕組みや設置される学校の種類が異なります。まずは基本的な違いから見ていきましょう。
中学校は、日本の義務教育の後半部分であり、通常は小学校卒業後の3年間を指します。生徒は12歳~15歳の年代が通う学校で、各地域に設置されている一般的な学校です。
一方の中等部は、中等教育学校の初等段階にあたり、「中高一貫校」と呼ばれる学校に設置されています。この場合、中等部は中学校に相当する教育課程を持ちますが、通常3年間の教育を行い、中等部終了後は高等部(高校相当)に進む流れが多いです。
つまり、中等部は主に中高一貫校の一部として存在し、連続した6年間の中等教育を目指すものですが、中学校は単独で義務教育の後期を担っているわけです。
この構造の違いが、それぞれのカリキュラムや学校の特徴に影響を与えています。
中学校と中等部の教育課程やカリキュラムの違い
次に、具体的な教育内容の違いを見てみましょう。中学校のカリキュラムは文部科学省の義務教育課程に沿って決められており、基礎的な科目を3年間で学びます。
中等部の場合は、中高一貫教育の一部であるため、高校の内容も見据えた教育が行われています。これにより、中学校よりもやや早めに専門的な教科内容を始めたり、発展的な授業を取り入れることもあります。
例えば、数学や理科の内容が中等部のほうが難しく、進度も速いことが多いです。また、英語教育にも力を入れている学校が多く、海外留学や国際交流の機会が充実している中等部もあります。
この違いは、将来的に大学進学を視野に入れた生徒にとって、有利なスタートになるケースも多いです。
以下に、簡単な比較表を作成しました。
「中等部」という言葉を聞くと、何となく"中学校と違うの?"と思うかもしれませんね。実は、中等部は中高一貫教育のスタート地点です。例えば、6年間続く学校で前半の3年間が中等部として位置づけられています。
ここで面白いのは、中高一貫校では「中学校のカリキュラム」と「高校のカリキュラム」がスムーズに繋がるよう、独自の教育プランが組まれていること。早めに難しい内容に入れる分、勉強もグッと深くなるんですよ。だから、中等部に通う生徒は将来の大学受験に向けて早く準備できるわけです。
こうした仕組みがあるため、進学重視の家庭では中等部を選ぶことが増えていますね。
次の記事: 児童発達支援と日中一時支援の違いとは?わかりやすく解説! »





















