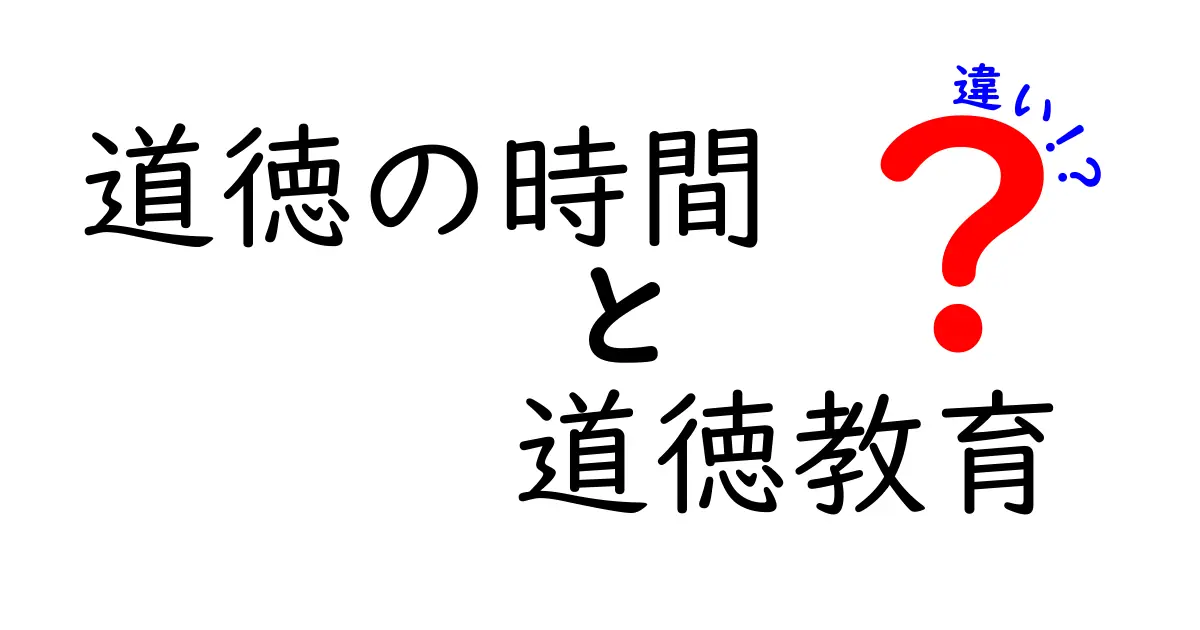

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
道徳の時間と道徳教育の違いとは?
学校でよく耳にする言葉「道徳の時間」と「道徳教育」は、一見似ているようで実は意味が少し違います。
道徳の時間は、学校の時間割の中に組み込まれた授業の一つで、子どもたちが善悪を学ぶ時間です。
一方、道徳教育は、こうした授業のほかにも、学校生活や先生の指導、家庭での習慣なども含めた、広い意味での心の教育を指します。
つまり、道徳の時間は道徳教育の一部分とも言えます。
中学生の皆さんが日々の学校生活で体験する「道徳の時間」とはどのようなものか、これから詳しく説明します。
なぜ道徳の時間は必要なのか?
道徳の時間は、単なる授業ではなく、社会で生きていくために大切な心の持ち方を学ぶ場です。
例えば、友達を思いやる気持ちや、ルールを守る大切さ、正しい判断をする力などがテーマになります。
学校は勉強だけでなく、人間として成長する場所でもあるため、道徳の時間を設けることで、生徒一人ひとりの価値観や考え方を育てようとしています。
こうした時間は、中学生にとって自分自身と向き合うよい機会となります。
道徳の時間の具体的な内容
道徳の時間には、絵本や話し合い、劇などを通じて考える活動が多く取り入れられています。
例えば、ある話を聞いて「もし自分ならどうするか?」を考えたり、友達と意見を交換したりします。
このように、単に答えを教わるのではなく、自分の考えや感じ方を大切にしながら学ぶスタイルです。
これにより、自分の行動がどう人に影響するかを理解しやすくなります。
道徳教育はもっと広い意味!
道徳教育は、授業の枠を超えて学校全体や家庭、社会で行われる教育のことです。
例えば、学校での生活ルールや、友達との関係を学び取る経験、地域のボランティア活動も道徳教育に含まれます。
家庭での親子の関わりや、社会のニュースから学ぶことも大切な要素です。
つまり、道徳教育は日常のあらゆる場面に存在し、自分で考え判断する力を育てることが目的なのです。
表でわかる「道徳の時間」と「道徳教育」の違い
| 項目 | 道徳の時間 | 道徳教育 |
|---|---|---|
| 場所 | 学校の授業時間内 | 学校生活全般、家庭、地域社会など |
| 目的 | 善悪の理解や心の成長 | 価値観形成や社会での行動力の育成 |
| 方法 | 授業・話し合い・教材使用 | 日常生活の経験・交流・指導 |
| 対象 | 児童・生徒全員 | 児童・生徒を含む社会全体 |





















