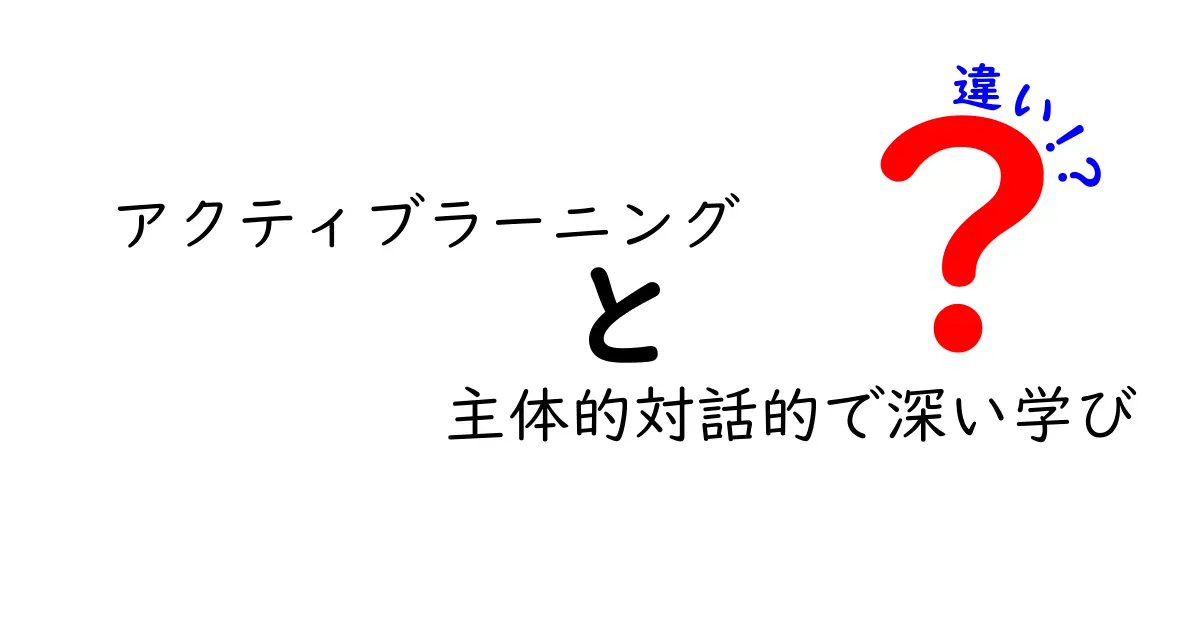

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アクティブラーニングとは何か?
アクティブラーニングは、学校や授業でよく使われる言葉ですが、簡単に言うと「生徒が自分から積極的に学びに参加する方法」です。
従来の教室では先生が話すことを生徒が聞く「受け身の学習」が多かったのですが、アクティブラーニングでは生徒がグループで話し合ったり、発表したり、問題を解いたりすることで、自らの考えを深めていきます。
この方法は、知識をただ覚えるだけでなく、自分で考えたり説明したりする力を伸ばすのにとても効果的です。
学校での授業だけでなく、企業の研修や自己学習の場でも活用されていて、最近とても注目されています。
主体的対話的で深い学びとは?
「主体的対話的で深い学び」は、2016年から日本の教育指導要領で重視されている考え方です。
これは、ただ知識を得るだけでなく、自分から進んで学ぶ「主体的」な姿勢、
友達や先生と話し合って理解を深める「対話的」なやりとり、
そしてその結果として「深い学び」を目指すという3つの要素を大事にしています。
つまり、自分で疑問を持って調べたり、みんなと意見交換したりしながら、単なる暗記ではない本物の理解を進めることです。
この教育方針は、これからの社会で必要とされる「考える力」や「コミュニケーション力」を育てることが目的です。
アクティブラーニングと主体的対話的で深い学びの違いを表で比較
まとめ:違いを理解して学びを深めよう
「アクティブラーニング」と「主体的対話的で深い学び」は、とても似ているけれど少し違う言葉です。
アクティブラーニングは授業などの具体的な学びの方法で、
主体的対話的で深い学びは学びの目標や考え方を表す言葉として使われます。
どちらも、今の社会で必要な「自分で考えて動く力」を育てるための大切な考え方なので、理解して取り組むことで勉強や仕事がもっと面白くなります。
ぜひこの違いを知って、日々の学びに役立ててみてください!
実は「主体的対話的で深い学び」という言葉は、教育の現場でよく「難しそう」と感じられます。でもこれを一言で言うなら「みんなで話し合いながら、じっくり考えて本当の意味を理解すること」。
たとえば、友達とゲームのルールについて話し合うとき、ただルールを覚えるだけでなく、どうしてそのルールがあるのか考えたり、新しいアイディアを出し合ったりすることと似ています。
こんな風に見方を変えると「主体的対話的で深い学び」って、実はとても身近で楽しいことなんですよ!
前の記事: « 社会情動的スキルと非認知能力の違いとは?わかりやすく解説!





















