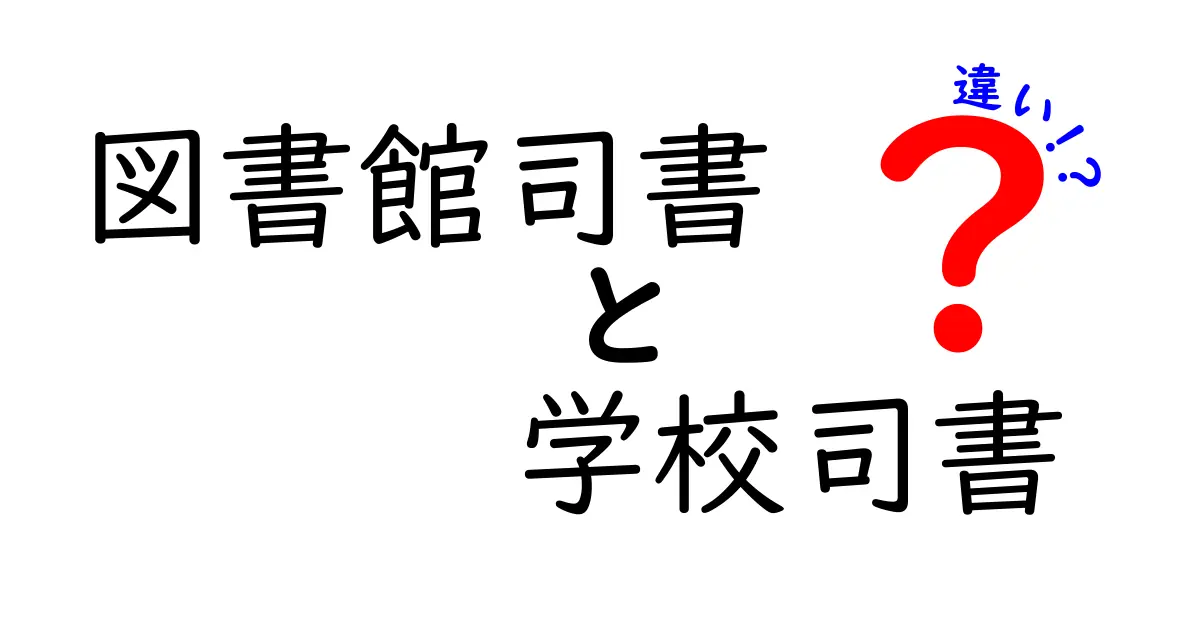

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
図書館司書と学校司書とは?基本の違いを知ろう
図書館司書と学校司書は、どちらも本や資料を扱う仕事ですが、その働く場所や役割には明確な違いがあります。
図書館司書は公共図書館や大学図書館など、地域や専門の大きな図書館で働きます。一般の人々が自由に利用できる図書館を運営し、蔵書の管理や貸し出し、イベントの企画などを行っています。
一方、学校司書は小学校から高校までの学校内に設置された図書室で働き、主に生徒や教職員のために資料を整え、読書指導や調べ学習の支援も行います。学校の教育活動の一環としての役割が強いのが特徴です。
このように、働く場所や利用者が違うことがまずポイントです。
仕事内容の違いを詳しく解説
図書館司書の主な仕事は、図書や資料の貸し出し・返却の管理、蔵書の選定や購入、利用者の相談対応、イベントの企画などです。
地域の幅広い年齢層が利用するため、多様なニーズに応えることが求められます。
また、資料のデジタル化や地域との連携も重要な役割です。
学校司書の仕事は、授業や学習に役立つ本や資料の準備、読書推進活動、調べ学習のサポート、教員との協力など、教育現場に密着した内容が中心です。
生徒が自分で調べたり、興味を持って読書したりできるよう手助けすることが重要です。
このように利用者と目的の違いから、それぞれの仕事の具体的な内容はかなり異なります。
図書館司書と学校司書の資格や求められるスキルの違い
図書館司書になるには、一般的に「司書資格」を取得する必要があります。これは大学や専門学校の司書課程を履修し、指定の単位を取ることで得られます。
また、図書館で働く場合はさらに専門職員などの資格や経験が求められることもあります。
学校司書も同様に司書資格が基本ですが、学校現場の知識や子どもとのコミュニケーション力が特に重要とされます。
最近は「学校司書教諭資格」や「学校司書資格」が別に設定されている自治体もあり、教育面の専門性がより求められています。
つまり、資格は共通する部分もありますが、学校司書は教育支援の知識とスキルが強く求められる傾向があります。
図書館司書と学校司書の違いをまとめた表
このように、図書館司書と学校司書は基本資格が似ているものの、働く場所や目的、求められる役割やスキルには違いがあります。
どちらも本や資料を通じて、多くの人の学びや情報アクセスを支える大切な仕事ですので、自分の興味や適性に合わせて選ぶことが重要です。
学校司書という言葉を聞くと、普通の図書館司書とあまり違いがないように感じるかもしれませんが、実は学校司書は教育の現場でかなり重要な役割を担っています。単に本を貸したり整理したりするだけではなく、子どもたちが学習で使いやすいように資料を整えたり、教員と協力して調べ学習の支援をしたりもします。つまり、学校司書は先生と図書担当の両方の役割を少し持っていて、子どもたちの「学びをサポートする特別な司書」と言えますね。だから学校司書になるには、教育の知識やコミュニケーション能力もとても大切なんですよ。





















