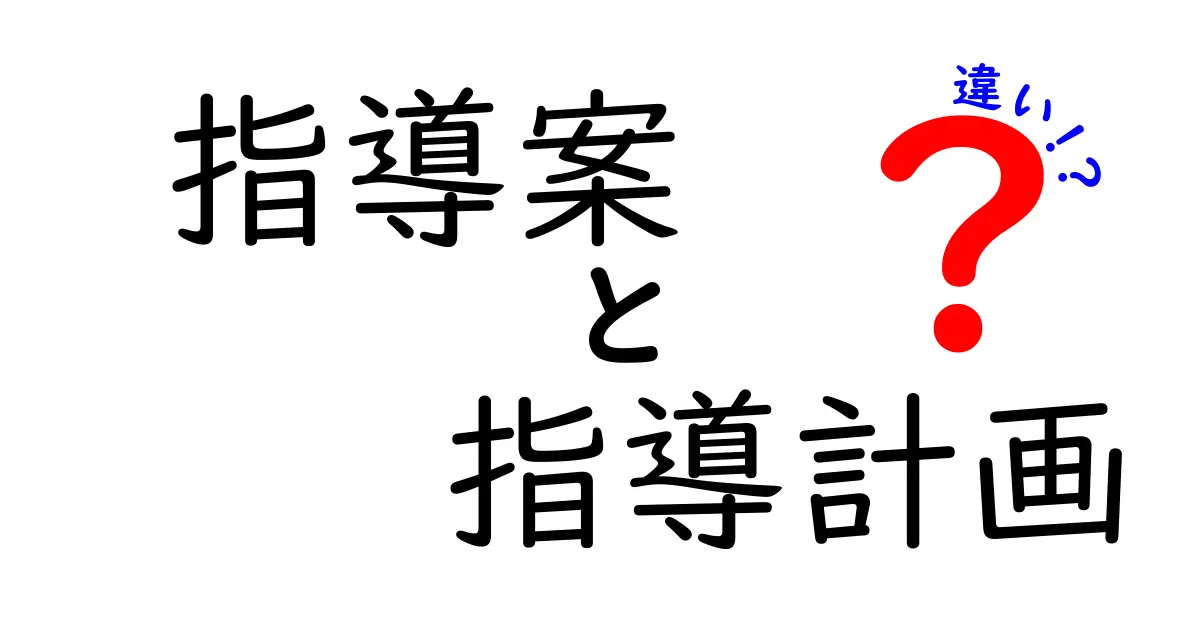

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
指導案と指導計画の基本的な違いとは?
教育の現場でよく使われる言葉に「指導案」と「指導計画」があります。似たような言葉なので混同されがちですが、実は意味や目的に違いがあります。
まず、指導計画は一年間や学期などの長い期間を見据えて、どんな内容をどのような順番で教えるか全体的に組み立てるものです。これは教師が年間を通してどの単元をいつ扱うか、単元の目標や大まかな方法をまとめた「計画表」のようなものです。
一方、指導案は授業一回分や一単元といった具体的な授業内容についての詳細な計画です。どのような教材を使うか、授業の導入や展開・まとめをどのように進めるかなど、教師が授業中に行う具体的な活動を細かく書き出します。
つまり、指導計画は全体の設計図、一方指導案はその設計図をもとにした具体的な建物の設計書と思うとイメージしやすいでしょう。
これらの違いを理解することは、効率的な授業準備や教育効果の向上にとても重要です。
指導計画の特徴と役割
指導計画は教師が年間・学期単位で作成する教育計画のことを指します。
具体的には、学習指導要領をもとに、年間目標や各学期の目標を設定し、各単元の配分や順序を決めます。
メリットとしては、長期間の流れが見えるため、計画的に授業を進めやすくなることです。全体のバランスや進捗を把握しやすく、期間内に必要なカリキュラムを無理なく消化できます。
また、校内での授業共有や指導の統一を図る際にも重宝します。異なる教師間で内容のずれが少なくなるので、生徒の学習にムラが生じにくくなります。
指導計画はタイムスケジュールや年間の目標がベースであり、教育全体の枠組みを作る重要な設計図のような役割を果たしているのです。
指導案の特徴と作成のポイント
指導案は具体的な授業内容を細かく計画したもので、通常は1回の授業や1単元分の詳細計画です。
内容としては、授業の目的、教材や教具の準備、導入の方法、展開(活動の順序や内容)、まとめ、板書計画や評価方法などが含まれます。
指導案を書くことで、教師は授業の流れをイメージしやすくなり、効果的な指導ができます。
作成のポイントとしては、生徒の理解度や反応を予想し、柔軟に対応できる設計にすることが大切です。また教材の使い方や時間配分のバランスもよく考慮しましょう。
さらに、振り返りや次回授業への課題も記入しておくと、授業の質を向上させる助けとなります。
指導案は詳細な授業の設計書として、授業の成否に大きく影響します。よく練られた指導案は教師の自信にもつながり、生徒の学びを深める効果が期待できます。
指導案と指導計画の違いを表で比較
| 項目 | 指導計画 | 指導案 |
|---|---|---|
| 目的 | 年間・学期の教育目標と内容の大枠を設定する | 具体的な授業の展開方法や内容を詳細に計画する |
| 範囲 | 長期間(年・学期単位) | 短期間(1回の授業や単元単位) |
| 内容 | 単元の配分や順序、目標など大枠 | 授業毎の活動、教材、時間配分、板書や評価など詳細 |
| 作成者 | 担当教師や学校全体 | 授業担当教師 |
| 用途 | 教育の全体設計と管理 | 授業の具体的実践の準備と改善 |
まとめ:違いを理解してより良い教育を目指そう
今回は「指導案」と「指導計画」の違いについてわかりやすく解説しました。
両者は似ていますが、指導計画は教育活動の年間や学期という全体的な枠組みを作る設計図であり、指導案は個別の授業をどう進めるか詳細に計画した設計書です。
この違いをしっかり理解すれば、効果的な授業準備や教育の質の向上が期待できます。教師だけでなく教育に関わる方にも知ってほしい基本知識です。
ぜひ実際の教育現場でも、指導計画と指導案の両方をうまく活用して、子どもたちが楽しく学べる環境作りを目指してくださいね。
指導案という言葉を聞くと「ただの授業の計画」と思いがちですが、実はかなり細かく授業の全てが設計されているんです。たとえば、どの順番で説明するか、どんな質問をするか、板書の内容や時間配分まで…。これほど細部にこだわるのは、授業の成功を確実にするため。指導案を書くときは、教師が“その瞬間の生徒の反応”まで予想して準備していることが多いんですよ。だからこそ、指導案は単なる計画以上の“授業の設計図”として、教育の質を高める重要なツールなんです。
前の記事: « 指導案と日案の違いとは?初心者でもわかる教育現場の基本書類ガイド





















