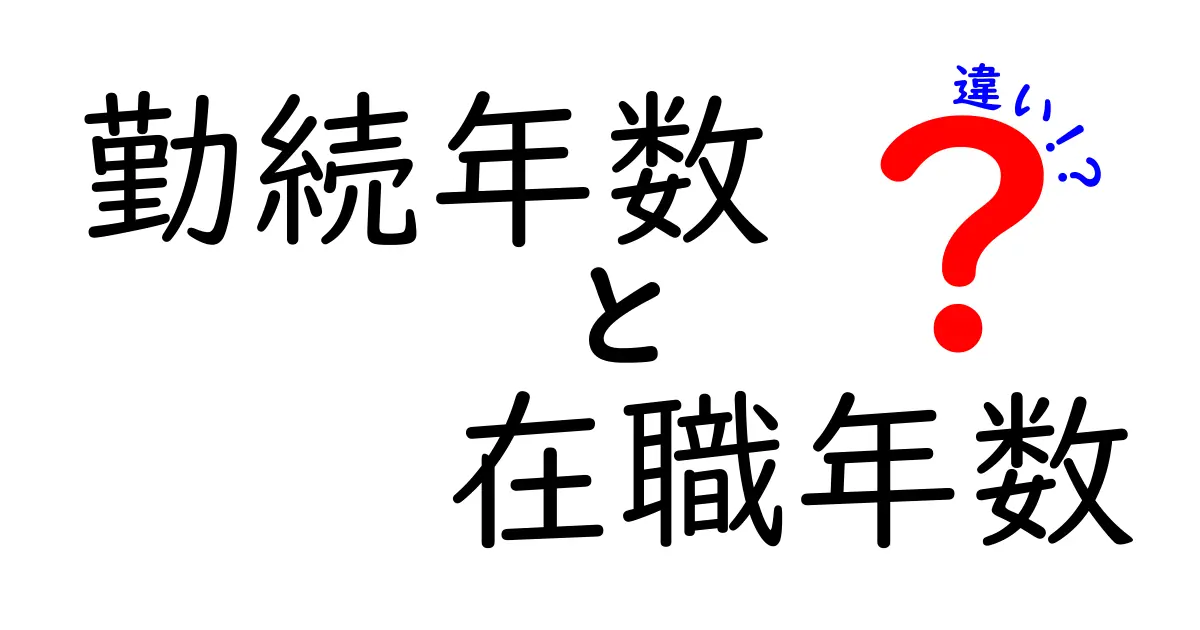

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
勤続年数と在職年数の違いって何?
みなさんは勤続年数と在職年数という言葉を聞いたことがありますか?どちらも会社でどれくらい働いているかを表す数字ですが、その意味には実は違いがあります。
まず、勤続年数というのは、会社に入社してから休まずに働いた期間を指します。例えば、会社を辞めてしまったり、退職してから再入社した場合は、その期間は別々にカウントされることが多いです。
一方で、在職年数は、その会社にいた合計の期間を表します。途中で休んだり、転職後に戻ったりしても、累計で計算されることもあります。
この違いがわかれば、書類を書くときや人事評価のときにとても役立ちます。
勤続年数と在職年数の具体的な違いを表で確認しよう
言葉だけではわかりにくいので、以下の表で確認しましょう。
具体例でわかる!勤続年数と在職年数
例えば、田中さんが2015年に入社し、2018年に一度退職、2020年に再入社した場合を考えます。
・勤続年数は2015年から2018年の3年間と、2020年から現在までの期間が別々にカウントされることが多いです。つまり3年+再入社後の年数。
・在職年数は2015年から2018年までの3年間と2020年から現在までの期間を足したもの、つまり合計の期間となります。
この違いは、会社の規定や人事制度によっても変わりますが、基本的な考え方はこのようになっています。
なぜ勤続年数と在職年数の違いを知ることが大切なの?
勤続年数は昇進やボーナスなど、職場の評価に大きく影響します。途切れがあればリセットされる可能性があり、次のチャンスに影響するかもしれません。
一方、在職年数は年金や退職金、社会保険の計算に使われることが多いです。合計で計算されるため、転職や休職の影響が少ない場合があります。
なので、自分のキャリアを把握したり、転職活動や退職時の手続きをするときには、この違いを理解しているととても便利です。
特に社会保険の手続きや年金の受給資格をチェックする際には在職年数が重視されるケースがあり、混同しないように注意しましょう。
勤続年数って聞くと、なんだかすごく長く頑張った感じがしてモチベーションが上がりますよね。でも実は、勤続年数は"連続して働いた期間"のことを言うので、例えば途中で退職や休職をはさむとリセットされることが多いんです。一方で、在職年数は”その会社にいた合計期間”なので、休んだ期間があっても合計で計算されることがあります。この違いを知っておくと、特に転職や退職の時に役立ちます。勤続年数がリセットされることにショックを受けないように、ちゃんと仕組みを覚えておきましょう!
次の記事: 勤続年数と年金の違いとは?わかりやすく解説! »





















