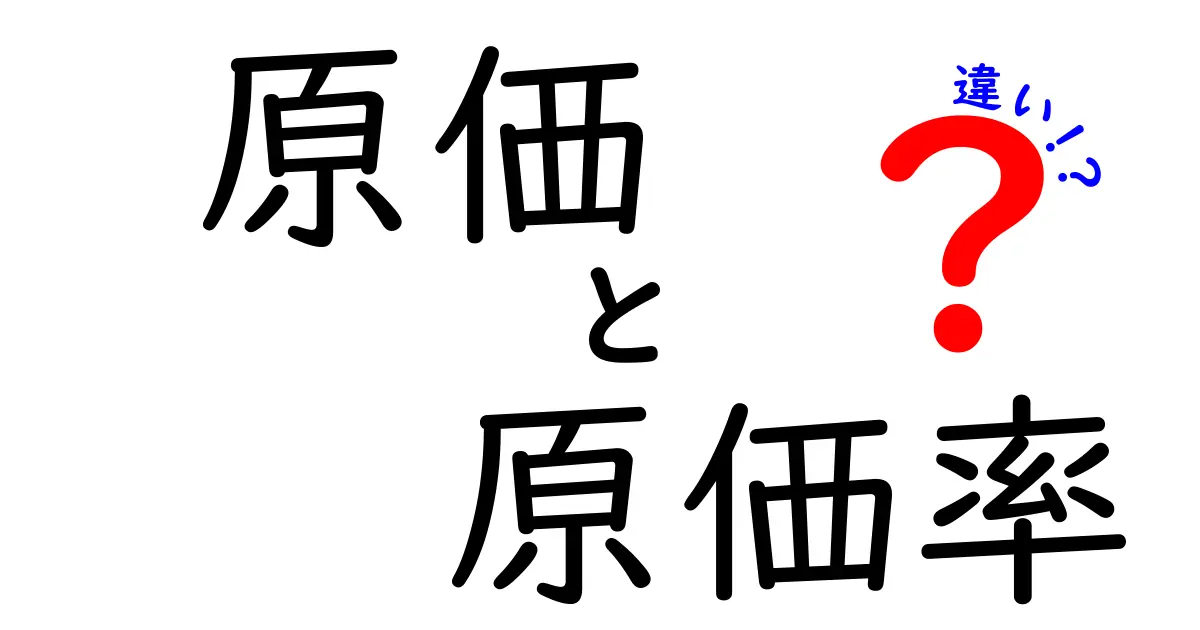

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
原価と原価率の意味を理解しよう
ビジネスやお店でよく聞く「原価」と「原価率」という言葉。似ているようで実は意味がぜんぜん違うんです。
原価は、商品を作るためにかかったお金のこと。材料費や仕入れ費、加工費などを全部合計した数字です。たとえばケーキを作るときの小麦粉や砂糖、バターの値段や、お店で働く人の給料の一部も原価に含まれます。
一方、原価率は、その商品の販売価格に対する原価の割合をパーセントで表したもの。簡単に言うと「この商品が売れたとき、どのくらいのお金が材料などに使われたか」の割合です。
この2つは、ビジネスのお金の管理や価格設定でとても大事なポイントになります。
原価と原価率の計算方法と違い
では、具体的にどうやって計算するのか見てみましょう。
原価の計算方法:
商品の材料費+加工費+その他の費用=原価
例えば、パンの材料費が100円で、パンを焼くためのガス代や人件費が50円かかれば、原価は150円になります。
原価率の計算方法:
原価 ÷ 販売価格 × 100=原価率(%)
たとえば、パンの販売価格が300円だったら、原価率は150円÷300円×100=50%となります。
この計算からわかるように、原価は金額そのもので、原価率は割合で表す指標です。
原価だけ見てしまうと、商品がいくらで売られているのか分からないため、原価率を知ることが利益を考えるうえで重要になります。
原価と原価率を使う場面とそのポイント
両者はビジネスの現場で、それぞれこんな場面で役立ちます。
- 原価:商品のコスト管理や仕入れ価格の計算に使う。材料をどれだけ買うべきか考えるときに便利。
- 原価率:利益率のチェックや価格設定に役立つ。例えば、原価率が高すぎると利益が少ないので値上げやコスト削減を検討することが多い。
原価率を適切に管理できると、無駄なコストを減らし、より効率的な販売が可能になります。
以下の表で簡単に比較してみましょう。
| 項目 | 意味 | 使い方 |
|---|---|---|
| 原価 | 商品を作るためにかかった費用の合計 | 材料費や労務費の管理 |
| 原価率 | 販売価格に対する原価の比率(%) | 利益管理、価格設定 |
まとめ
原価は「金額」そのもの、原価率は「割合」で、この2つを正しく理解し使い分けることで、売上や利益をより良くコントロールできます。原価が同じでも売値によって原価率は変わるため、数字を比較するときは注意しましょう。
原価率って、単なる数字の比率以上にビジネスの賢い指標なんです。例えば、同じ商品でも原価率が10%より50%の方が利益が少ないけど、原価率だけを見て安い商品と思うのは間違い。販売価格と合わせて考えないと、本当の利益はわからないので、数字の裏側を見る感覚が大切ですよね。こういう話をすると、一気に実務的で面白くなりますよ!
次の記事: 労務費と法定福利費の違いとは?初心者でもわかる詳しい解説 »





















