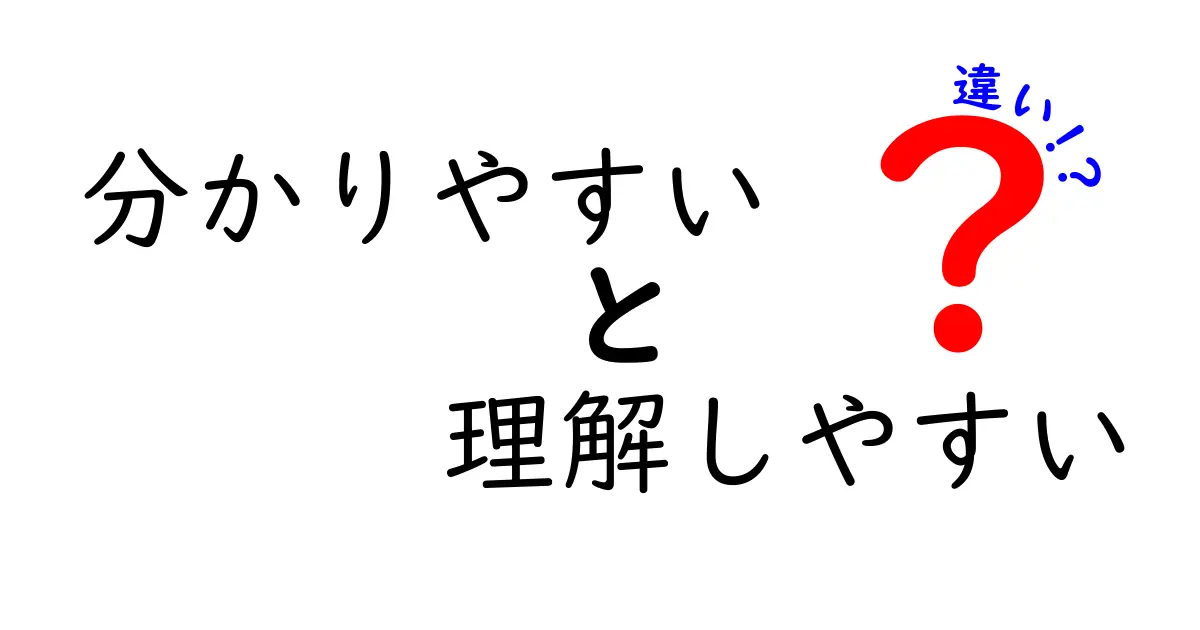

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
分かりやすいと理解しやすいの違いを徹底解説
説明をするときに使われる言葉にはいくつかの似た意味が混ざりがちです。その中でも特に「分かりやすい」と「理解しやすい」は混同されやすいですが、実は指す視点が違います。
まず分かりやすいとは、受け手が受け取った情報の入口で“すぐに印象としてつかめる”ことを指します。例としては短い文章、平易な語彙、視覚的な図解、箇条書きといった外見上の工夫が挙げられます。
一方理解しやすいとは、受け手が内容を頭の中で“順序立てて理解する過程”を支える設計を指します。ここでは論理の組み立て、前提知識との結びつき、原因と結果の説明、具体例の連鎖といった内的な構造が重要です。
このように、分かりやすさが入口の設計を指すのに対して、理解しやすさはその入口から先の思考の組み立て方を指す点が大きな違いです。
教育現場や業務の場面でこの違いを理解して使い分ければ、最初のつかみだけで終わらず、学習者の持つ疑問を順次解消していくことができます。
例えば、授業の導入では分かりやすさを重視して入口を広く開き、授業の中盤には理解しやすさを高めるために論理のつながり・理由づけ・前提の確認を丁寧に行うと、学習の流れを止めずに深い理解へと導くことができます。
また、説明の場面で重要なのは受け手の背景を想定することです。初学者には専門用語を避け、日常的な例を多用する分かりやすい表現が有効です。一方で、同じ話題を深く掘り下げるときには、前提知識を確認しながら段階的に情報を積み上げ、理解しやすさを支える構造を意識する必要があります。
さらに、表現の一貫性を保つことも大切です。用語の意味を統一し、同じ事象を複数の角度から説明する際には順序を変えず、因果関係を明確に示すと、理解のズレを減らせます。こうした視点を組み合わせることで、最初の印象だけで終わらず、学習者が自分で考え、応用できる力を育てることができます。
違いを知ると伝え方が変わる:実践例と注意点
次に、具体的な場面での違いを見ていきましょう。文書作成、プレゼン、授業、説明の場面で、用語の使い方を変えると受け取り方が変わります。
重要なのは三つの観点です。誰に向けて話すのか(対象者)、何を伝えたいのか(目的)、どの程度の詳しさが適切か(深さ)。この3点を意識して、分かりやすい・理解しやすいの順に配慮すると、メッセージがスムーズに伝わります。
以下の表は、具体的な差を整理したものです。
この表を日常の説明に当てはめると、同じ話題でも最初は分かりやすい表現で入口を作り、続く説明で理解を深める、という段階を作ることができます。
さらに、実際の場面での工夫として、次の3つを意識すると良いでしょう。1) 相手の背景に合わせた用語選び、2) 情報の流れを一貫させる、3) 質問を投げて双方向性を高める。これらを実践すると、受け手は情報の入口だけでなく、全体の骨格も理解しやすくなります。
理解しやすいという言葉は、学習者の頭の中の道筋を丁寧に整えるときに使います。ある日、友人のミキと私は、数学の公式を理解するコツについて話しました。最初は難しそうに見える公式でも、理由と例を結びつけ、ステップごとに確認することで、頭の中に道の地図が描かれます。私たちが使ったのは、まず公式の意味を日常の現象と結びつけ、次に順序を整理する『因果の順序』を明確にする、そして最後に確認の質問をいくつも作って、思考の流れを閉じ込める、という方法でした。この小さな対話は、理解しやすさが単なる語感ではなく、受け手の認知の設計を意味することを教えてくれました。





















