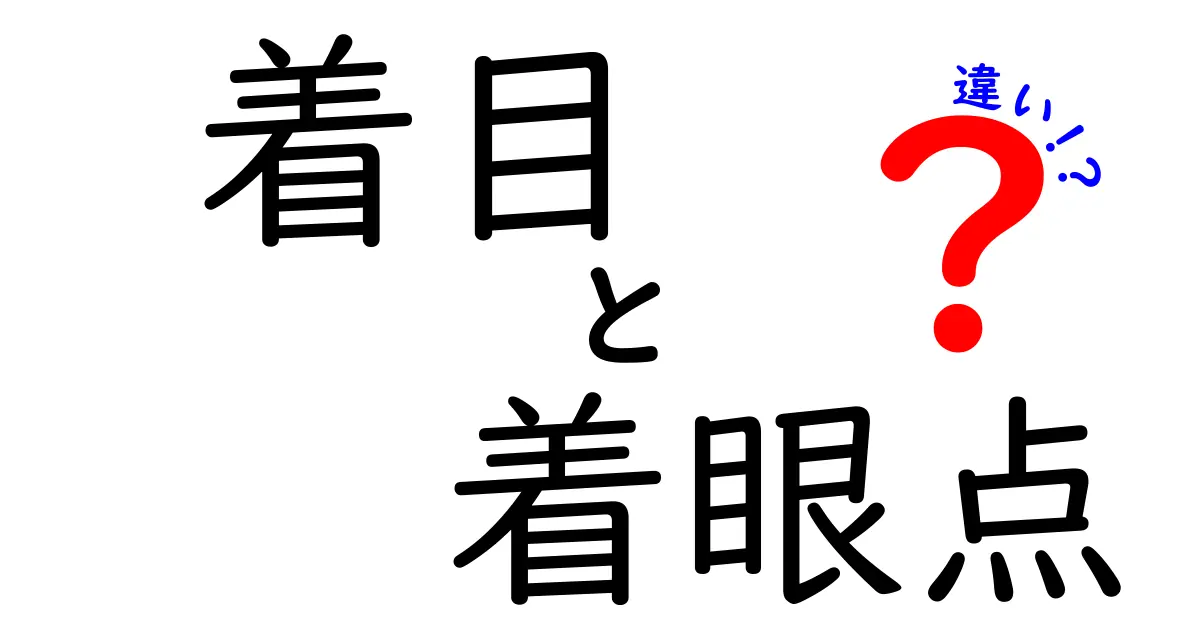

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
着目と着眼点の違いを徹底解説!意味・使い方・例文で中学生にも伝わるポイント
着目と着眼点は日常の会話やニュース、先生の説明、作文などでよく出てくる言葉です。しかし多くの人はこの二つを混同して使ってしまいがちで、結果として伝えたいことがはっきり伝わらないこともあります。ここでは、着目と着眼点の基本的な意味、使いどころの違いを分かりやすく解説します。まず意識するべき点は、どちらも「何かを見つめる」という行為そのものですが、どこに注目するか、どの角度から見るかが異なるという点です。日常の場面を思い浮かべてみるといいでしょう。友達と話すとき、先生の説明を理解するとき、作文のネタを探すとき、私たちはそれぞれ違う着眼点で情報を組み立てます。以下のポイントを覚えておくと、言葉の使い分けが自然になります。
1) 着目は「特定の事柄を意識して見る」意味、2) 着眼点は「物事を見る軸や視点そのものを指す」意味、3) 違いは場面に応じた使い分けが鍵、という整理です。
- 着目 は観察・分析の対象を決める時の語。
- 着眼点 は物事を評価・説明する際の視点・軸を指す語。
- 作文やプレゼンでの使い分けがポイント。
次に、具体的な場面の切り分けを見ていきましょう。学校の授業や日常の生活、仕事の現場など、場面ごとに使い分けることで伝わり方が大きく変わります。
まずは着目、次に着眼点という順序で考える練習をすることで、相手に伝える力を自然と高められます。
着目の意味と使い方
着目は、ある対象の中から「これを特に気にする・見つけ出す」という行為を表します。例えば、作文を書くときは「場面設定の着目点」を決め、それに沿ってエピソードを選びます。見落としがちな小さな情報や、特徴的な要素を意識的に拾い上げることで、文章の核が強くなります。実際の文章例を挙げると、ニュース記事を読むときには「事件の背景」と「現場の様子」の二つの着目点をそれぞれ分けて書くと、読み手にわかりやすい説明になります。
この使い方は中学生にも実践しやすく、「何を見て、何を伝えるのか」を自分の言葉で整理する習慣につながります。強調したい点は、着目は常に特定の事柄を選ぶ段階から始まる点です。
着眼点の意味と使い方
着眼点は、物事をどう見るかの“軸”を指す語です。たとえば社会のニュースを学ぶとき、同じ出来事でも「政治の政策」という着眼点で見るか、「人の生活への影響」という着眼点で見るかで、結論の見え方が変わります。着眼点を変える訓練としては、与えられたテーマに対して複数の視点を列挙し、それぞれの利点と限界を比べる練習が有効です。授業ノートや日記にも、どの着眼点を採用したのかを明記すると、後から見直すときに役立ちます。
著者は、着眼点の切り替えを意識することで、文章全体の論理の流れをスムーズに保つことができると考えています。
違いのポイントと使い分けのコツ
着目と着眼点の違いをひとことで言えば、着目は「何を気にするのか」という対象の選択、着眼点は「どう見るか」という視点・軸のことです。実際の文章づくりや討論では、この二つを組み合わせると説得力が高まります。コツは次の三つです。第一に、まず着目点を決めてから、そこへ向けて説明の筋道を作ること。第二に、着眼点を複数準備して、比較することで深い分析を提示すること。第三に、読者が混乱しないよう、用語の定義と例文をセットで提示することです。これらを意識するだけで、作文・作文発表・ニュース解説など、さまざまな場面で伝わり方が変化します。
最後に、適切な場面選択と語順の工夫が、情報の伝わり方を大きく左右するという点を忘れずに。
ねえ、今日は雑談風に「着目」と「着眼点」を深掘りしてみよう。私たちは毎日何かを選んで見ています。映画を観るとき、同じシーンでもどこを着目するかで感想が変わるし、レビューを書くときは着眼点を変えるだけで伝わり方が変わります。着目は“ここを見よう”というポイントの選択で、着眼点はそれをどう評価するかの視点のこと。例えば友達にニュースを説明するとき、着目は「事件の背景」、着眼点は「社会への影響」という二つの切り口を用意しておくと話が一段と面白くなります。私もこの二つを使い分ける練習を日々していて、作文やプレゼンが格段に楽になったと感じます。日記や課題にも、まずどこを着目するのか、次にどの視点を着眼点として採用するのかを書き出してみるといいですよ。
前の記事: « バイアスとパイピングの違いを徹底解説 中学生にも分かる実用ガイド
次の記事: 融合と複合の違いを徹底解説 中学生にも分かるポイント »





















