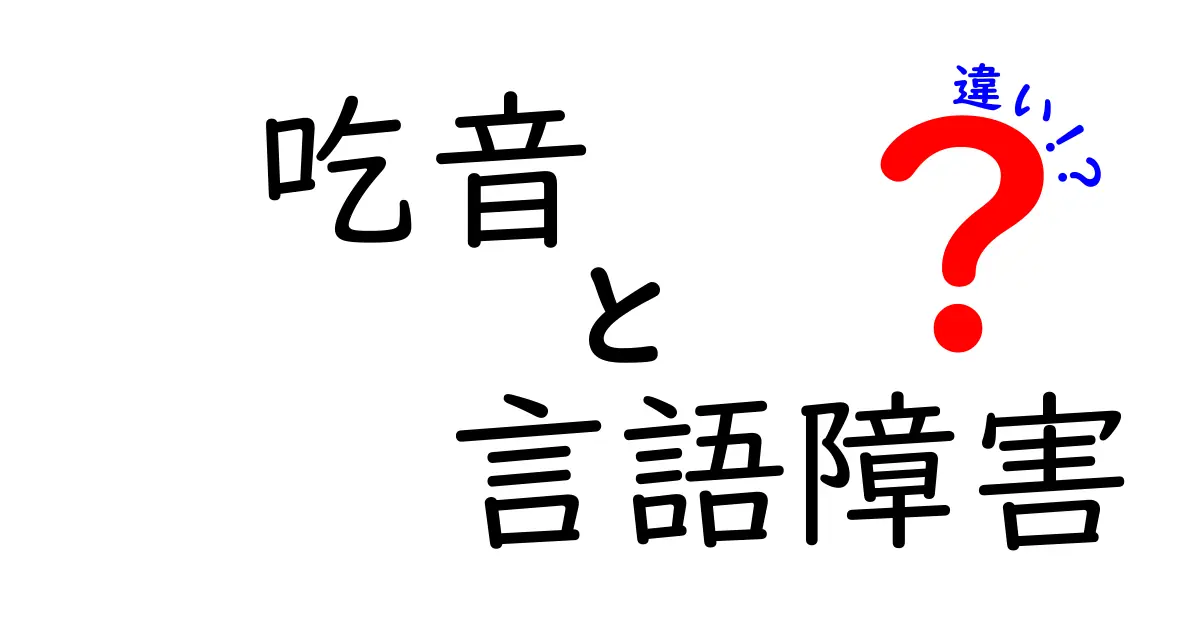

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
吃音と言語障害の違いを正しく理解するための基本
吃音と言語障害は似て見えることがありますが、実は別の概念です。吃音は発話の流れに関する“つまり”や“くり返し”が主な特徴で、話すときに言葉がスムーズに出てこない状態を指します。成長過程で起きやすく、環境やストレスに左右されやすい側面もありますが、病気としての診断名ではありません。
一方、言語障害は言語の理解・運用・表現そのものに関する発達的・神経的な問題を指します。語彙が少ない、文を正しく組み立てられない、発音が難しい、意味の取り違いが多いなど、原因や表れ方はさまざまです。
この二つを混同すると、子どもが「恥ずかしい」「私には話す力がない」と感じやすくなります。だから正しい理解と適切な支援が大切です。
本記事では、それぞれの特徴を整理し、見分け方と支援のポイントを中学生にも伝わる言葉で解説します。
なお、吃音は遺伝的な要因、神経の結びつき、発達の個人差などが関係することが多く、単純に治すべき対象として扱うべきではありません。周囲の人の理解と、必要であれば専門家の力を借りることが重要です。
吃音の特徴と日常の影響
吃音の主な特徴は次の三つです。反復、音の引き延ばし、そしてブロック(詰まり)です。例えば「おはようございます」を「おおはようございます」や「おはよう…ございま」みたいに言い出すといった現れ方があります。これらは自然な会話の一部として出てくることが多く、場面や気分によって表れ方が変わるのが特徴です。
また、吃音は「話すことが難しい」という自己評価にも影響します。誰かに伝えたいことがあるのに、すぐに伝えられないと自分を責めてしまい、話す機会を避けるようになることがあります。これが学校生活や友人関係にも影響を与え、緊張や不安が増える悪循環に陥ることもあります。
しかし、吃音は適切な練習と環境の工夫で改善する可能性が高く、療育や支援を受ければ自信を取り戻すことができます。専門家は「話し方のリズムを少し変える練習」「深呼吸を使った発声法」「焦らずに話す時間を作る訓練」などを提案します。
学校での支援としては、教師の理解とクラスの配慮、話す順番を待つ時間の確保、発話の機会を増やす工夫などが有効です。親や友人の協力も大切で、話題の準備を一緒にしてあげたり、相手の話をよく聴く姿勢を示すことが安心感につながります。
言語障害の特徴と日常の影響
言語障害は幅広い意味を持ち、発達の段階で起こることが多いです。語彙不足、文法のつくりにくさ、理解の遅れ、発音の難しさなどが典型例です。学校では作文や読み書き、算数の文章題を理解する力にも影響が出ることがあり、字を読む速度が遅かったり、話すときの表現がうまくつながらなかったりします。原因は多岐にわたり、聴覚の問題、発達の遅れ、脳の処理の仕方の違い、環境要因などが複雑に絡みます。
言語障害がある子どもには、個別の支援計画を立てることが重要です。言語聴覚士や教育相談員と協力して、語彙力を増やす練習、文を構成する練習、文章理解を高める読解訓練を進めます。家庭での声かけは「急かさず、ゆっくり話す」「長い文を短い文に区切る」「子どもの話すペースを尊重する」など、焦らせず安心して話せる環境づくりが効果的です。
また、言語障害は必ずしも知的能力と直結しません。個々の強みを見つけ、得意な分野を伸ばす支援が大切です。学級づくりとしては、読み聞かせの時間を増やす、視覚教材を活用する、質問の回収を待つ時間を十分に設けるなど、多様な学習スタイルを認める取り組みが有効です。
今日は友だちと学校の休み時間に口こみ話をしていたときのことを思い出してみたんだ。吃音と聞くと難しそうに感じる人もいるけれど、実際には話し方のリズムの工夫や待つ時間の大切さで、ぐんと話しやすくなる場面があるんだよ。私の友だちにも吃音の人がいて、最初はみんな戸惑うかもしれない。でも大事なのは、話す人のペースを尊重して、焦らせないこと。私たちができる一番の支援は、相手の言葉を最後まで聴くことと、待つ時間を作ることだと思う。
前の記事: « 翻訳家と通訳者の違いを徹底解説!現場で差がつく3つのポイント





















