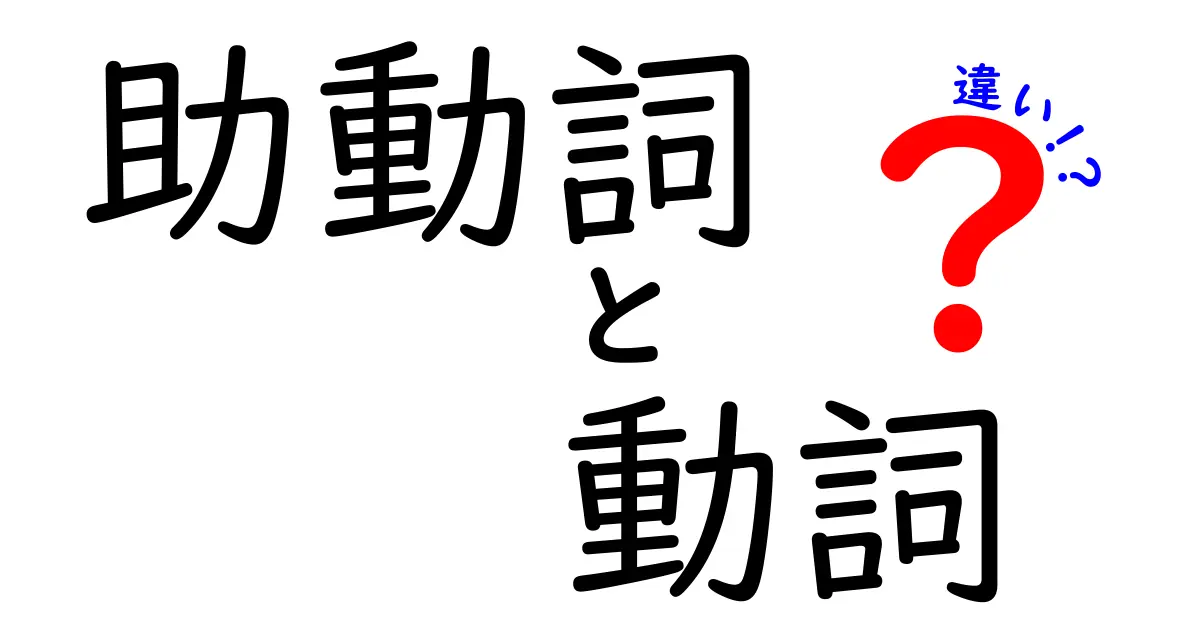

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
日本語の学習でつまずきやすいのが「助動詞」と「動詞」の違いです。
動詞は自分で動作を表す語で、行くや見る、食べるなどが基本形です。
一方、助動詞は動詞や形容詞に接続して文の意味をくわえる役割を持つ語です。
例として「行く」+「ことができる」=「行くことができる」(可能を表す)や「行く」+「ます」=「行きます」(丁寧さ)などがあります。
この違いを理解するには、まず「何を伝えたいか」を考えることが大切です。
本記事では、助動詞と動詞の違いを、わかりやすい例と実践的な使い分けのコツを交えながら紹介します。
読み進めるうちに、文の意味がどう変わるのか、どの場面で何を使えばよいのかが見えてくるはずです。
さっそく基本の考え方から確認していきます。
助動詞と動詞の基本的な違い
動詞と助動詞の基本的な違いは、機能と役割です。
動詞は「動作・状態」を自分で表す語で、文の中で主語と動作を結ぶ中核となります。
例えば「友達が宿題をする」は「する」が動詞で、主語が誰か、何をするかを示しています。
対して助動詞は、動詞に接続して文の意味を変えたり、時間・可能性・意志・命令・推量・丁寧さなどのニュアンスを付け足します。
例を挙げると「行く」+「ことができる」=「行くことができる」(可能を表す)、「食べる」+「ます」=「食べます」(丁寧さ)、「読む」+「た」=「読んだ」(過去を表す)のように、助動詞は動詞を修飾する柱の役割を果たします。
ここで重要なのは、助動詞自体が独立して動作を完結させるのではなく、必ず別の語と組み合わせて使われることです。
つまり、助動詞は動詞の「意味を補強したり、時制や態度をつけたりする補助的な役割」を持つと考えるとわかりやすいです。
この感覚をつかむと、文を読んだときに「この部分はどういう意味か」「どの助動詞が使われているか」が自然と分かるようになります。
次の段落では、具体的な例を使ってさらに深く比較します。
使い分けのコツと実践例
実際の文章を読んだり作ったりするときに、助動詞と動詞の違いを意識するコツがあります。
まずは動詞の基本形を確認します。
次に「この語が何を伝えようとしているのか」を問います。
もし「可能性・推量・丁寧さ・過去・意志・条件」などの意味を加えたい場合、助動詞を使います。
例を見てみましょう。
「行く」→「行ける」(可能)、「行く」→「行きます」(丁寧)、「見る」→「見た」(過去)、「読む」→「読ませる」(使役)など、動詞と助動詞の組み合わせでニュアンスが大きく変わります。
文章を自然にするコツとして、短い語を連結しすぎず、適切な間を作ること、そして丁寧さや尊敬語・謙譲語の使い分けを学ぶことが挙げられます。
さらに、語の活用表と実際の会話文を比較すると、覚えやすくなります。
総じて、「動詞は自分の動作を示す中心」、「助動詞は意味を補い、文の雰囲気を決める補助役」という見方がしっくりきます。
日常の文章練習では、まず短い作文から始め、次第に複雑な文で助動詞を増やしていくと良いでしょう。
最後に、よく使う助動詞の一覧表を作って暗記する方法も効果的です。
助動詞って実は会話の裏方さん。動詞が動作を担う主役なら、助動詞はその雰囲気を整える脇役。友達に丁寧に伝えたいときは『〜ます』をつけるだけで印象が変わる。『〜たい』『〜られる』『〜ことができる』といった形が、いかにして話のニュアンスを決めるのかを、日常の例で思い出してみよう。授業では、同じ動詞でも助動詞をつけると敬語にもなる。本文の中で出てくる例文を自分の会話に置き換えて練習すると、自然と使い分けの感覚が身につく。
次の記事: 副詞と連体詞の違いを徹底解説|中学生にも分かる使い分けのコツ »





















