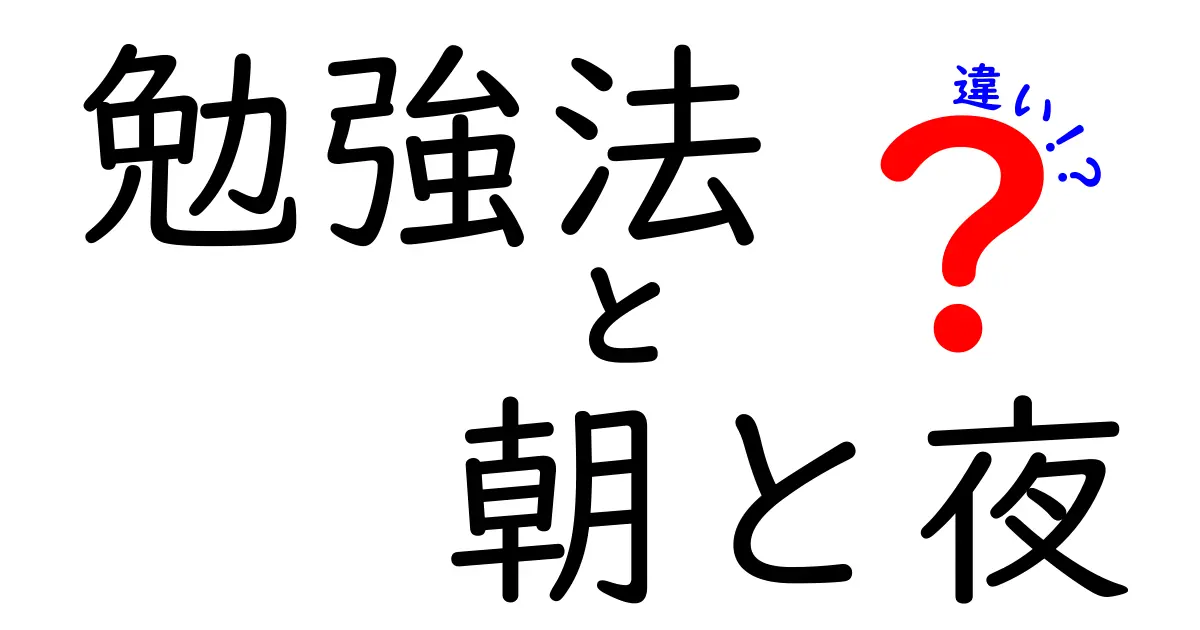

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
朝と夜の勉強法の違いを完全解説!時間帯で変わる集中力と記憶のコツ
朝と夜では体のリズムや脳の働きが変わります。このリズムの違いを理解することで、同じ科目でも効率が大きく変わることがあります。まず抑えておきたいのは「夜は疲労が蓄積されている分、短時間で高い集中が必要になる場面が多い」一方で「朝は睡眠の記憶の整理が進みやすく、新しい情報を覚えやすい土壌が整っている」という点です。これらは個人差がありますが、科学的にも証明されつつある傾向です。
本記事では、朝と夜のそれぞれの特徴を分かりやすく整理し、中学生でも実践できる具体的な勉強法を紹介します。
眠る前に詰め込み過ぎない、朝は不可欠な「基礎づくり」を中心に置く、などの基本を押さえつつ、学習計画の立て方と、集中力を高める仕組みを作るコツを解説します。
まず大切なことは「時間帯を意識した学習計画を作る」ことです。朝は新しい情報の頭の中の整理が進みやすいので、初期段階では難しい公式や新しい概念を一気に覚えるよりも、基礎の理解を深めることを優先します。ここでのポイントは無理をしないことと、適切な休憩を挟むことです。長時間ダラダラと勉強するより、集中の質を高める短時間の blocksを繰り返す方が記憶の定着に向きます。さらに眠りの前に暗記コツを詰め込みすぎると、睡眠中の記憶整理が妨げられる可能性があるので注意します。
朝の勉強は、新しい情報を受け取る窓口を広げる作業です。夜はその日学んだ内容を整理して定着させる作業を中心に組むと、効率が上がります。
朝の勉強のメリットとコツ
朝は頭がまだ眠気から完全には抜けていない状態ですが、だからこそ頭の回転が鋭いと感じる人も多いです。脳は朝の新鮮な刺激に反応しやすく、新しい概念を覚えたり、難しい問題に挑戦したりするのに適しています。コツとしては、起きてから最初の90分を「新しいことを学ぶ時間」として設定することです。眠気が残る時間帯に難しい問題を避け、代わりに基本問題の演習や解法の手順の確認から始めます。朝の環境づくりも大事で、机の整理、適度な照明、コップ一杯の水分補給を習慣化すると集中しやすくなります。
具体的には、短いブロックで進める方法がおすすめです。例えば25分勉強して5分休むサイクルを2~4回繰り返すと、脳の疲れを最小限に保ちながら学習量を確保できます。注意点としては、朝は早く起きるのが苦手な人もいるため、無理をして体調を崩さないよう自分のリズムに合わせることです。
夜の勉強のメリットとコツ
夜は日中の生活の疲れが出る時間帯ですが、その反面、雑音が少なく周囲の干渉が減ることが多いです。静かな環境で深い理解を追求するのに向いています。また、日中に学んだ内容を思い出す練習をするのに適しており、間隔をあけての復習は記憶定着を高めます。コツは「詰め込みすぎず質を優先する」ことです。長時間の勉強は疲労を蓄積させ、思考の速度を落とすため、20分程度の集中を3~4回に分けるのが効果的です。就寝前には難しい新規情報よりも、日中の学習の復習とアウトプット中心にするのが良いです。
自分の睡眠スケジュールを崩さず、睡眠前のスクリーンタイムを控えることも大切です。夜に向く科目としては、文章力が問われる科目や総復習、計算の手順を整える作業などがあります。
朝と夜を組み合わせた学習のおすすめプラン
理想的には朝は新しい情報の理解と基礎づくり、夜はその日の復習とアウトプットを組み合わせることです。以下は一例の1日プランです。
朝 30分 基礎の練習と新しい概念の整理
15分 休憩
25分 新しい内容の理解と演習
10分 休憩
15分 ノートの整理と要点の写経的復習
夜 20分 その日の要点の復習と暗記事項の見直し
10分 休憩
25分 問題演習と解法の確認
15分 1日の総括ノート作成
週末には表形式の総復習表を作成し、どの科目が強くどの分野が弱いかを把握して次週の学習計画に反映します。
集中力は勉強の要。朝は頭が軽く新しいことを覚えやすいと感じる人が多いけれど、夜は疲れが出て集中が続かないこともある。私の友だちと話しても、朝は新しい教科の実践問題を中心に進め、夜は日中に覚えた公式の復習とアウトプットを大切にするという意見が多い。短い休憩を挟みつつ20分程度の集中を3回程度回すと効果的だという共通点があった。結局は自分の体内時計に素直になり、朝と夜の性質を使い分けることが最善の近道だと思う。
前の記事: « 受験日と試験日、違いはどこ?中学生にもわかる徹底解説





















