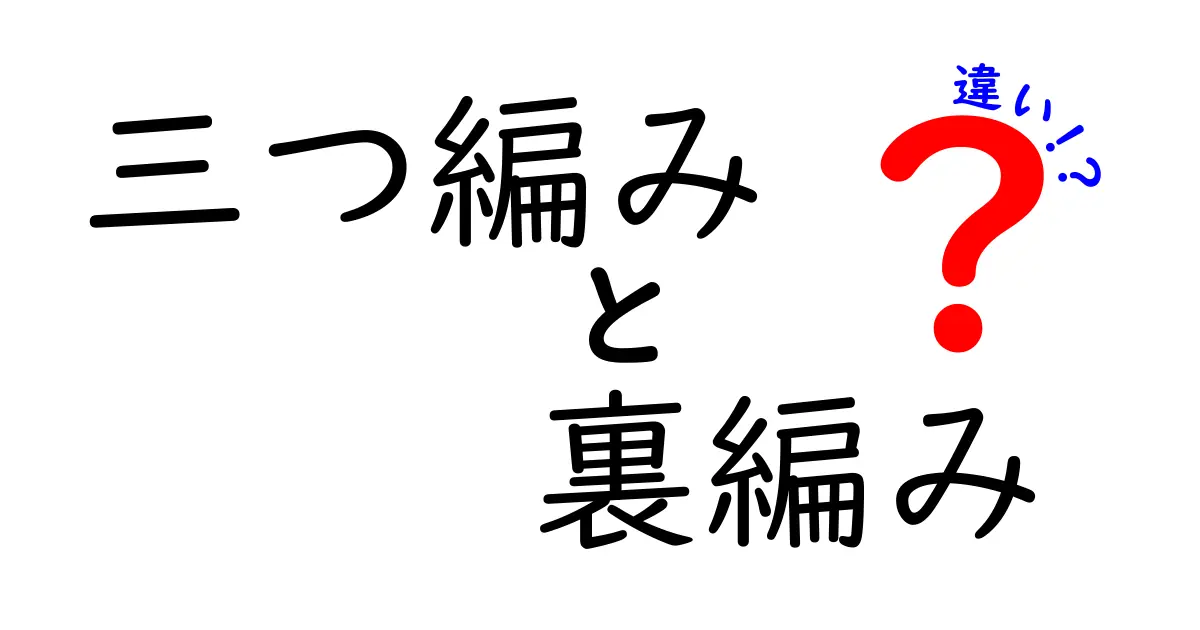

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
三つ編みと裏編みの違いを徹底解説
このキーワードを見て「三つ編み」と「裏編み」の違いが気になる人は多いでしょう。三つ編みは髪の毛や紐などを三つの束に分けて交互に重ねる、立体感と安定感を作り出す編み方の総称です。裏編みは編み物の世界で使われる用語で、糸の表面ではなく裏側の目を拾って編む技法のことを指します。この二つは目的・道具・仕上がりの印象が大きく異なるため、混同すると仕上がりに差が出てしまいます。以下では、それぞれの特徴を中学生にも分かりやすい言葉で丁寧に解説します。
まず “何を作るのか” という目的をはっきりさせることが大切です。三つ編みは髪飾りやアクセサリーの土台、またはお団子ヘアのベースとして使われることが多く、見た目の華やかさと作業の手軽さが魅力です。一方で裏編みは編み物の世界の基本技のひとつとして、模様づくりやリブ編みの土台として活躍します。
このような背景を押さえておくと、学校の文化祭や部活の発表、手芸クラブでの作品づくりなど、場面ごとに適した技を選ぶことができるようになります。以下のセクションでは、それぞれの特徴を具体的に整理します。
三つ編みとは何か
三つ編みは、糸や髪の毛を三つの束に分け、左・中央・右の順で交互に組み合わせて結ぶ基本的な技法です。均等に束を整えることが美しい仕上がりのコツで、束が細すぎたり太すぎたりすると見た目が不揃いになってしまいます。髪で作る場合は、初めは緩めに編み、徐々に締まっていく程度に力を入れると毛流れが自然になります。裏側を意識して編むと、髪の戻りやすさも調整できます。
また、三つ編みは技術の難易度が低く、練習を重ねることで素早く安定した結び目を作ることが可能です。イベント前の準備時間が限られているときにも役立ち、手軽に「動きのある髪型」を演出できます。最近では三つ編みを応用した複雑な編み込みアレンジも増えており、コツさえ掴めば多様な表情を出すことができます。
裏編みとは何か
裏編みは、編み物の基本技として用いられる“地の目の裏側から編む”アプローチのことを指します。糸の表情を変えることで、作品全体に柔らかさや滑らかさを生み出すのが特徴です。裏編みを使うと、表編みの凸凹を抑えつつ、編み地の安定感を高められる場面が多いです。例えばセーターの袖口や裾、靴下などのリブ編みは裏編みを活かして作られることが多く、伸縮性が高い点が大きな利点です。
裏編みの練習を積むと、糸の太さや針の選択で表情が大きく変わることを実感できます。長い距離を編むときには、糸のテンションを一定に保つコツを覚えると安定した編み地が得られます。初心者が初めて裏編みを試すときは、目の数をしっかり揃え、針の動きを均一に保つことを意識するとよいでしょう。
違いを日常の場面で活用するポイント
日常の場面でこの二つを活用する際には、目的と仕上がりのイメージを先に決めることが大切です。三つ編みは髪型のアレンジやアクセサリー作りの土台として最適で、短い時間で華やかさを演出できます。イベントや学校の行事で、即席で形になる点が魅力です。裏編みは、編み物で原稿のように“綺麗な表情”を出すのに向いており、模様の基礎を作る力があります。模様を変えたい場合にも、裏編みの技術を応用することで表情のバリエーションを広げられます。
さらに、材料選びも重要なポイントです。髪の場合は滑りにくいスタイリング剤を少量使うと編みやすくなり、編み物では糸の太さ・質感に合う針を選ぶと編み地の密度が均一になります。最後に、道具を揃える前に自分の作りたい作品をイメージし、必要な技法をリスト化しておくと、練習の効率が格段に上がります。
裏編みって、聞くと難しそうに感じるけど、要は“糸の向きを変えるだけで地味に表情が変わる”技術の話だよ。私が初めて裏編みを意識して編んだとき、表側と裏側の印象がこんなにも違うのかと驚いたんだ。友達と編み物の話をしていたとき、彼は『裏編みは裏側が味噌みたいにしっかりしてるから、ブランケットみたいな大きなアイテムの土台に最適』と言っていて、僕もその言葉に納得した。裏編みを練習すると、目の揃え方が安定してきて、作品全体の仕上がりが格段に良くなる。結局、技術は「使い道を想像する力」と「地道な練習」の組み合わせなんだなと実感したよ。
次の記事: アンゴラとモヘアの違いを徹底解説!見分け方と使い方のポイント »





















