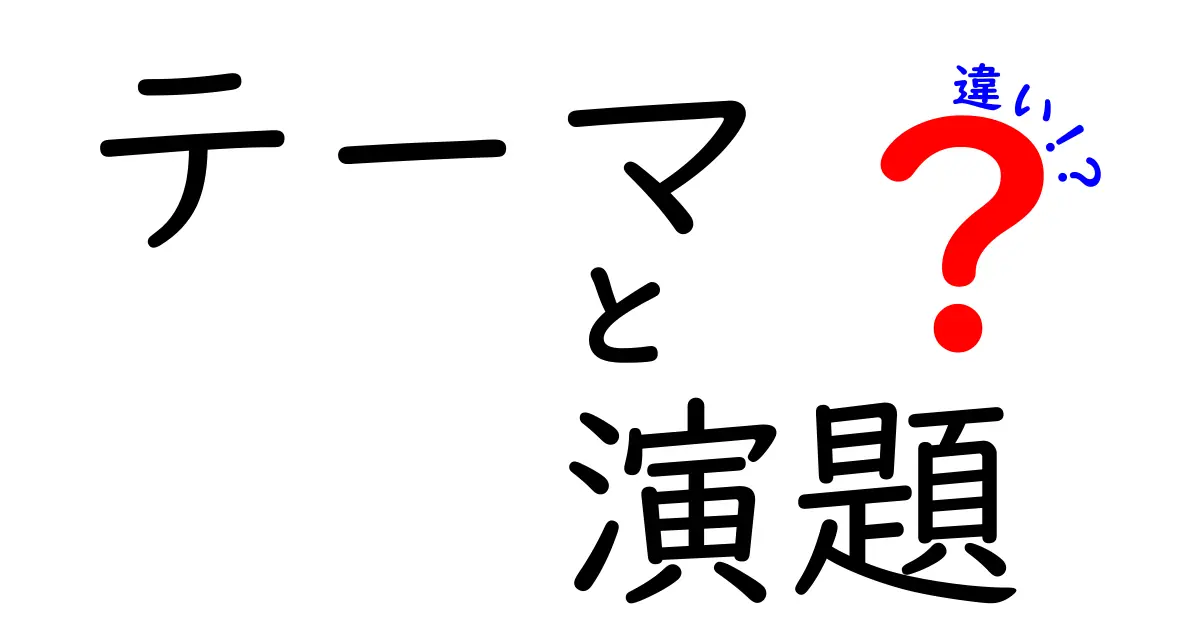

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
テーマと演題の違いを理解する基本のポイント
ここでは、教育現場や発表の場でよく混同される「テーマ」と「演題」の意味の違いを整理します。まずテーマは、話の核となる“考え方の中心”であり、長い展開の方向性を決める土台です。対して演題は、聴衆が受け取る最初の入り口となる“表現の名前”であり、具体的な発表タイトルとして読ませる力を持ちます。つまり、テーマは内容の中身を支える柱であり、演題は聴衆にとっての導入部、入口の言葉です。日常の会話でも「今回の話のテーマは何ですか?」と問われる一方で、「演題は何という名前で呼ばれていますか?」と聞かれることがあります。ここで違いをはっきりさせておくと、資料作成やプレゼン構成がスムーズになります。
例えば、ある科学の授業でのテーマは「協力と共感の科学」のように抽象的な範囲を示します。一方の演題は「協力と共感の科学:実験と観察の視点」のように、具体性と興味を引く要素を同時に兼ね備えた形になります。テーマは広く深くを狙い、演題は人の目を引く工夫をします。ここがポイントです。
続けて、聴衆の受け取り方の違いにも注目しましょう。テーマは受け手に対して「これから何を学ぶのか」を示す指針となり、長い文章や複数のセクションを組み立てるときの羅針盤になります。
一方で演題は、講義の入口として「何を話すのか」を短く端的に伝え、聴衆の注意を引くための言葉遊びや具体性、意外性を含むことが多いです。演題はタイトルとしての記憶に残る力があり、イベントや発表のパンフレット、スライドの表紙にも強く影響します。
実践的な使い分けと表現のコツ
次に、実務の場での使い分け方のコツを整理します。まずテーマを決める前提として、発表の目的をはっきりさせます。目的は「情報を伝える」「考えを喚起する」「行動を促す」など様々ですが、テーマはその目的に沿って選びます。演題は、そのテーマを受けて聴衆がすぐにイメージできるよう、具体性と魅力を兼ね備えた言葉を選ぶと良いです。表現のコツとしては、短く力強いキーワードを演題に取り入れ、聴衆の興味を引く「問いかけ型」や「驚き型」を組むと効果的です。例えば、教育の講演では「未来をつくる学びの現場」のような抽象表現に、「実験で見る協力の力」といった具体性を加えるとよいでしょう。さらに、聴衆の属性を意識して、学生向け、ビジネス向け、一般向けなど、対象に合わせた演題の語彙を選ぶと伝わりやすくなります。
このように、テーマと演題はそれぞれの役割が異なるため、適切に使い分けることが大切です。特に公的な資料や学術的な発表では、最初にテーマを決め、その後演題を磨くプロセスを取ると、整理がしやすく、聴衆への伝わり方も安定します。
演題という言葉を初めて聞いたとき、私は最初“イベントの名前”くらいにしか思っていませんでした。でも、よく考えると演題は私たちの話の入口としてとても重要な役割を持っています。テーマが舞台の地図のように広い道筋を示すのに対し、演題は聴衆に『ここで何を話すのか』を具体的に伝える看板です。授業の発表練習を通じて、演題をうまく付けるコツは短く、覚えやすく、そして興味をそそる言葉を選ぶことだと気づきました。つまり演題は、最初の一歩を踏み出す扉の鍵のようなものなのです。
前の記事: « 演題と講演の違いを徹底解説:意味の違いと使い分けのコツ





















