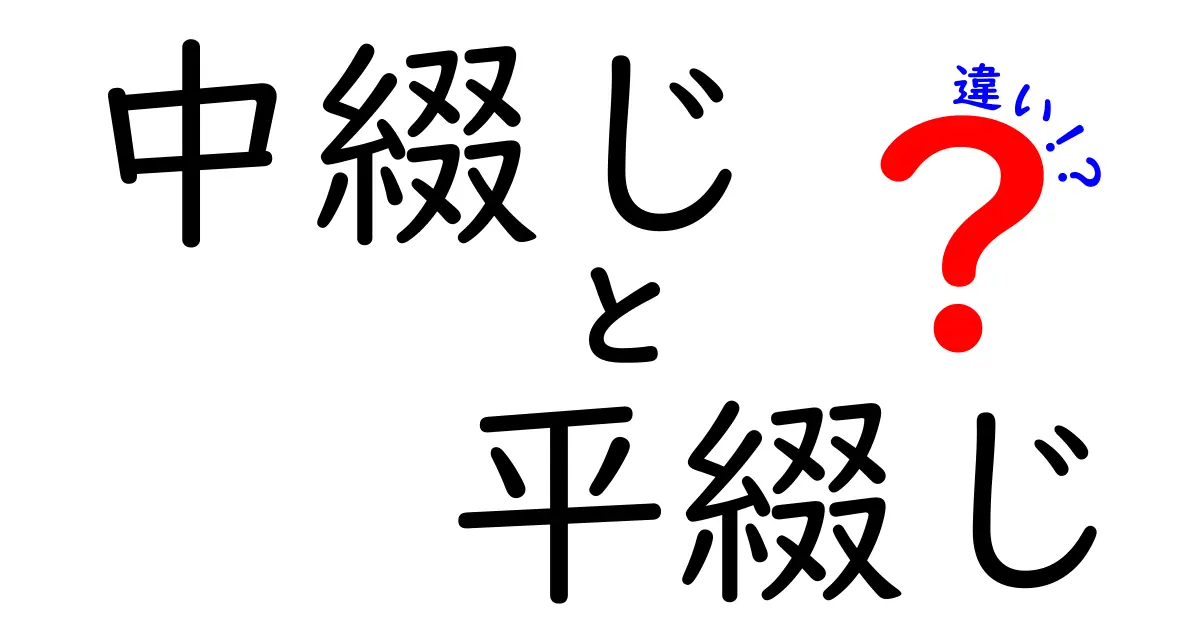

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
中綴じと平綴じの基本を知ろう
中綴じとは、冊子の背を中心にして紙を折り畳み、中央部分をステープルで止める製本方法です。折丁を束ねて背の中心に留めるのが特徴で、冊子の厚みが薄いときに最適です。学校の配布資料やイベントのパンフレットなど、ページ数が多くても40ページ前後程度の小さめの本に良く使われます。紙の性質によっては折り目が薄い紙だと破れやすくなる点には注意が必要です。
一方、平綴じは背を糊で固めて表紙と中身を一本の綴じとして仕上げる製本方式です。耐久性が高く、ページ数が増えても安定して開きやすいのが特徴で、技術的には大判の冊子や雑誌、長いマニュアルなどに向いています。背の部分が綺麗に揃い、見栄えが良いのもポイントです。内側の余白の取り方や、開いたときの見開きの美しさが印象を決めます。
両者を比べると、コスト・納期・仕上がりの印象が異なります。中綴じは作業が早く安価なケースが多く、印刷と加工がシンプルです。平綴じは材料費が高くなる場合がありますが、長期間の使用に耐える丈夫さと読みやすさが魅力です。ページ数が少ない資料には中綴じ、ページ数が多い資料には平綴じが適していることが多いと言えるでしょう。
中綴じと平綴じの使い分けと実務的ポイント
冊子を作るときは、まず「何ページか」「使用目的は何か」「開きやすさは必要か」を考えます。ページ数が40ページ前後なら中綴じが手頃で、折り丁の組み合わせや折り目の場所を正確に合わせることが重要です。反対に、200ページ近いマニュアルや本格的な雑誌では平綴じが向いています。背の糊付けは時間と経験が必要で、印刷所の機械にもよります。
- 発送・配布の際の軽さを重視する場合は中綴じ
- 耐久性と読みやすさを重視する場合は平綴じ
- デザインの表紙に影響を与える点は、どちらを選ぶかの判断材料
- 納期や予算に余裕があれば、平綴じの方が品質が高いと感じることが多い
最後に、印刷データの組版にも注目しましょう。本文の行間・余白・窓開きの仕上げなど、綴じ方によってページの見え方が変わります。制作前に印刷所へ相談し、サンプルを取り寄せて比較するのが最善です。
放課後の教室で友だちと印刷所をのぞいたときの会話を想像して書きました。中綴じは薄い冊子を速く安く作るときに向いていて、平綴じは厚みのある冊子でも背が曲がりにくく長く丈夫です。私たちはどの場面でどちらを選ぶべきか、コストと使い勝手のバランスをどう取るかを、実務的なポイントと現場の雰囲気を添えて説明します。





















