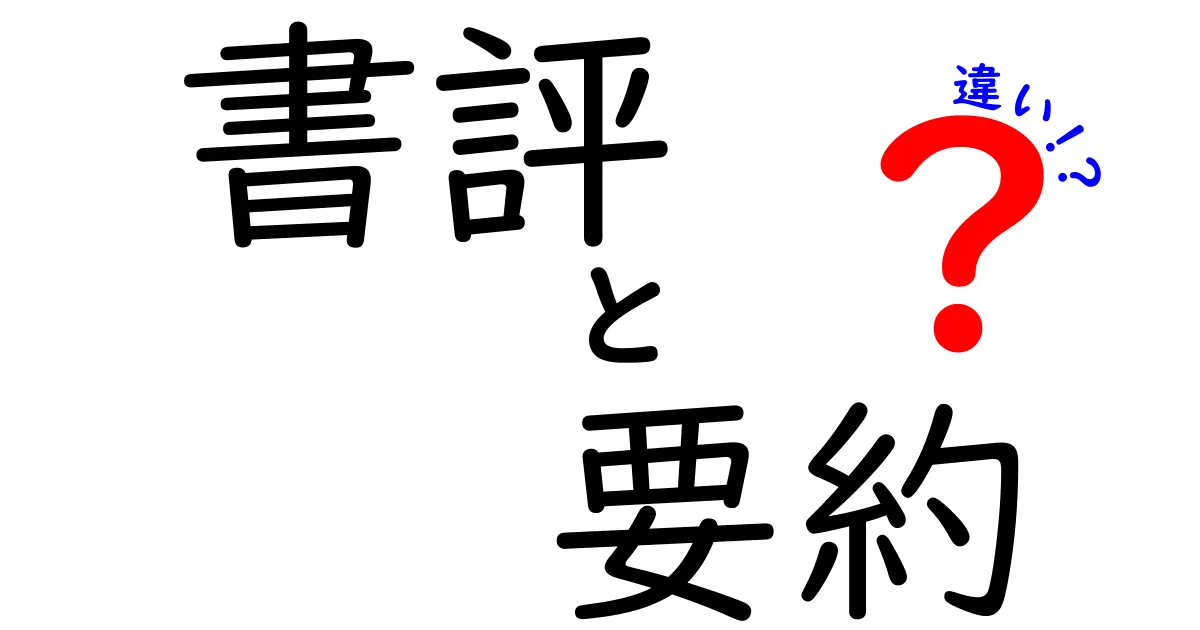

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
「書評」「要約」「違い」の基本を押さえる
現代の読み物には「書評」「要約」「違い」という3つの要素がよく登場します。
「書評」は本の内容をどう評価するか、どう感じたかを伝える文章であり、
「要約」は本の核心を短く分かりやすくまとめたもの、
そして「違い」はこの2つの機能の差を説明する考え方です。
この3つを混同すると読書の意図が伝わりづらくなります。
本記事では、中学生でも分かる言葉で、書評と要約の定義、具体的な違い、そして実践的な使い方を丁寧に解説します。
初めてこの3つを学ぶ人にも、すでに知っている人にも、それぞれの良さと限界を理解してほしいと思います。
読書ノートをつくる際や、授業の課題で本を紹介するとき、どういう順序で伝えるべきかを考えるときにも役立つはずです。
「書評」と「要約」の違いを一目で見抜くコツ
本当にわかる違いは、「目的」と「情報量」、そして読み手の期待値の3つで決まります。
書評は著者の意図・構成・文体・根拠の吟味を含み、
評価の視点が入り込みます。
一方、要約は情報の正確さを保ちながら、核心のみを抜き出す作業です。
難しい専門用語が出てくる場合も、要約は難解な語を避け、
中学生にも伝わる言葉で置き換えることが基本です。
この違いを意識するだけで、読む場面に応じて適切な文章を書けます。
また、長さの目安を決めるときには、読者が知りたい点と結論を最短で伝えることを重視します。
例えば新しい本を紹介する場合、書評は評価軸のハイライトと数点の根拠を、
要約は本文の核となる1〜3つのポイントに絞って伝えると良いでしょう。
ケーススタディと表で見る違い
以下は実際の読み物を例に、書評と要約の違いを具体的に理解するためのセクションです。
読み手となるあなたが、どの場面でどちらを使うべきかを迷わず判断できるよう、長さの目安と要点の切り出し方を整理します。
このセクションを読むと、情報をどう整えると読み手に伝わりやすいかが分かるようになります。
- 観点: 目的・情報量・読み手の働きかけの3軸で比較
- 書評: 著者の意図・文体・根拠を評価・伝える
- 要約: 核心ポイントを正確に短く伝える
- 違いの要点: 目的の違いが言葉遣いと構成を決める
この理解は、学校の課題でのレポート作成にも役立ちます。あなたが書評と要約を使い分けられるよう、今後も練習を重ねてください。
最後に、読み手の目線を意識することが最も大事です。
結論を先に伝えるのか、根拠を詳しく並べるのか、目的に応じて選択してください。
要約は、元の意味を壊さず、核心だけを抽出する技術です。友人の長い話を短く伝える練習を思い出してみてください。要約では、まず本質の点を拾い、次に伝わりやすい言葉に置き換え、最後に元の順序感を保つ工夫が大切です。練習のコツは、声に出して説明する練習を繰り返すこと。これによって、授業のレポートや日常の読書ノートでも、読み手に伝わる力がぐんと高まります。
次の記事: 上映と轟音の違いを徹底解説!映画体験を倍増させる音の秘密 »





















