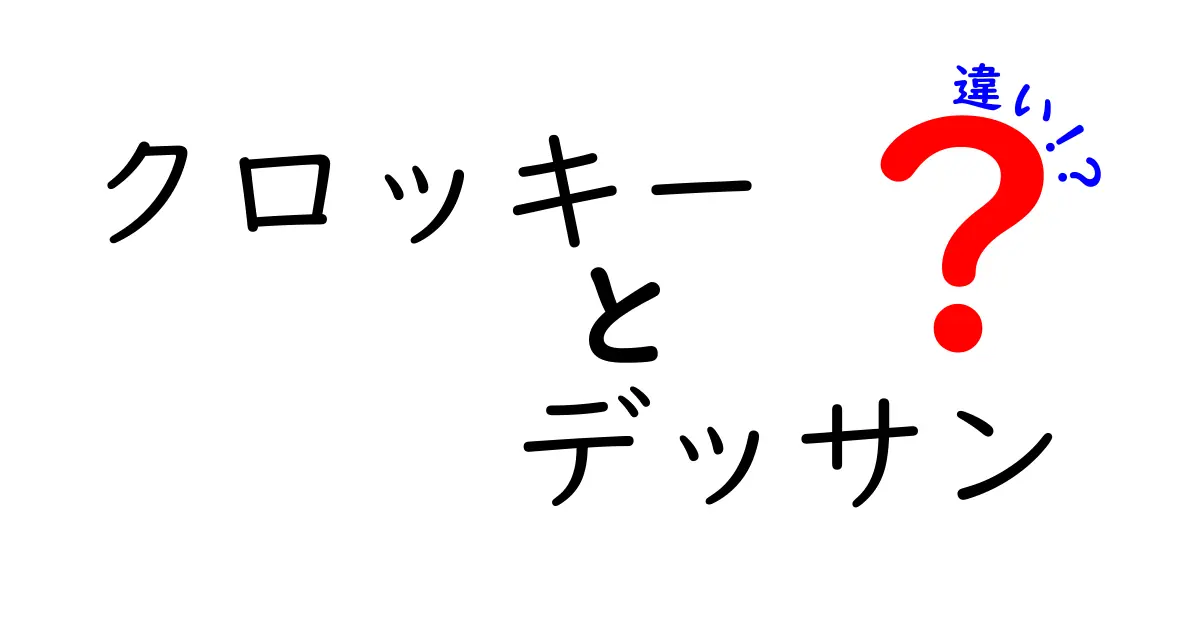

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:クロッキーとデッサンの基本の差
クロッキーとデッサンは、絵を描くときの「決定的に違う2つの考え方」です。速さと観察の質、対象の捉え方、完成の基準が大きく異なり、練習の目的もアプローチも変わってきます。本記事では、初めて触れる中学生にも分かるよう、2つの特徴を丁寧に解説します。さらに、実際の練習でどう使い分けるか、道具や練習の流れも具体的に紹介します。絵を上達させるには、どちらも重要な要素なので、両方の良さを知っておくとよいでしょう。
最初は「速く描くことが正解なのか」「細かい描写が必要なのか」といった疑問を持つ人もいます。しかし、クロッキーとデッサンは互いを補い合う練習です。速さの練習が観察の精度を高め、長い観察が線の意味を深めます。この2つを組み合わせると、対象をただ写すだけでなく、絵としての「伝える力」が強くなります。この記事を読んだあと、実際の練習で両方を取り入れると、描く力がぐんと安定します。
また、クロッキーとデッサンには「題材の選び方」も影響します。クロッキーは人物・動き・風景など、瞬間的な変化を捉える練習に向いています。デッサンは静物・静止した被写体・人物のポーズを長く見つめ、形と陰影を正確に表現するのに適しています。こうした違いを理解してから、日々の練習計画を組むと効率的に上達します。
中学生が勉強感覚で取り組むときのコツは、難しく考えすぎず「まずは描いてみる」ことです。回数を重ねるごとに、手の動きと目の観察が自然に結びつくようになります。さらに、練習日誌をつけると、自分がどの点で成長したかを確認でき、モチベーションの維持にも役立ちます。
クロッキーとは何か?
クロッキーは短時間で主な形だけを素早く捉える練習です。時間を決めて描くことで、手の動きと目の観察を同期させる訓練になります。一点を詳しく描くのではなく、動き・姿勢・大きさの比率をすばやく掴むことが目的です。中学生にも取り組みやすいよう、最初は1分程度の短時間から始め、5分、10分と徐々に時間を延ばしていくと良いでしょう。路上の人物、風景、物の形など、自由な題材で練習でき、手のスピード感や線の連続性を鍛えられます。
クロッキーは形のつながりを体感する力を高めます。大量の練習を通じて、線の質と動きの印象をそろえる練習でもあります。速さを求めるほど、観察の「要点」を見抜く力が試され、描写の無駄を省く習慣が身につきます。初学者は、最初の数回は失敗を多数経験しますが、それを恐れず、描くたびに改善点を見つけるクセをつけましょう。
また、クロッキーは「失敗の許容度を高める練習」とも言えます。失敗しても消して別の線を引く回数を増やすことで、思い切りよく表現する力が育ちます。短い時間で多数のスケッチを描くため、材料費も抑えられ、学校の授業や部活の合間にも取り組みやすい点が魅力です。
デッサンとは何か?
デッサンは対象を観察して、形・明暗・質感を丁寧に表現する練習です。時間をかけて観察し、陰影のつき方、光の向き、素材の質感といった要素を正確に描き分けることを目指します。中学生が取り組みやすい段階としては、鉛筆の濃さを変える練習や、陰影の描き分けを意識することから始めると良いでしょう。デッサンは技術的な要素が多く、正確さを求めるほど難易度が上がりますが、観察の深さと描く道具の扱いを少しずつマスターしていくと、絵の完成度がぐんと上がります。
デッサンを楽しむコツは「観察の視点を変える」ことです。例えば、物を正面から見るだけでなく、斜めから、上から、あるいは反射光を意識して観察してみると、同じ対象でも見え方が大きく変わります。こうした視点の変化は、後のクロッキーにも生きてきます。さらに、紙の上での陰影のつけ方を意識することで、立体感が自然に出てきます。最初は線の太さを意識しすぎず、形の関係性を整えることを優先しましょう。
デッサンは、観察と再現の両方を鍛える「総合的な練習」です。細部の描写を追いかけすぎず、まずは大きな形と陰影のバランスから整えると、完成度が安定します。継続して練習することで、描く対象ごとの特徴を素早く読み取り、正確さと表現力の両立が可能になります。
違いのポイントを5点で比較
- 所要時間とテンポ:クロッキーは数分程度の短時間連描きが基本で、テンポ良く描く訓練です。デッサンは長時間をかけて観察と表現を積み上げます。時間の使い方が全く異なり、思考のスピードも変わります。
- 焦点と表現:クロッキーは「形の要点を掴むこと」に焦点を当て、線の太さや陰影よりも全体のシルエットや動きを重視します。デッサンは「質感・明暗・立体感」を丁寧に描き出すことが目的です。
- 対象の扱い方:クロッキーでは対象を素早く捉えるため、細部を省略し、大まかなポーズや配置を先に決めます。デッサンでは観察を深め、細部にわたる観察結果を再現します。
- 道具の使い方:クロッキーは速い線を連続させやすい鉛筆やペンを使い、保持の練習にも向きます。デッサンは筆圧やトーンを変えやすい鉛筆、コンテ、紙の質感を活かす道具を選ぶとよいです。
- 学習効果の違い:クロッキーは観察力と瞬間の判断力を高め、デッサンは観察の深さと技術の蓄積が進みます。両方を組み合わせると、絵全体の安定感と表現力が増します。
クロッキーとデッサンを練習する時のコツ
道具と準備
練習を始める前に、道具を整えることが大切です。ノートと鉛筆、消しゴム、定規など、手元に必要なものをそろえましょう。クロッキー用には薄い鉛筆やシャープペン、速写の時は細いボールペンや3B程度の鉛筆が使いやすいです。小さなノートではなく、B4程度の紙を使うと、手首の動きを大きく使えるため、線の力強さが出やすくなります。また、良い状態で描くためには机の高さを自分に合わせ、姿勢を正しく保つことも重要です。
準備が整ったら、道具を使い分ける練習を少しずつ取り入れ、どの道具がどんな表現に向いているかを体で覚えましょう。ここでのコツは「完璧を求めず、手の感覚をつかむこと」です。
さらに、日常の中で「観察ノート」をつくると効果的です。見たものを短い文章とともにメモしておくと、次の描画時に観察したポイントを思い出しやすくなります。
実践の流れの例
以下は、初めての人向けの、1回の練習の流れの例です。はじめに時間を決め、焦らず観察することが大事です。1分で全体の形を捉え、2分で大きな陰影の位置を決めます。3分で細部の明暗を整え、最後の1~2分で全体のバランスを確認します。もちろん個人差があるので、最初は5分程度のクロッキーから始め、慣れてきたら時間を少しずつ延ばしていくと良いでしょう。以下の表は、練習の流れを視覚化したものです。
練習を重ねるうちに、観察力と手の動きの連携が自然に身についていきます。自分の描く意図を言語化する練習も、絵を上達させる大切な要素です。日々の小さな積み重ねが、絵の完成度を大きく左右します。
クロッキーという言葉を初めて聞くと、速さに焦りが出るかもしれません。しかし、実はクロッキーは“速く描く練習”以上の意味を持っています。最初は手の動きと目の観察を“つなぐ”ための訓練で、少しの時間で形の要点を掴むコツを学べます。私が中学生の頃、友だちと公園へ行って1分クロッキーを回し描きしたことがあります。最初は見えていたはずの形がうまく線に表れず、悔しくて何度も描き直しましたが、そのたびに「この角度ならこの線が効く」という感覚を体が覚えていくのを実感しました。
今振り返ると、あの短い時間で“何を描くべきか”を見定める力が身につき、それがデッサンの細部描写にも響きました。結局のところ、クロッキーは“描く質を上げるための準備運動”のようなものです。あなたがもし、思うように絵がうまくならないと感じているなら、焦らず、まずは1分・3分・5分と短い時間設定で、失敗を恐れずに回数を重ねてみてください。習慣になるころには、描く速度と観察の質が自然と両立するはずです。





















