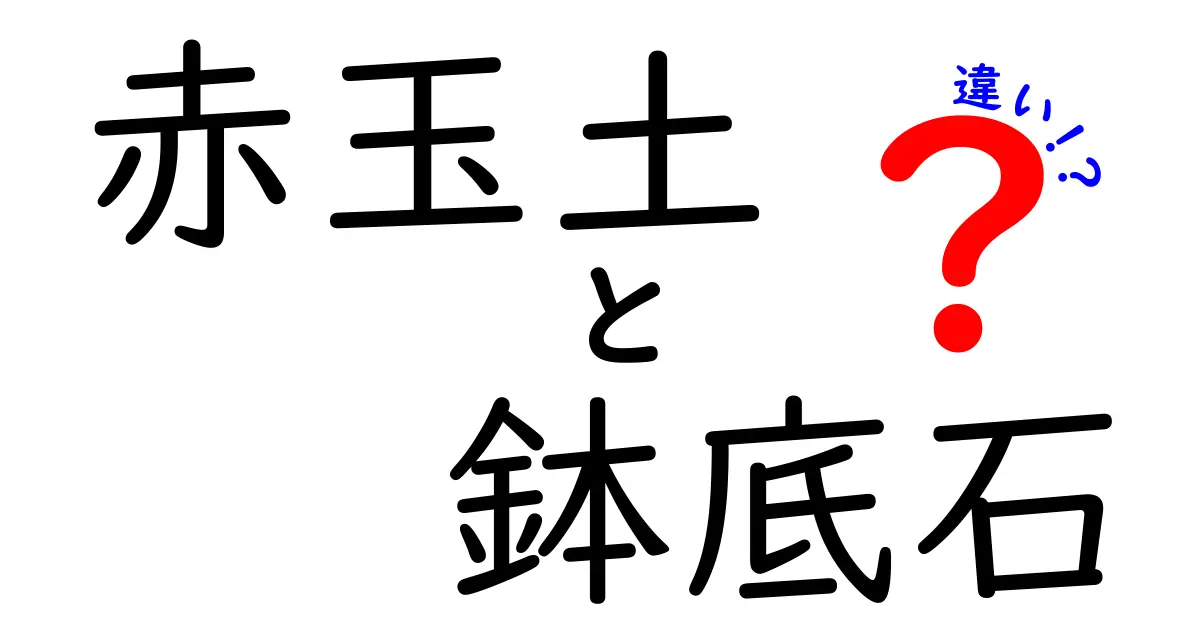

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
赤玉土とは何か?その特徴と役割について
<赤玉土は園芸用の土の一種で、小さな粘土の粒が固まったものです。主に日本の園芸で使われており、赤茶色の色が特徴です。
この土の大きな特徴は、水はけがよく、空気の通りも良いため、植物の根が健やかに育ちやすいことです。赤玉土は土壌の通気性と排水性を高め、根腐れを防ぐ役割があります。
また、赤玉土は植物に必要な水分を保持しながらも、過湿になりにくいため、観葉植物や盆栽、多肉植物などに幅広く使われています。加えて、中和性があり、多くの植物に適したpH環境を保ちやすいのもポイントです。
<
鉢底石とは何か?その役割とは?
<鉢底石は、鉢の底に敷くための石や小石のことを指します。これは赤玉土とは全く違い、鉢の底に水が溜まらないようにして排水性を確保する目的で使われます。
鉢底石を敷くことで、土からの過剰な水分が流れやすくなり、根が水浸しになってしまうことを防止します。特に、水はけが悪い土壌や水やりをする頻度が高い場合に重要な役割を果たします。
鉢底石には軽石や小石、砕いた瓦などが使われますが、軽石は特に軽くて水はけが良いため人気があります。
<
赤玉土と鉢底石の違いを表で比較!使い方のポイントも解説
<水はけと通気性を良くする
pHが中性に近い
軽石など、多孔質な石が多い
他の土と混ぜて使うことも多い
適度な水分保持
<
まとめ:赤玉土と鉢底石は役割が違うけれどどちらも大切
<赤玉土は植物が実際に根を張る土で、水分や空気のバランスを保つために欠かせません。一方で鉢底石は過剰な水が溜まるのを防ぐ排水の役目を果たします。
この2つを正しく理解し、うまく活用することで植物をより健康に育てることができます。
植物を育てる時は、まず鉢底石を敷いてから赤玉土を入れるという手順を忘れずに。これが基本となり、根腐れ知らずの元気な植物に育てるポイントです。
赤玉土は水はけが良く、植物が根を伸ばしやすい土ですが、実は粒の大きさや粒の表面の質で水の保持力がかなり変わります。
例えば赤玉土の粒が細かすぎると、土の隙間が少なくなってしまい、通気性が悪くなりやすいんです。逆に大きすぎると水を保持しにくい特徴も。
だから園芸ショップでは、赤玉土の粒のサイズを「小粒」「中粒」「大粒」に分けて売っていて、育てる植物に合わせて選ぶことが大事。この選択が植物の育成成功のカギになるんですよね。つい赤玉土をまとめて買ってしまいがちですが、ちゃんと粒サイズもチェックしましょう!
次の記事: 植え替えと鉢増しの違いとは?初心者にもわかる植物の育て方の基本 »





















