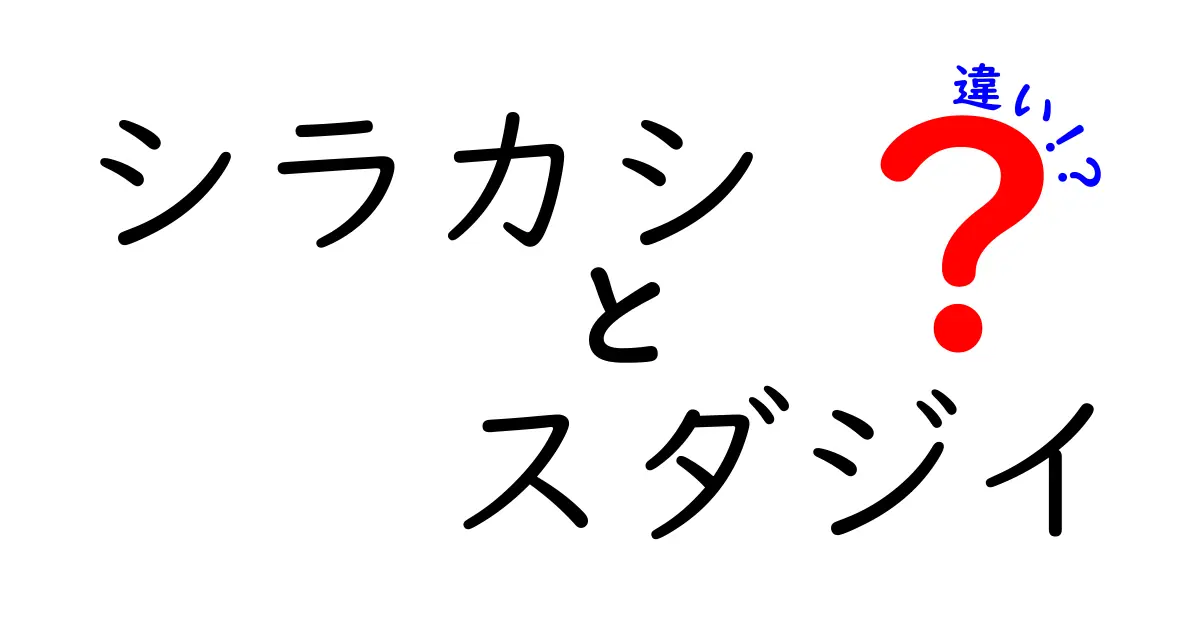

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
シラカシとスダジイとは何か?
みなさんは「シラカシ」と「スダジイ」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも日本に自生する樹木の名前ですが、見た目や特徴が似ているため、違いがわかりにくいこともあります。シラカシはブナ科の落葉樹で、スダジイはブナ科の常緑樹として知られています。自然や植物に興味がある人には特に注目されることが多い木ですが、初心者には混乱のもとです。この記事では、シラカシとスダジイの違いやそれぞれの特徴、見分け方をわかりやすく説明していきます。
両者の特徴を理解することで、街路樹や公園などで見かけたときに違いをすぐに見分けられるようになりますよ。
シラカシの特徴と見分け方
シラカシ(学名:Quercus myrsinifolia)はブナ科のうちのカシ類で、日本全国の山地や丘陵地に自生しています。
葉は厚くて光沢があり、少しギザギザのある楕円形で、表面は濃い緑色です。秋になると落葉して冬は葉を落とします。若い枝は細く、樹皮は薄くて滑らかです。
また、シラカシのドングリはやや細長くてツヤがあります。実は食用としても昔は使われていました。
シラカシの見分け方のポイントは以下の通りです。
- 落葉樹であること
- 葉は厚く光沢があり、楕円形でギザギザの縁がある
- 樹皮は薄くて滑らか
- ドングリは細長く、ツヤがある
シラカシは冬に葉が落ちるので、見た目でスダジイと区別しやすい特徴です。
スダジイの特徴と見分け方
スダジイ(学名:Castanopsis sieboldii)もブナ科の樹木ですが、こちらは常緑樹として知られています。日本の暖かい地域の海岸近くや温暖な山地に自生しています。
葉は硬くて厚みがあり、縁には細かいぎざぎざがあり、表面は濃い緑色で光沢があります。落葉しないため、冬でも葉が落ちることはありません。
樹皮はややざらざらしていて、灰褐色です。ドングリは丸みを帯びていて、イガに包まれています。
スダジイの見分け方は以下の通りです。
- 常緑樹で冬でも葉がある
- 葉は厚く光沢があり、細かい鋸歯がある
- 樹皮はざらざらしていて灰褐色
- ドングリは丸みがあってイガに包まれている
常緑樹である点が最大の特徴で、これがシラカシとの大きな違いといえます。
シラカシとスダジイの違いを表にまとめてみよう
| 特徴 | シラカシ | スダジイ |
|---|---|---|
| 分類 | ブナ科 カシ属 | ブナ科 スダジイ属(カスタノプシス属) |
| 葉の状態 | 落葉樹(冬に葉が落ちる) | 常緑樹(冬も葉がある) |
| 葉の形と縁 | 厚く楕円形、縁に少しギザギザ | 厚く細かい鋸歯がある |
| 樹皮の状態 | 薄く滑らか | ざらざらして灰褐色 |
| ドングリの特徴 | 細長くツヤがある | 丸みがありイガに包まれている |
| 生育環境 | 山地や丘陵地 | 暖かい海岸近くや温暖な山地 |
このように見比べると、落葉か常緑か、葉の形やドングリの形など明確な違いがあることがわかります。街路樹や公園で見かけたら、冬に葉があるかどうかをチェックするだけでシラカシかスダジイか判断できます。
まとめ:シラカシとスダジイの見分け方を覚えておこう
シラカシとスダジイは見た目が似ていますが、分類や葉の状態、樹皮、ドングリなどでしっかり区別ができます。
特に冬の葉の有無が一番簡単な見分けポイントです。シラカシは落葉樹なので冬は葉がなくなり、スダジイは常緑樹なので葉が残ります。
これを覚えておくと、自然観察や植物学の勉強にも役に立ちますし、日常生活の中でも植物に関心を持つ楽しみが増えます。
ぜひ公園や山歩きの際に注意して観察してみてくださいね。
スダジイの葉っぱってじつは冬でも青々としているんですよね。常緑樹だから冬でも枯れないで、冬の寂しい景色に彩りを加えてくれます。しかも葉っぱの表面はツヤツヤで触るとちょっと硬め。だから冬に落ちないだけでなく、寒さや風にも強いってわけ。こう考えると、スダジイは自然の工夫がいっぱい詰まった木なんだなって感心しちゃいますね。
前の記事: « ヤマボウシとヤマモモの違いとは?見た目や特徴を比較してみた!
次の記事: ミズキとヤマボウシの違いは?特徴や見分け方をわかりやすく解説! »





















