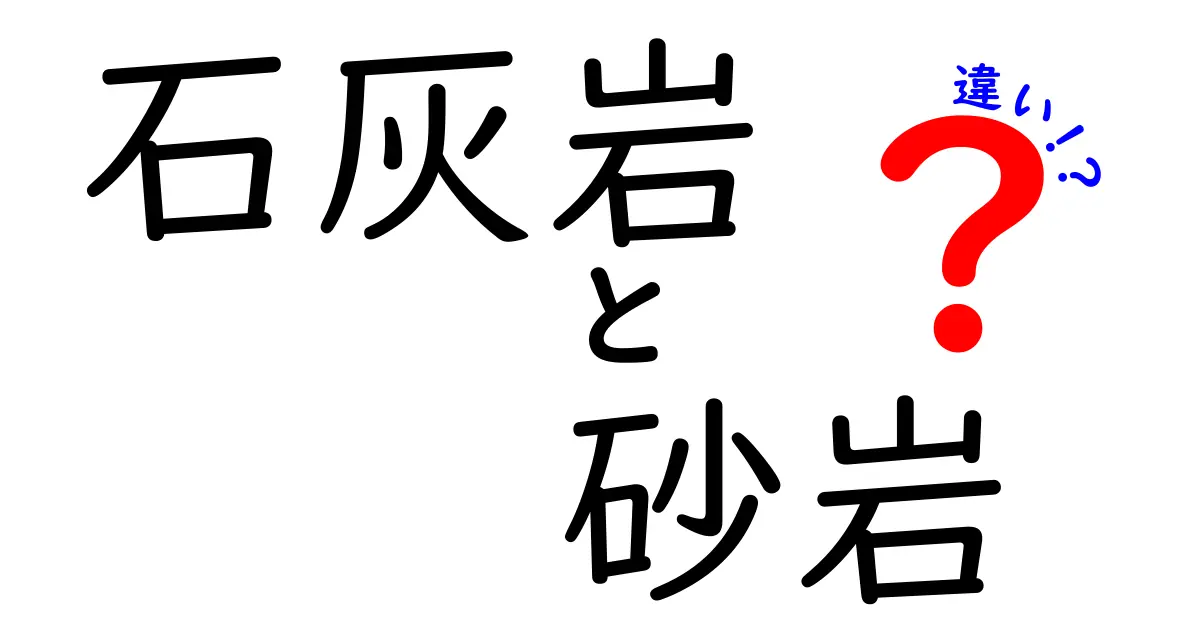

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
石灰岩と砂岩って何?基本を知ろう
石灰岩と砂岩は、どちらも地球の地面に存在する岩石ですが、その成り立ちや見た目、性質には大きな違いがあります。中学生のみなさんも学校で習うことがありますよね。
石灰岩は主にカルシウム成分でできている岩石で、昔の海の中で貝やサンゴなどの生き物の殻や骨がたまってできました。
砂岩は、砂の粒が固まってできた岩石で、川や海などで流された砂が集まって圧縮されてできたものです。
これが二つの岩石の大まかな違いの始まりです。
石灰岩と砂岩の成り立ちと特徴の違いを詳しく解説
石灰岩と砂岩の材料やでき方には根本的な違いがあります。
石灰岩は主に「炭酸カルシウム(CaCO3)」を成分とし、海の生物が作った殻や骨、プランクトンの死骸などが長い時間をかけて圧縮されてできました。
石灰岩は白っぽい色をしていて、水に触れると弱い酸(例えば雨水の中の二酸化炭素)が溶かします。_これは石灰岩が酸に弱い性質があるからです。_この性質を使って、石灰岩の存在を確かめることもできます。
一方、砂岩は岩の風化でできた砂粒が自然に集まって固まった岩です。
砂粒は主に石英という鉱物が多いので、砂岩は通常茶色やピンク、赤っぽい色をしています。砂岩は石灰岩よりも硬く、水に強いです。
川や海の近く、砂漠などいろんな場所でできるため、世界中にたくさんあります。
まとめると、石灰岩は生物由来が多く弱酸性に溶けやすい岩、砂岩は砂粒が固まった硬い岩石です。
石灰岩と砂岩の見た目や性質、使われ方の比較表
どんな場所で見つかる?石灰岩と砂岩の分布と利用環境
石灰岩は昔の海や湖の底でできることが多いため、日本でも九州や四国の一部に多く見られます。
また、洞窟の鍾乳石なども石灰岩が溶けてできる自然のイメージです。
砂岩は川や砂漠の近く、海岸など、砂が集まりやすい地域でできます。
砂の種類や色が違うため、地域によって砂岩の見た目も変わります。
建築材料としてもよく使われるため、多くの文化財の壁や柱として砂岩が使われています。
このように、石灰岩と砂岩は地球の環境や場所によってできる場所が違い、利用法も異なります。
石灰岩は雨水に含まれる微量の炭酸が溶け込んで、長い時間をかけてゆっくり溶ける性質があります。実はこの性質が原因で、鍾乳洞(しょうにゅうどう)の美しい鍾乳石ができるんです。雨水が石灰岩の洞窟に滴り落ちると、少しずつ石が溶けては蒸発して、カルシウムが固まって形を作ります。だから、石灰岩は自然の彫刻家みたいですね。こうした自然の働きがあるから、建物の石として使うときは酸に弱いことを覚えておく必要があります。
前の記事: « 地質年代と地質時代の違いとは?初心者でもわかる簡単解説!





















