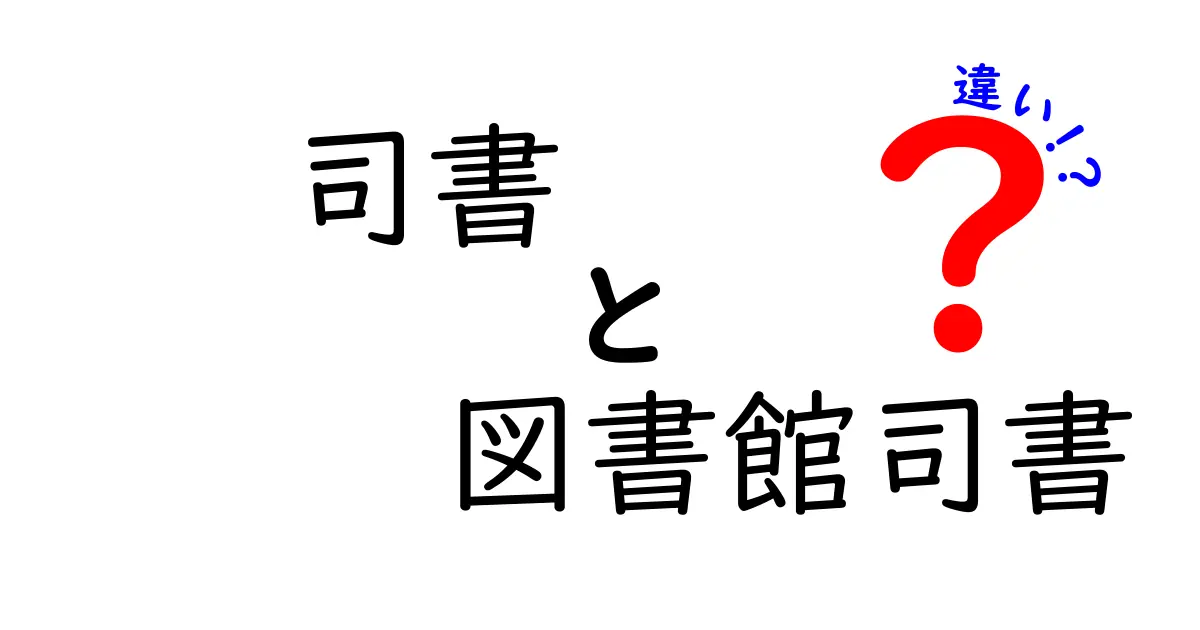

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
司書と図書館司書の違いについての基本知識
みなさんは「司書」と「図書館司書」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも本や資料に関わる仕事ですが、この二つには違いがあります。
まず、司書とは図書館で働くために必要な国家資格のことです。つまり、司書は資格の名前であり、その資格を持つ人が図書館や情報センターなどで働くことができます。
一方で「図書館司書」はこの司書資格を持っていて、実際に図書館で働いている人のことを指します。
このように、簡単に言えば「司書」は資格、「図書館司書」はその資格を持って働く人という関係にあるんです。
この違いは言葉の使い方としてとても重要で、資格の話をするなら「司書」、人物や職業の話をするなら「図書館司書」を使うことが多いです。
また、司書の資格は国家資格で、取得には一定の専門教育が必要です。詳しくは後ほど説明しますね。
司書資格とは?取得方法や役割について
司書資格は日本の文部科学省が認めた国家資格の一つで、図書館に関する専門知識と技能を持つことを証明します。
取得するためには、大学や専門学校などで司書教員指定の授業(図書館情報学など)を受ける必要があります。
また、仕事として司書を目指す人のために短期の養成講習も用意されていて、この講習を受けて修了証を得ることでも取得可能です。
司書の役割は図書館資料の整理や利用者支援、資料の貸し出し管理など多岐にわたります。例えば、本の貸し出しだけでなく、図書館の資料を使いやすく整理し、利用者が探している情報を案内する仕事も司書の大切な役目です。
近年はデジタル資料の取り扱いや、データベースの利用支援なども求められることがあります。
このように司書資格を持つ人は、図書館の専門家として図書館の円滑な運営に貢献しています。
図書館司書の仕事内容と必要なスキル
図書館司書の仕事は名前の通り「図書館で働く司書」です。
主な仕事には以下のようなものがあります。
- 本の貸し出しと返却の管理
- 図書の分類や整理
- 利用者の質問対応や情報提供
- 図書館イベントの企画・運営
- デジタル資料の管理と利用支援
これらの仕事をこなすには、本だけでなく図書館のシステムや情報検索の知識も必要です。
さらに、利用者のニーズに応えるためのコミュニケーション能力や、資料を効率よく分類する細やかな注意力も欠かせません。
例えば、利用者が探したい本のジャンルや著者名をうまくヒアリングし、適切な資料を案内する力も求められます。
こうしたスキルは資格取得の教育だけでなく、実務経験を積むことで磨かれていく部分も大きいです。
総じて図書館司書は単なる「本の管理人」ではなく、情報の専門家であり利用者の学びや楽しみをサポートする重要な役割を担っています。
司書と図書館司書の違いをまとめた表
| 項目 | 司書 | 図書館司書 |
|---|---|---|
| 意味 | 図書館で働くための資格名 | 司書資格を持つ図書館勤務者 |
| 役割 | 図書館業務の専門知識を持つ人 | 図書館で資料管理や利用者支援を行う職員 |
| 取得方法 | 大学や講習で資格取得 | 資格取得後、図書館で勤務 |
| 働く場所 | 図書館以外の場所もある | 主に図書館 |
いかがでしたか?「司書」と「図書館司書」は似ているようで違う言葉であり、それぞれ役割や使われ方が異なります。資格に興味がある人や図書館で働きたい人はぜひこの違いを理解して目指してみてくださいね。
「司書」の言葉一つをとっても深く掘り下げてみると面白いことがあります。例えば司書資格はただの資格名と思われがちですが、日本の図書館サービスを支える重要な制度です。資格を取るためには専門の勉強が必要で、図書館の本や情報をどう管理し利用者に提供するかを体系的に学びます。つい「司書」の名前だけで仕事がほぼ決まると思いがちですが、実際には資格取得後の経験やスキルアップも大切なんです。つまり「司書」と呼ばれる人々は、図書館のバックボーンを支える裏方のプロフェッショナルたちだと言えます。
次の記事: 対面授業と面接授業の違いとは?わかりやすく徹底解説! »





















