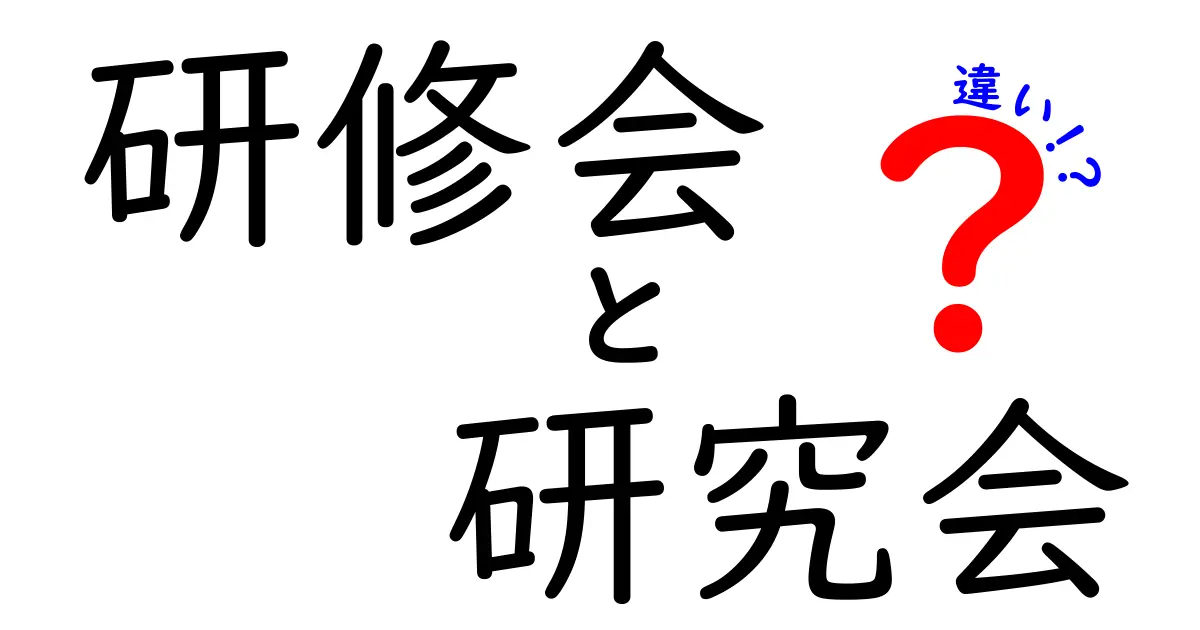

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
研修会と研究会の基本的な違いとは?
研修会と研究会はよく似た言葉ですが、目的や形式が異なります。まず、研修会は参加者が新しい知識や技術を学ぶための集まりです。たとえば、会社の研修や資格取得のための勉強会がこれに当たります。
一方、研究会はあるテーマについて話し合いを行い、知識を深めたり新しい発見を目指したりする場です。研究者や専門家が集まることが多く、議論や情報共有が中心となります。
簡単に言うと、研修会は“学び”、研究会は“議論”がメインです。
この違いは、参加者の役割や期待される成果にも影響します。研修会では講師や指導者から教わることが多いのに対し、研究会では参加者同士の意見交換が重要です。これを理解するだけで、自分に合った集まりを選べるようになります。
研修会の特徴と目的
研修会は教育やスキルアップが目的の会合です。多くの場合、講師がいて参加者に知識や技術を教えます。たとえば、新入社員研修や安全衛生の研修、言語スキルの向上セミナーなど、会社や学校でよく開催されます。
研修会の特徴は、以下の通りです。
- 明確な学習目標が設定されている
- 講義や実習中心で参加者は受講生の立場
- スキルや知識の習得が主な成果
- 比較的時間や場所が限定されていることが多い
こうした特徴により、研修会は効率よく一定の能力を習得したい人に最適な形式です。
また、研修会は資格取得や会社の方針統一などのために使われることが多く、決まった内容を身につけられるところが魅力です。
研究会の特徴と目的
研究会は参加者が主体的に議論したり情報交換したりする集まりです。専門的なテーマに沿って、参加者が自分の意見や知見を持ち寄り、新しい発見や理解を深めることを目指します。
研究会の特徴は以下のようになります。
- テーマは専門的・学術的なことが多い
- 講義よりも討論や発表が中心
- 参加者は対等な立場で意見を交換する
- 定期的に集まることが多く、研究の継続性が大切
研究会では、自分の考えを説明したり、他の人の意見を聞いて学んだりすることが求められます。これにより、メンバー同士の理解が深まり、より良い成果が生まれやすくなります。
大学のゼミや専門職の勉強会も研究会の一例です。
研修会と研究会の違いをわかりやすく表で比較
| ポイント | 研修会 | 研究会 |
|---|---|---|
| 目的 | 知識や技術の習得 | 知識の深化と議論 |
| 構成 | 講義・実習中心 | 発表・討論中心 |
| 参加者の立場 | 受講者(学生役) | 対等な研究者・参加者 |
| 成果 | スキルアップ、資格取得 | 論文作成、問題解決 |
| 期間 | 短期が多い | 継続的な場合が多い |
この表を見ると、それぞれの役割やスタイルがよくわかりますね。
研修会は学びに特化し、研究会は意見交換に特化しているのが最大のポイントです。
自分に合った会の選び方と活用法
研修会と研究会は似ているようで役割が違うので、目的に応じて選ぶことが大切です。
もし、仕事や学校で必要なスキルや資格を短期間で身につけたいなら、研修会を選びましょう。明確に教えてくれる講師がいるので、効率よく学べます。
反対に、自分の考えを深めたい、仲間と意見を交わしながら新しい知見を得たい場合は、研究会の方が向いています。
また、仕事や趣味で両方に参加する人も増えています。研修会で基礎を固め、研究会で応用力を高めるというのはとても効果的です。
自分が何を学びたいか、どんな形で成長したいかを考えながら、両方を上手に使い分けることが将来のスキルアップに役立ちます。
研究会に参加していると気づくのですが、意見を出し合うだけでなく、実は人間関係の深まりも大きな魅力です。メンバー同士で真剣に議論し、時には違う意見にぶつかっても、それを乗り越えることで信頼が生まれます。これは単に知識を深めるだけでなく、自分の考えを整理したり、新しい視点を得たりする貴重な場になります。だから研究会は、まるで頭の中のパズルをみんなで解くような楽しさがあるんですよね。
前の記事: « 教頭と教頭先生の違いとは?役割や呼び方のポイントを徹底解説!





















