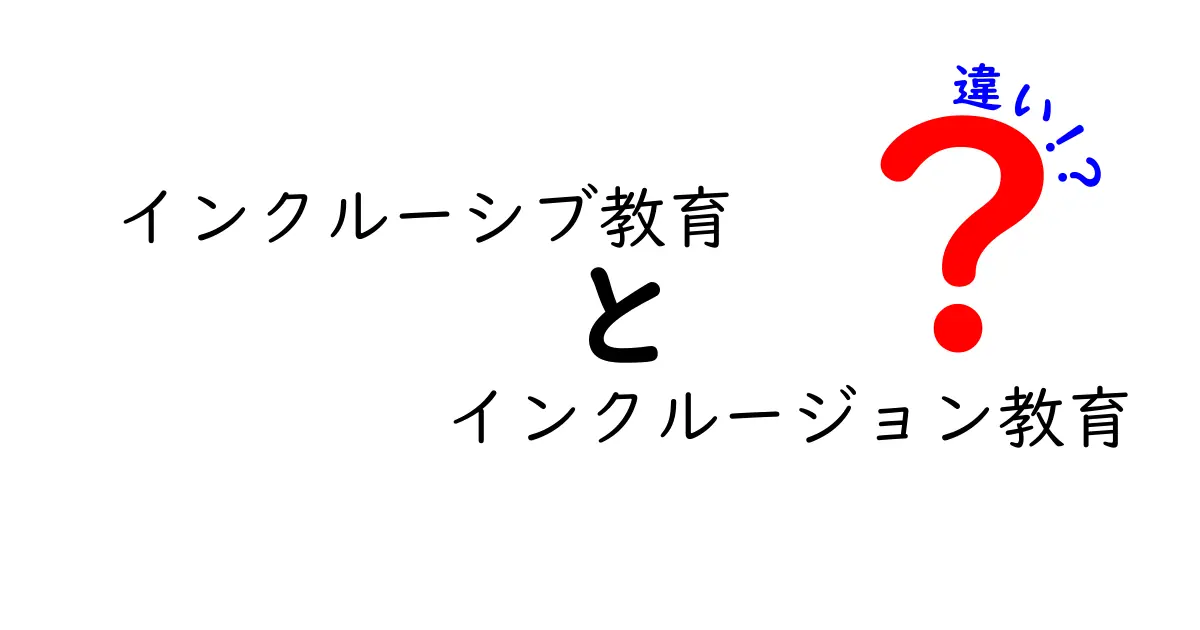

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インクルーシブ教育とインクルージョン教育の基本的な違いとは?
インクルーシブ教育とインクルージョン教育は、どちらも「すべての子どもが一緒に学べる環境を作ること」を目指していますが、言葉の使われ方や強調されるポイントに違いがあります。
まず、「インクルーシブ教育」は日本や国際的にもよく使われる言葉で、障害のある子どももない子どもも、みんなが同じ教室で学ぶことを重視します。お互いの違いを認め合い、多様な子どもたちが共に成長できるような教育のあり方です。
一方、「インクルージョン教育」は、英語の“Inclusion”という言葉から来ており、言葉の意味としては「包み込む」「包含する」というニュアンスが強いです。つまり、単に一緒に学ぶだけではなく、子ども一人ひとりの特性をしっかり受け入れ、その子に合った支援や環境整備を進めることを重視しています。
このように、どちらも似ていますが、インクルージョンは子どもの個別のニーズにより重点を置いた広い概念と言えるでしょう。
インクルーシブ教育とインクルージョン教育の歴史的背景
インクルード(含む)という考え方自体は昔からありますが、国連が推進する障害者権利条約(CRPD)や持続可能な開発目標(SDGs)などを背景に、世界的にインクルーシブ教育の重要性が注目されるようになりました。
日本でも、特別支援教育の充実と通常学級への参加推進が進み、インクルーシブ教育の考え方が広まっています。
インクルージョンという言葉は、欧米で特に個々の多様性や差別をなくす動きの中で強調され、社会的包摂を意識した教育改革に関わっています。
こうした歴史の違いもあり、インクルーシブ教育は教育現場での実践や制度面を示す点が強いのに対し、インクルージョン教育は理念や社会全体の包摂的なあり方を示すことが多いのです。
インクルーシブ教育とインクルージョン教育の具体的な違いを比較した表
両者の違いをわかりやすく整理した表をご覧ください。
| ポイント | インクルーシブ教育 | インクルージョン教育 |
|---|---|---|
| 意味の焦点 | 障害の有無に関わらず同じ場所で学ぶこと | 個々の特性やニーズに合わせた包摂的な支援 |
| 強調点 | 共に学び合う環境の整備 | 社会的な差別や偏見をなくし包み込むこと |
| 使われる場面 | 学校教育の現場・制度 | 教育理念や社会全体の包摂 |
| 歴史的背景 | 特別支援教育の拡大と法制度の充実 | 多様性尊重や権利保障の思想 |
| 具体例 | 通常学級へ障害児を迎え入れる | バリアフリーな学校体制や偏見解消活動 |
このように、インクルーシブ教育は教育の方法や制度を重視し、インクルージョン教育は社会的な理念や個人への配慮に重点を置く違いがあります。
日常の会話やニュースでは、区別せずに使われることも多いですが、理解を深めるとより良い教育のあり方を考えるヒントになるでしょう。
まとめ:違いを知ってこれからの教育を考えよう
今回は「インクルーシブ教育」と「インクルージョン教育」の違いについて説明しました。
どちらも子どもたちがともに学び、生きやすい社会を目指す重要な考え方です。
違いを理解することで、教育制度や社会の動きを正しく捉えられ、周りの人とも意見交換しやすくなりますね。
これからの社会は多様性がますます大切になるので、インクルーシブやインクルージョンの考え方を知っておくことは大きな武器になります。
ぜひ家族や友達とも話してみてくださいね!
インクルーシブ教育という言葉を聞くと、障害のある子どもが普通のクラスに入るイメージが強いですが、実はこれだけではインクルーシブ教育の全てではありません。大事なのは、そこにいるすべての子どもが尊重され、助け合う空間になること。例えば、学び方が違う子がいてもお互いを認め合い、みんなが成長できるように工夫がされています。この『みんなを含める』という考え方が、インクルーシブ教育の根底にあるんです。





















