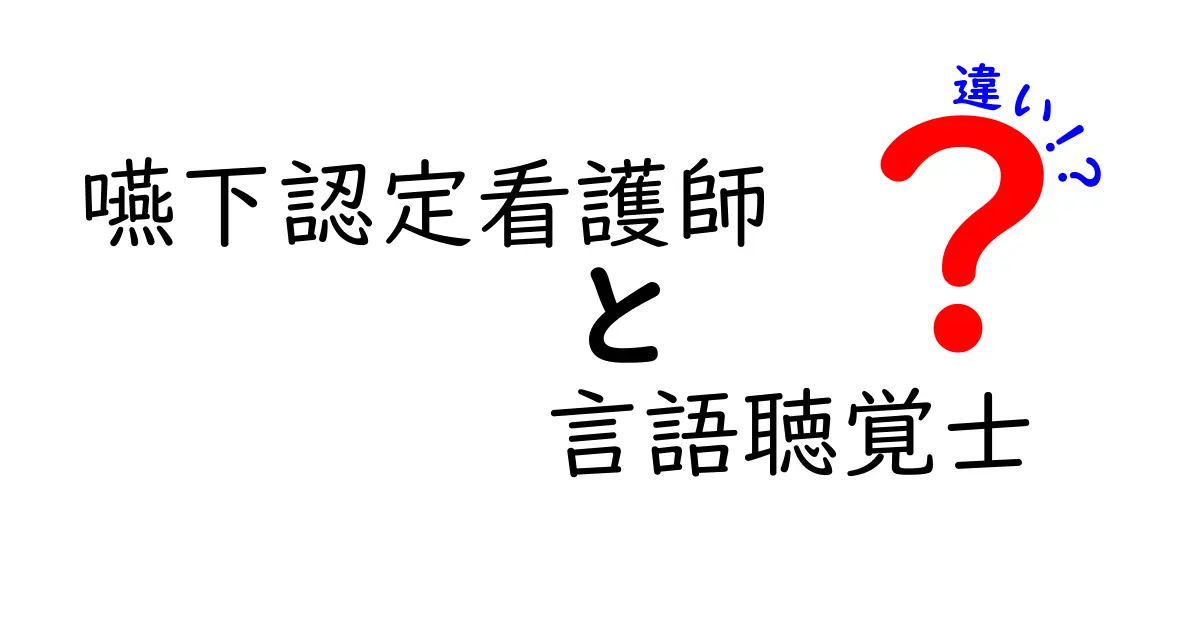

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
嚥下認定看護師と言語聴覚士の違いを理解するためのガイド
嚥下障害を抱える人をサポートする現場には、二つの専門職が協力しています。その中でよく名前が上がるのが「嚥下認定看護師」と「言語聴覚士」です。どちらも高齢者施設や病院で重要な役割を担いますが、できることや専門の視点が違います。この記事では、二つの違いを分かりやすく解説します。
まずは基本を押さえましょう。嚥下認定看護師は看護領域での専門性向上を目的とし、現場の安全管理、ケア計画、家族への説明などを主に担います。言語聴覚士は言語と嚥下の専門家として、食べ方の方法や訓練、検査の解釈を行います。
この二つの視点を理解することは、患者さん一人ひとりに合った「安全で美味しい食事」を提供するための第一歩です。
1. 役割の成り立ちと現場での主な仕事
嚥下認定看護師は病院や施設の看護師としての経歴をベースに、嚥下に関する安全管理を強化する専門家として育成されます。主な仕事は、患者さんの嚥下状態の観察、摂食・嚥下のリスク評価、食事形態の調整、誤嚥を予防するための介助方法の指導、家族への教育などです。現場では、医師や薬剤師、リハビリの専門家と連携し、点滴の順序や薬の影響で嚥下が変わるケースを把握します。
この役割は“組織的な安全の網”を作ることに近く、視点は常に患者の安全第一です。例えば、誤嚥のリスクが高い患者さんには、口腔ケアの強化、姿勢の調整、食事速度の管理、嚥下体操の導入などを提案します。とはいえ、現場によってその責任範囲は異なるため、病院の規程や所属組織の方針に従いながら、医師と連携して働くことが多いです。
一方、言語聴覚士はリハビリの専門家として、嚥下機能の評価と訓練を主に担当します。喉の筋肉を使うトレーニング、嚥下動画などの評価、飲み物や固形物の粘度・形状の適切な選択、訓練計画の立案と実施、評価結果の説明などです。現場では検査機器の扱い、食形態の目安、家族や介護者への指導も行います。嚥下機能改善のための「具体的な訓練プログラム」を作成することが多いのが特徴です。さらに、言語聴覚士は発話・言語の訓練も併せて行うケースがあり、総合的なコミュニケーション支援を提供することも役割の一部です。
2. 資格・教育の違いとキャリアパス
嚥下認定看護師になるには、まず基本の看護師免許が必要です。その後、嚥下ケアに関連する教育プログラムを受講し、認定試験に合格することで資格を得ます。資格を持つ看護師は、病棟や施設での「安全な食事介助」や「誤嚥予防の計画立案」を行い、現場の看護師リーダーとしての役割を担当することが多いです。
教育内容は、安全管理の知識、倫理、家族教育、チーム医療の運営など幅広く、現場のニーズに合わせて学習を深めます。資格の更新・継続教育も必須の場合が多く、最新のガイドラインに対応する努力が求められます。
言語聴覚士は、大学や専門学校で言語聴覚療法を学んだ後、臨床実習を経て国家試験に合格します。国家資格を得た後は、病院、リハビリテーションセンター、福祉施設などで働き、嚥下機能の検査(例:VFSS、FEESなど)や、嚥下訓練の計画・実施を行います。学会や研究会に参加して新しい評価法を学び、最新の科学的知見を実践に取り入れることが多いです。長期的には、専門領域を深掘りする「認定資格」や「学位取得」などのキャリアパスも存在します。
3. 実務での連携と見極めポイント
現場では、嚥下認定看護師とと言語聴覚士がそれぞれの強みを生かして協力します。例えば、看護師は日々のケアの中で患者の嚥下リスクを継続的に評価し、訓練の進捗を記録します。言語聴覚士は評価と訓練を担当し、家族への訓練方法の伝達も行います。連携の要点は「情報の共有」と「役割の明確化」です。誤嚥が疑われる場合には、直ちに医師の判断を仰ぎ、介入計画を更新します。
見極めポイントとしては、患者さんの具体的なニーズに合わせてどちらの専門家が先導役をとるべきかを判断することです。高齢者の長期ケアでは、嚥下だけでなく言語・コミュニケーションの改善も同時に考える必要があります。病棟の中ですぐに使える現場のコツとしては、姿勢の調整、食形態の変更、口腔ケアの徹底、家族への説明資料の提供など、多角的なアプローチを組み合わせること、そして継続的な評価です。
4. 表で見る違い
この表は、嚥下認定看護師と言語聴覚士の違いを分かりやすくまとめたものです。観点ごとに何が得意か、どんな場面で役立つか、体制の特徴、教育の違いなどを比べています。実務では、表に現れるポイントを実際の介護・リハビリ計画に落とし込むことが大切です。以下の表は、日常の現場判断を助ける簡潔なガイドとして活用してください。
今日は小ネタの話題。嚥下認定看護師という資格名を初めて聞く人は少なくないけれど、実は「嚥下」だけを勉強するわけではありません。看護の現場で安全を守るための幅広い判断力と、家族への丁寧な説明力がセットになっている点が魅力です。私の友人が新人の頃、嚥下のリスク説明を家族に丁寧に伝える練習をしていました。最初は緊張していましたが、分かりやすく伝えるコツを身につけると、患者さんの安心感がぐんと増したそうです。というわけで、資格はゴールではなく、日々のケアを支える道具の一つ。学べば学ぶほど、食べることの尊さと、私たちの仕事の意味を深く感じられるはずです。





















