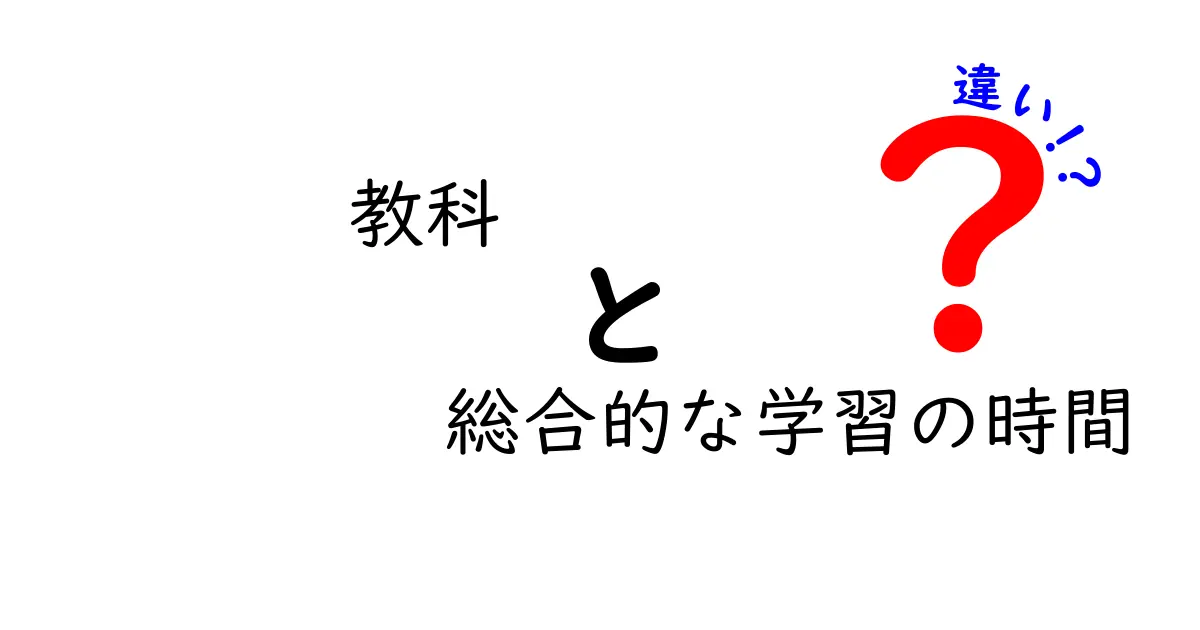

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
教科と総合的な学習の時間はどう違うの?
学校の授業でよく耳にする「教科」と「総合的な学習の時間」ですが、これらは似ているようで実は役割や目的が大きく異なります。
教科は国語、数学、理科、社会、英語など、それぞれ専門の内容を学びます。基本的な知識や技能を身につけることが目的で、テストなどで習得度を測ることが多いです。
一方、総合的な学習の時間は決まった教科書も無く、テーマに沿って自分で課題を見つけたり調べたりしながら考える時間です。たとえば環境問題や地域の歴史、スポーツ活動など幅広い内容からテーマを選ぶことができます。
この時間は自分で調べてグループで話し合ったり発表したりすることで、問題解決力やコミュニケーション能力が身につく大切な時間とされています。
教科の特徴と総合的な学習の時間の特徴を表で比較
なぜ両方の学びが必要なのか?
教科の学習は学校教育の基本であり、社会で役立つ基礎的な知識や考え方を習得するために欠かせません。
けれども、単に知識を詰め込むだけでは、その知識を活かして新しい問題を解決する力はなかなか育ちませんよね。
そこで、総合的な学習の時間が活躍します。この時間を通じて、自分で問題を発見して調べ、みんなで話し合うことで、実際の社会で必要な力を身につけることができるのです。
たとえば、自分の地域の歴史について調べレポートを作ることで、教科書の歴史の知識がより深まり、自分の生活にもつながる学びになります。
つまり、教科で基礎固め、総合的な学習の時間で応用力や表現力を育てる――この両方がバランスよくあるからこそ、豊かな学びが実現します。
まとめ
・教科は基礎知識や技能の習得が目的で、決まった範囲と方法で学ぶ
・総合的な学習の時間はテーマに沿った探究や話し合いを通じて実践的な力を育てる場
・両者をバランス良く学ぶことで、しっかりとした基礎力とともに主体的に考え行動する力が身につく
これからの学校生活で、それぞれの違いを理解し、自分の学び方を工夫するともっと楽しくなりますよ!
「総合的な学習の時間」って一言でいうけど、実はかなり自由度が高いんですよね。教科書や決まった授業内容がないので、自分で興味のあるテーマを選んで調べることもできるんです。例えば、好きなスポーツの歴史を調べてみたり、地域の祭りについて深く知ったり。
こんな風に自分から学びを作っていける時間はなかなか学校の中でも珍しいんですよ。もちろん難しい部分もありますが、グループで意見を出し合ったり発表したりするうちに、自然と考える力やコミュ力がアップしていきます。だから「総合的な学習の時間」は実は学校生活の中でとても貴重なチャンスなんです。





















