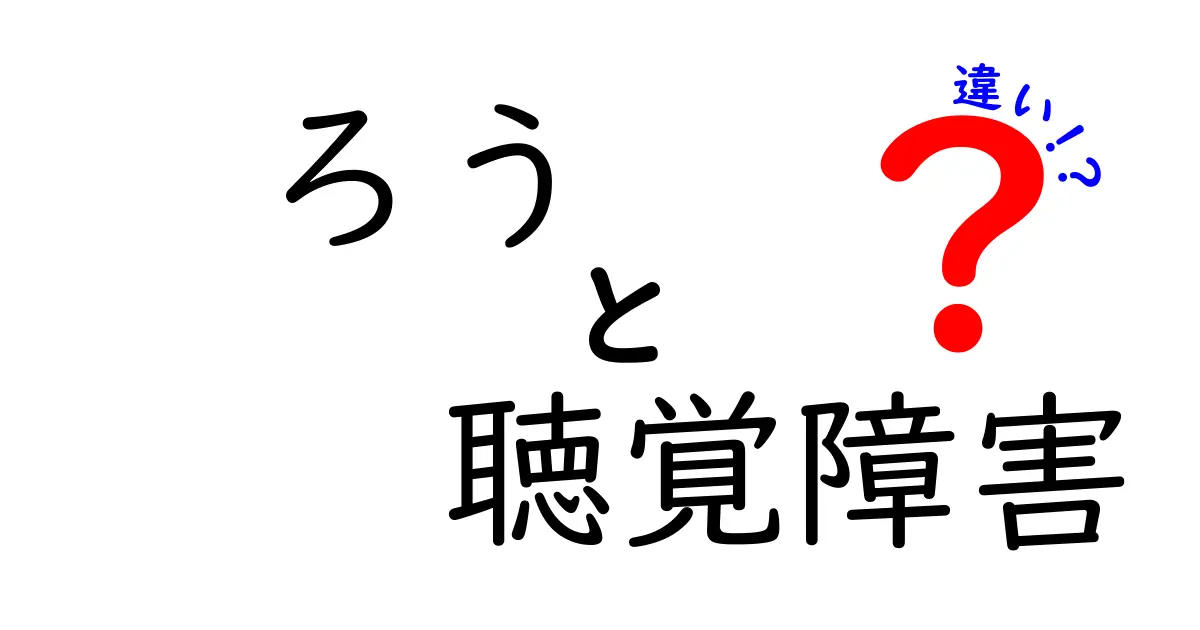

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ろうと聴覚障害の基本的な違いを知ろう
ここではろうと聴覚障害という二つの言葉が何を指しているのかを基本から説明します。まずろうとは難聴の状態を前提として生まれつきまたは後天的に聴覚に障害を持つ人々を指す言葉です。特に聴覚を使うコミュニティ手話を中心とした生活アイデンティティを重視する場面で使われることが多いです。ここで押さえたいのはろうは文化的社会的アイデンティティを含む語として使われることがあるという点です。次に聴覚障害は医療用語としての表現で聴覚の機能障害そのものを指します。医学的評価や支援制度の話題で使われることが多く個人のアイデンティティよりも状態の説明に重点が置かれます。これら二つは似ているようで使われる場面やニュアンスが異なります。例えば学校の配慮を話すときには聴覚障害を持つ児童という表現が適切な場合が多いですが、 Deaf communityの話題や手話の教育文化活動を語る場面ではろうの児童ろう者という言い方が自然です。さらに社会的な認識の違いも重要でろうという言葉は個人の障害だけでなくコミュニティの結びつきや言語としての手話の価値を含むことがあります。逆に聴覚障害という言葉は障害の診断や支援の枠組みを想起させ医療や行政教育の現場でよく使われます。最後に言葉の選び方は相手の好みや文脈にも左右されるため初対面や公式の場では相手に合わせた表現を選ぶことが大切です。
日常と専門の語彙での違い
日常生活の会話では聴覚障害がある人と表現することが多いです。これは事実を説明する際に分かりやすく差別偏見を避けるための着地点にもなる表現です。ただしここで大切なのは人を単なる障害としてラベル付けしないことです。相手の名前個性得意なこと使えるコミュニケーション手段を尊重して話すことが大切です。手話を使う人は手話を前提とする場面を作ることでコミュニケーションを円滑にします。一方教育や医療の場国の制度の話題になるとろうや聴覚障害は使い分けの判断が必要になります。たとえば学校の支援計画を作る際には個人のニーズを中心に据えた表現が推奨され可能な限りアクセスを確保することが求められます。聴覚補助機器字幕手話通訳聴覚情報の代替手段などどの手段が適切かは個人の状況と希望で異なります。ここで覚えておきたいのは語彙は相手の立場を尊重するための道具だという視点です。誤解を避けるためにも場面ごとに適切な用語を選ぶ努力を続けることが大切です。
教育支援の現場での使われ方の違い
教育の現場ではろうと聴覚障害の区別が実務に影響します。手話が主なコミュニケーション手段の児童には教室の情報を手話通訳や字幕視覚資料などで提供する工夫が必要です。 ろうの子どもたちの文化的ニーズに応える取り組みとして手話教育の充実や同じくろうの友人と交流する場の確保が進んでいます。一方医療的行政的な場面では聴覚障害の程度を測定する検査難聡用補聾器の適合教育支援の申請手続きなどが中心になります。ここでも 言葉の選び方 が重要で障害の説明だけでなくできること得意な学習スタイルを強調する表現が使われます。学校の方針としては手話と口話の両方を尊重する二重アプローチを選ぶケースが増えています。これにより聴こえない子どもも仲間の一員として授業に参加しやすくなり自己肯定感が高まります。最後に保護者との連携も大切です家庭と学校が同じ言葉遣いで情報を共有することで支援の連携がスムーズになります。ここまでの話をまとめると現場では単純に障害をどう支援するかだけでなくどの言語どの手段でどうコミュニケーションをとるかという問題設定が核心になります。
ろうと聴覚障害の違いを表で整理
放課後の教室で友だちと雑談していたときろうという言葉の意味を深掘りしました。私たちは日常の会話で聴覚障害という言葉を使いがちですが、それだけでは伝わらないニュアンスがあると気づきました。ろうは手話を中心とするコミュニティや文化的アイデンティティを含む語として使われることが多く、聴覚障害は医療や教育の場で聴覚機能の障害を説明する言葉です。この違いを知っておくと相手を尊重した話し方ができるようになります。結局のところ言葉は伝わり方を決定づける道具なので、場面に応じて適切な語を選ぶ練習をするとよいです。





















