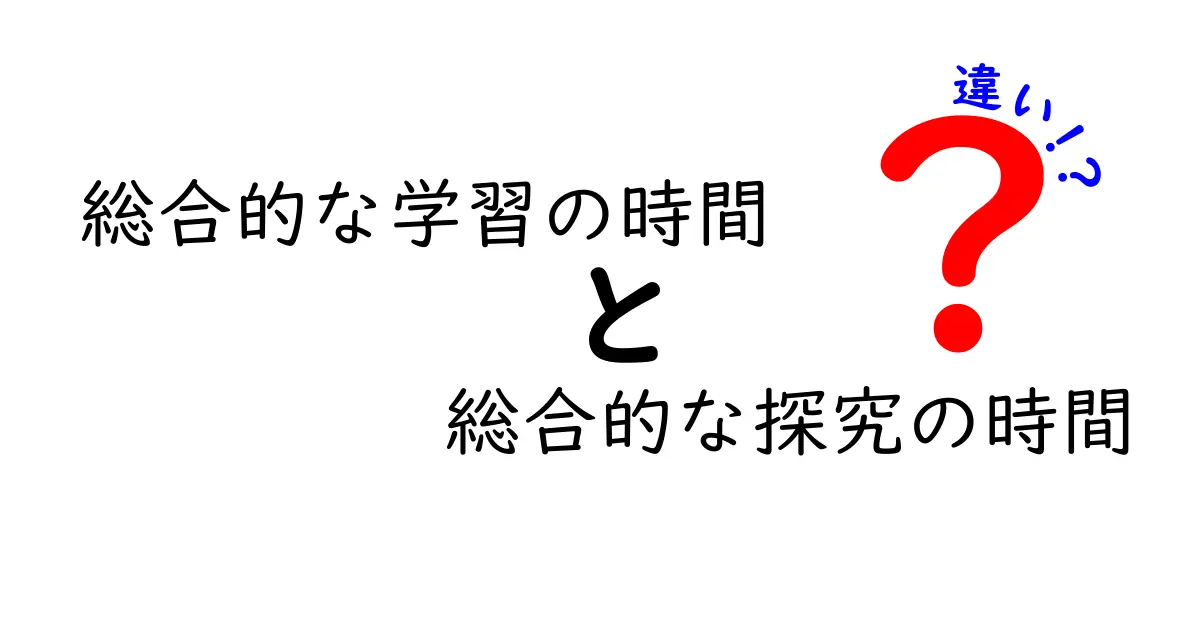

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
学校で「総合的な学習の時間」と「総合的な探究の時間」という言葉を聞いたことがありますか?
どちらも学びに関する時間ですが、名前が似ていてとても混乱しやすいです。
今回は、この二つの違いについてわかりやすく解説します。中学生でも理解できるように簡単な言葉で説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
総合的な学習の時間とは?
「総合的な学習の時間」は、主に平成20年代までの小・中学校で導入されていた学習の時間です。
学校の教科とは別に、生徒が自分の興味や関心に基づいて学習を深めるための時間です。
この時間は、教科の枠にとらわれず、さまざまな分野の知識や技能を組み合わせて取り組むことが大切でした。
たとえば、学校の周りの環境調査や地域の歴史を調べるなど、自主的にテーマを決めて学習を進めることが中心です。
また、グループで話し合ったり、発表したりして、お互いに意見を交換することも重要なポイントでした。
この時間を通じて自分で考え、問題を見つけ解決する力や表現力を育てることがねらいでした。
総合的な探究の時間とは?
「総合的な探究の時間」は、最近の学習指導要領で新たに位置づけられた時間です。
主に令和の時代に入ってから、小・中・高校の教育で導入されている新しい取組です。
「探究(たんきゅう)」という言葉が示す通り、より深く自分の興味関心に基づいた研究や調査を重ねていく学習の時間です。
ここで大切なのは、単に調べるだけでなく、「なぜそうなるのか?」「どうすればよくなるのか?」といった疑問を持って深く考察し、課題解決につなげていくことです。
また、ICT(情報通信技術)を積極的に活用し、インターネットで情報収集したり、デジタル機器で発表したりすることも増えています。
そのため、現代の社会や未来を見据えた実践的な学びが強調されています。
総合的な探究の時間は、単なる知識の習得ではなく、自ら問題を発見・解決する力や情報を活用する力を育てることを目指しています。
総合的な学習の時間と総合的な探究の時間の違い
この二つの時間は名前が似ていますが、具体的には以下のような違いがあります。
| ポイント | 総合的な学習の時間 | 総合的な探究の時間 |
|---|---|---|
| 設置時期 | 主に平成20年代まで | 令和時代から導入 |
| 学習の目的 | 幅広く知識や技能を組み合わせる学び | 問題発見・解決力や情報活用力を高める |
| 学習の進め方 | テーマを決めて調べたり話し合ったり | より深く疑問を掘り下げ調査・研究 |
| ICTの活用 | あまり強調されていない | 積極的に活用し、デジタル化が進む |
| 到達目標 | 自己表現力や協働性の育成 | 課題解決力や情報活用能力の育成 |
この表を見ると、時代の変化とともに学びの内容も進化していることがわかります。
どちらも大切な教育の時間ですが、「総合的な探究の時間」は今の社会により適した学び方として注目されています。
まとめ
「総合的な学習の時間」と「総合的な探究の時間」は、名前が似ているため混乱しがちですが、
設置された時期や目的、学習の進め方に違いがあります。
総合的な学習の時間は幅広く協働や表現力を育てるのが特徴で、
総合的な探究の時間はICTを活用しながらより深い問題発見と解決を目指します。
今後も自分で考え、社会で役立つ力を伸ばしていくための重要な時間として大切にされるでしょう。
ぜひ、この違いを理解して、学校の授業や自主的な学びに役立ててくださいね。
「総合的な探究の時間」でよく話題になるのがICT(情報通信技術)の活用です。
今ではスマートフォンやパソコンを使って、自分でテーマを深く調べたり、グループでオンラインで話し合ったりもできます。
昔の「総合的な学習の時間」では、図書館で本を調べたり先生に聞いたりするのが主でしたが、今はネットの情報を活用して、最新の社会問題や環境問題をリアルタイムで知ることが可能です。
こうしたICTの使い方が、探究活動をより面白くて深いものにしているんですよ。
ただし、ネット上の情報は正しいとは限らないので、信用できる情報かどうか見分ける力も大事になっています。
これが、今の学校で求められている新しい力の一つなんですね。
前の記事: « 指導案と指導計画の違いとは?わかりやすく徹底解説!
次の記事: 総合学習と総合的な学習の時間の違いとは?わかりやすく解説! »





















