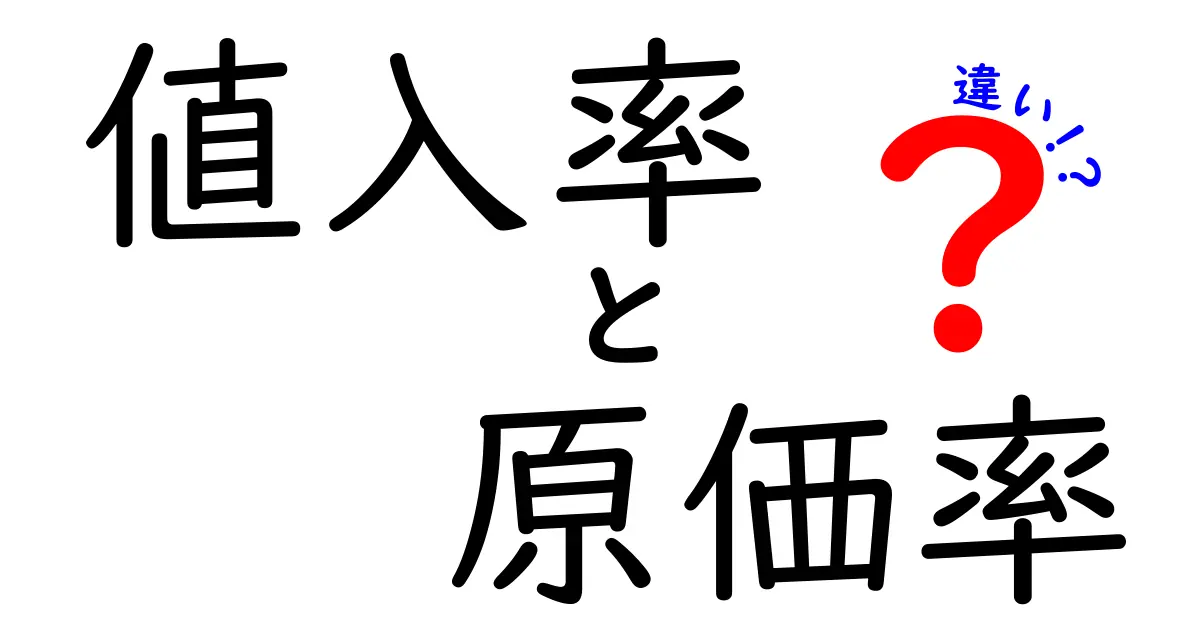

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
値入率と原価率とは?基本の意味をやさしく理解しよう
ビジネスやお店の経営でよく使われる「値入率(ねいれいりつ)」と「原価率(げんかりつ)」は、商品がどれくらい売れたかや利益を計算するときに大切な言葉です。
値入率は、商品の売値と仕入れ値の差、つまり利益がどれくらいあるかを割合であらわした数字です。簡単にいうと、売る値段の中にどれだけの利益が含まれているかを示しています。
「この商品は仕入れが1000円で、売値が1500円なら、利益は500円ですよね。
この場合、値入率は500円 ÷ 1500円 × 100 = 約33.3%」という計算になります。
一方で原価率は、売値の中に占める商品の仕入れ値の割合を示します。つまり、売値に対して実際にかかった費用がどれくらいかを示す数字です。
上の例でいうと、1000円 ÷ 1500円 × 100 = 約66.7%となります。
つまり値入率は利益の割合、原価率は費用の割合を見る数字と言えるのです。
この2つは足すと100%になりますが、使い方や意味が異なるので注意しましょう。
値入率と原価率の違いを詳しく比較!表でわかりやすくまとめました
では、値入率と原価率の違いをもっとはっきり理解するために、比べながら確認しましょう。
以下の表を見てみてください。
| 項目 | 値入率 | 原価率 |
|---|---|---|
| 計算式 | (売値 - 原価) ÷ 売値 × 100 | 原価 ÷ 売値 × 100 |
| 意味 | 売値に対する利益の割合 | 売値に対する原価の割合 |
| 数字の範囲 | 0~100% | 0~100% |
| 例(値) | 33.3%(利益が33.3%) | 66.7%(費用が66.7%) |
| 使い方 | 利益率の把握、販売価格の決定 | コスト管理、仕入れ価格の評価 |
この表からわかるように、値入率は利益重視、原価率はコスト重視の数字だと言えます。
どちらも経営には必要不可欠な数字なので、正しく理解して使い分けることが大切です。
値入率と原価率を知ってどう役立つ?ビジネス初心者のためのポイント
値入率と原価率を知ることは、商品を売るお店や会社の利益を守るためにとても重要です。
例えば、値入率が低すぎると「十分な利益が出ていない」ため、ビジネスが続けにくくなり、原価率が高すぎると「商品の仕入れや製造コストが高すぎて利益が減っている」ことを意味します。
逆に値入率が高すぎる場合は、販売価格が高すぎてお客さんが買いにくいかもしれません。
そのため、値入率と原価率をバランスよく管理し、適正な価格設定をすることがビジネスの成功につながるのです。
また、価格変更を検討するときも、この2つの数字を見ることで「どのくらい利益を確保できるか」「コストをどれだけ抑えられるか」が判断しやすくなります。
さらに、値入率と原価率は他の商品や他社との比較にも役立ちます。
同じような商品でも値入率や原価率は異なるため、どこに工夫をしたら利益を増やせるのかが見えてくるのです。
値入率について話すとき、実は売値が同じでも仕入れ値によって利益が大きく変わることが面白いポイントです。たとえば同じ1500円の売値でも、仕入れが800円なら値入率は約46.7%と大きくなり、利益も増えますよね。逆に仕入れが1400円なら値入率はわずか6.7%。この差はビジネスにとってとても重要で、小さい仕入れの違いが大きな利益の違いにつながることを覚えておきましょう。
次の記事: コストダウンと原価低減の違いをやさしく解説!成功のポイントも紹介 »





















