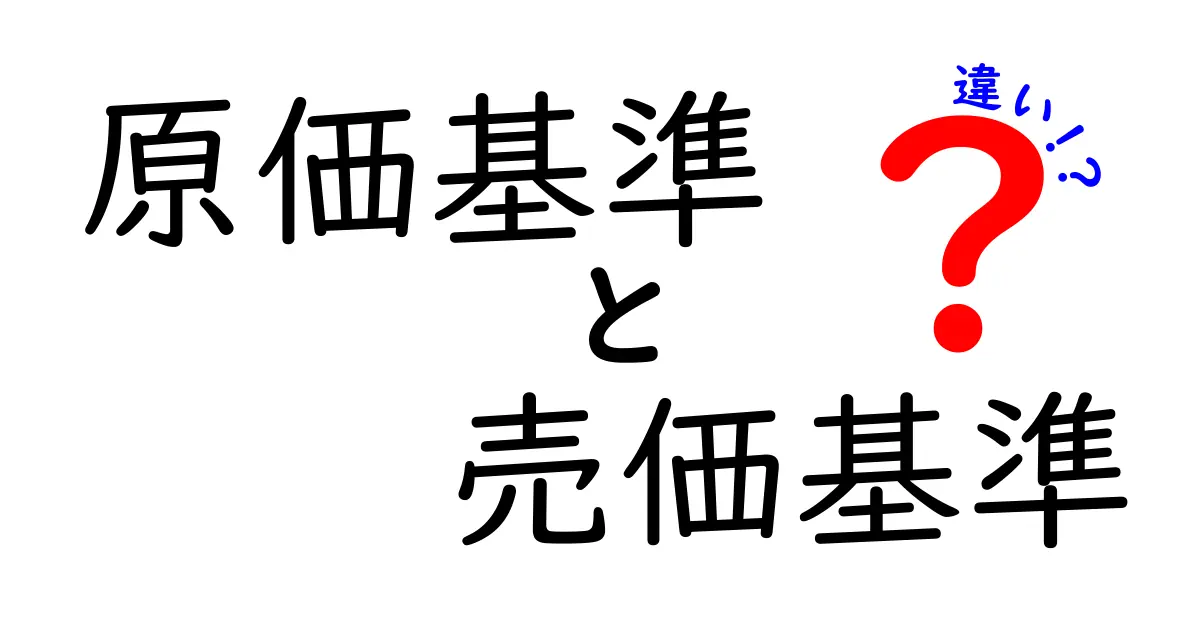

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
原価基準と売価基準の基本的な違い
ビジネスや会計の現場でよく使われる言葉に「原価基準」と「売価基準」があります。この二つの言葉の違いを理解することは、商品やサービスの価格設定や利益計算に大きな影響を与えます。
まず、原価基準とは商品やサービスを作るのにかかった費用、つまり原価を基本として考える方法です。これに対して、売価基準は商品やサービスの売る時の値段、つまり販売価格を基準に考える方法となります。
簡単に言うと、原価基準は「どれだけお金を使ったか」、売価基準は「どれだけで売るか」に重点を置いているのです。
この違いは企業の利益管理や価格設定に関わり、どちらを基準にするかで経営の方向性が変わります。
原価基準のメリットとデメリット
原価基準の最大のメリットは、商品やサービスの作成にかかったコストを正確に把握できる点です。これにより、無駄な費用を削減しやすくなります。
また、コストコントロールがしやすくなるため、企業が効率的な生産やサービス提供を目指す時に役立ちます。
一方で、原価基準は市場の状況や競合他社の価格を考慮しにくいのがデメリット。例えば、原価が高くても市場価格が低ければ、売れにくくなるリスクがあります。
さらに、原価基準だけで価格設定を行うと、利益率が低くなったり、販売戦略が硬直化する可能性もあります。
売価基準のメリットとデメリット
売価基準は価格を決める際に市場の需要や競合の価格を考慮しやすい点が大きなメリットです。
この方法は顧客が支払う価格から逆算して利益や原価をコントロールするので、販売戦略が柔軟に立てやすく、時代の変化にも対応しやすくなります。
しかし、売価基準に頼りすぎると原価が高くなっても高い価格を維持しようとして、顧客離れを招くことがあります。
また、価格競争に巻き込まれると利益が圧迫され、経営が厳しくなるリスクもあります。





















