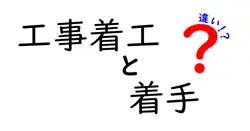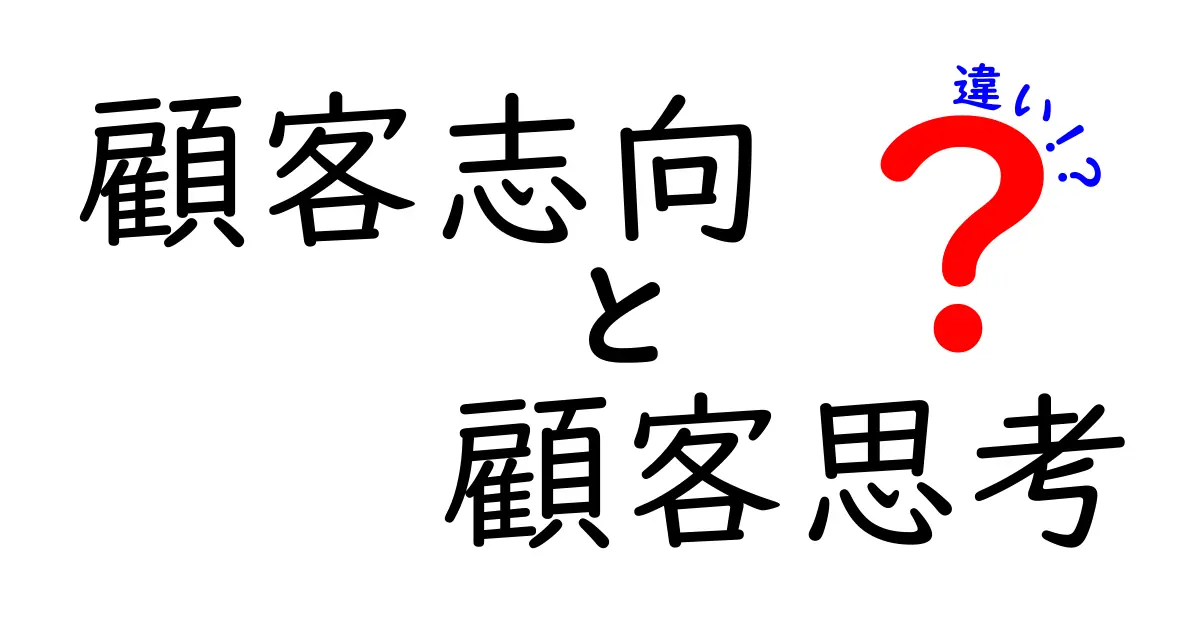

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
顧客志向と顧客思考の違いを理解する
顧客志向と顧客思考は似ているようで実は別の意味を持つ考え方です。顧客志向とは組織の理念や戦略の中心に顧客の満足と価値を置く考え方を指します。市場の声を集めてそれを意思決定に反映させることを意味し、長期的な信頼関係の構築をゴールとします。製品を何で作るかどう作るかといった設計の方向性や料金設定、ブランドの約束事などが顧客志向の価値観に引っ張られて変化します。短期の売上だけでなく顧客の本当のニーズを満たすことを優先する姿勢がこの考え方の核です。
一方で顧客思考は日々の業務の中で顧客の立場を前提に判断する力を指します。設計の段階から使い勝手の良さや操作の直感、情報の分かりやすさを想像して意思決定することです。開発現場では仕様の細部を顧客視点でチェックし、サポートでは質問に対して分かりやすい説明を用意します。顧客志向が戦略の核であるのに対し顧客思考は実務の判断基準であり、現場の言葉で実行力を生み出します。双方を分けて考えると現場と経営のズレが生まれやすく、逆に両者を結びつけると顧客体験が一段と向上します。
この違いを正しく使い分けるためのポイントを整理します。まず顧客の声を集める仕組みを整え、声の質を高めることが大切です。次にその声を戦略と日常の業務両方に反映させる仕組みを作ります。リーダーは方針を明確にし、現場は日々の判断基準として顧客志向と顧客思考を組み合わせて運用します。
また評価指標として長期的な顧客満足度と即時の使い勝手の改善を両方追うと、組織全体が顧客を中心に回るようになります。
この段階で重要なのは言葉だけでなく実際の行動がつながって初めて意味を持つということです。
ここまでの話を一つの枠組みにまとめると以下の表のように見えてきます。顧客志向は戦略の中心であり長期的な価値創造を狙い、顧客思考は日常の判断を支える現場の視点です。これを組み合わせることで製品は使われ方を想定した形で設計され、サポートは顧客の声に寄り添う形で改善されます。関係する部門間で共通の言葉を使い続けることが、結果として顧客体験の連続性を生むのです。
今日の小ネタは顧客志向を雑談風に深掘りします。友達とカフェで話していたとき、顧客志向をどう伝えるかで意見が分かれました。友達は何かを売る前にまず誰に届けたいのかを考えるべきだと言い、別の友人は売上の数字ばかり見ていると指摘しました。私は顧客志向を高めるには数字と声の両方が必要だと答えました。声だけを追うと現場の使い勝手が後回しになり、数字だけを追うと顧客の本当の困りごとを見失います。実はこのバランスが最終的な成功のカギになるのです。
この話のポイントは、顧客志向は理屈ではなく行動の連続性だということです。新機能を提案するときにはまず何を解決したいかを書く、その解決は顧客がどう感じるのかを言語化する、そしてそれを試行する。言葉だけのロジックではなく、実際の使い心地に落とし込むステップが大切です。
前の記事: « 団結力と結団力の違いを徹底解説!中学生にも伝わる見分け方