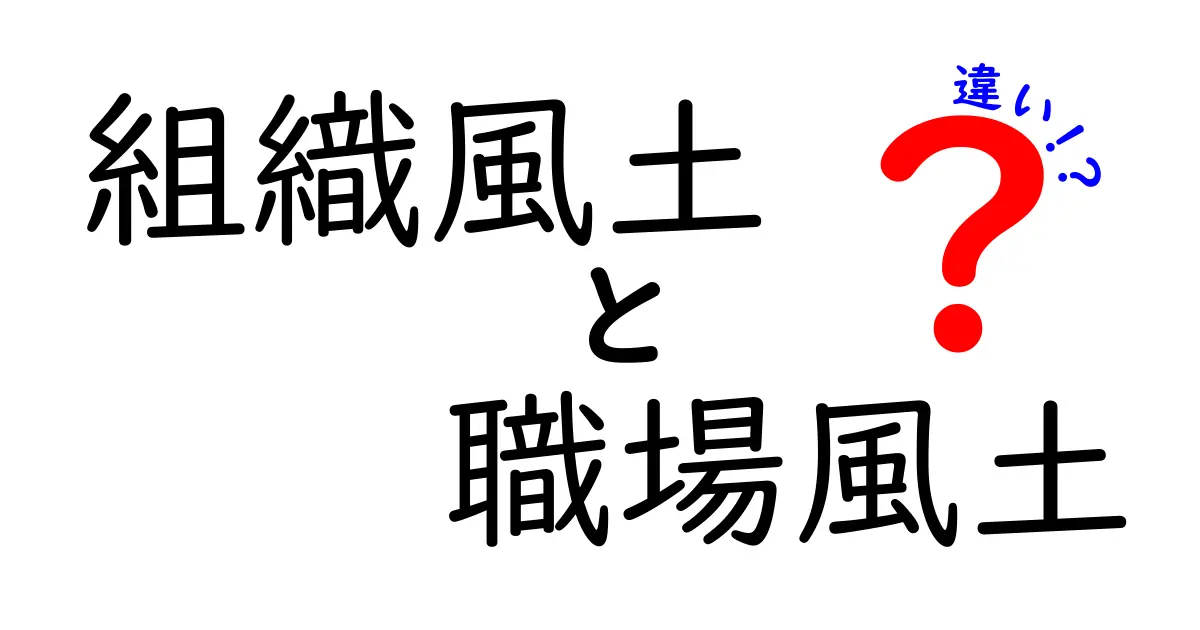

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:組織風土と職場風土の違いを読み解く
組織風土と職場風土の違いを一言で説明するのは難しいですが、まずはざっくりしたイメージを持つことが大切です。
組織風土とは、会社全体が長い時間をかけて培ってきた価値観や信念、行動の基準、制度のしくみなど、組織そのものの“性格”のことです。これが強いと、社員がどんな判断をするべきか、どう協力するべきか、どう評価されるかといった根本的な決定に影響します。
一方、職場風土は日々の現場・職場で感じる空気感です。部門ごとの雰囲気、上司と部下のやり取り、会議の進め方、情報の共有の仕方など、今この場でどう働くかに直結します。
組織風土と職場風土は別物のようでいて、実は強く影響し合います。経営方針がはっきりしていても、現場の会話が閉鎖的ならアイデアは出にくく、逆に現場の協力が生まれても組織全体の方向性が見えにくいと混乱が生まれます。
組織風土は組織全体のDNA、職場風土は日々の居心地と意思決定の現場と考えると、違いが見えやすくなります。つまり、組織が大切にする価値観を職場の実務にどう落とし込むかが、働く人のモチベーションと生産性を左右します。
組織風土と職場風土の基礎を知ろう
組織風土を構成する要素には、価値観・信念・習慣・制度・リーダーの行動様式・組織の歴史などが挙げられます。これらは個人の行動の背景となり、長い時間をかけて組織全体の“空気”を作ります。
職場風土は、部門ごとの習慣や日常の言葉遣い、情報の伝え方、協力の仕方、成果をどのように評価するかといった、いまこの瞬間の現場の実感に影響します。
この二つが適切に連携していると、従業員の信頼感が高まり、離職率が下がり、創造性も発揮されやすくなります。
日々の行動の積み重ねが風土を形作るという視点を持つと、何を変えるべきかが見えやすくなります。例えば新しい試みを推進する場合、経営陣の考え方と現場の実践がずれていると抵抗が生まれます。そこで、経営メッセージと日常の仕組みを揃える取り組みが効果的です。
日々の現場で現れる差と改善のヒント
現場で見える風土の差を見つけるには、まず観察する癖をつけることが大事です。
リーダーの言葉と実際の行動が一致しているか、重要な情報を誰がどの順序で共有しているか、会議の進め方は参加者全員が発言できる雰囲気かをチェックします。風土の改善には小さな実践の積み重ねが有効です。
例えば、 onboarding(新人の迎え入れ)での手順を整える、フィードバックを具体的な事例とともに定期的に伝える、遠隔勤務でも情報共有のルールを明確化する、等です。これらは局所的な改善のように見えて、組織全体の信頼感を高める効果があります。
また、透明性・公正性・共感の3つを土台にすることが大切です。透明性とは、意思決定の根拠を可能な範囲で共有すること、 公正性とは人を平等に扱い評価の基準を明確化すること、共感とは相手の気持ちや立場を理解し対話を続けることです。
これらを日頃の会話や報告の中で自然に使えるかどうかが、風土を変える第一歩になります。
ケーススタディと実践のコツ
実践的なコツとしては、まず小さな実験を行い、結果を共有して次へ活かす循環を作ることです。例えば、3か月間の「オープンな質問歓迎デー」を設ける、会議のルールを見直し、発言の順番を決めず全員が話せる時間を確保する、新人の最初の90日間は先輩がペアで付き添い、具体的な行動例を一緒に作る、などが実用的です。こうした取り組みを継続すると、風土は徐々に変わります。後日、アンケートや離職率・業務効率の指標をチェックすることで、変化の度合いを数値として確認することも可能です。さらに、成功体験だけでなく失敗例も共有し、何がうまくいかなかったかを皆で検討することで、組織としての学習力が高まります。このように、風土は“一度に変えるもの”ではなく、“日々の積み重ねと学びの連鎖”で形づくられるのです。
友達と放課後プロジェクトの話をしている想像をしてみて。組織風土は学校の校風みたいな長期の性格で、校則や大切にしている価値観がたまにもっとも強く現れる場所。職場風土は授業ごとのクラスの雰囲気のように日々の表情や言い方、協力の仕方が変わる“今ここ”の空気。ある日、リーダーがオープンな質問を歓迎する姿勢を見せ、同僚が率直な意見を言いやすくなると、私たちの提案数が増え、モチベーションも上がる。大事なのは、風土を作る“人の言葉と行動の繰り返し”だと私たちは気づく。





















