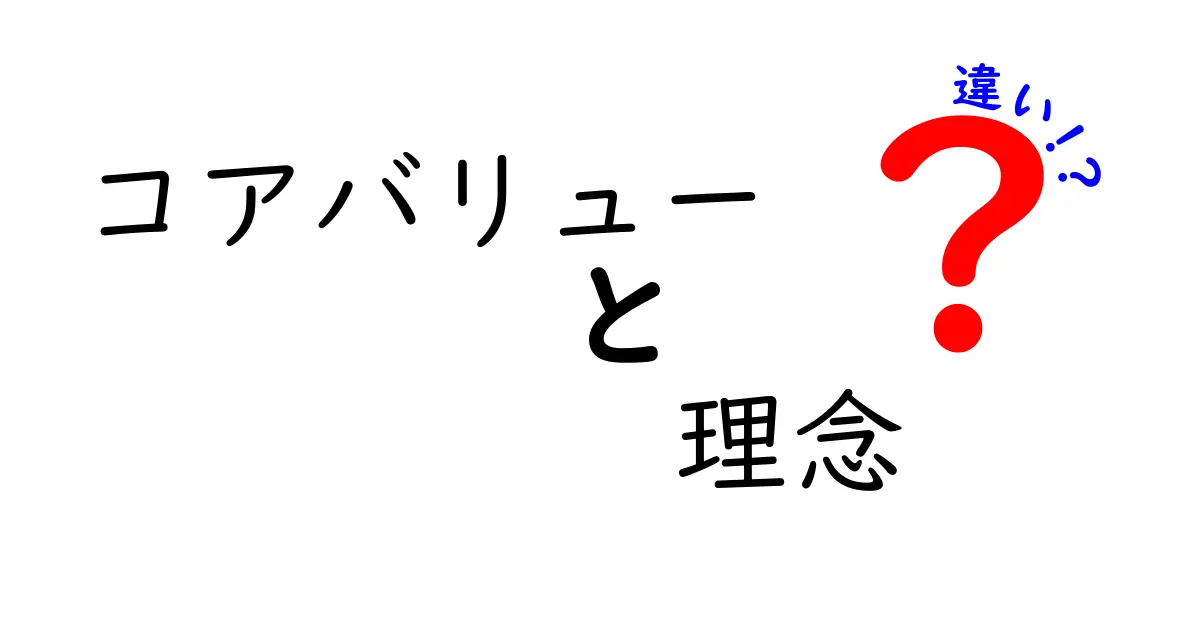

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
本記事の目的と全体像
この章では、コアバリューと理念、そして違いについて基礎から丁寧に解説します。学びの場でも、部活のリーダーでも、家庭の決断でも、こうした考え方を知っていると迷いが減ります。まずは用語そのものの意味を正確に捉え、次に具体的な違いを日常の意思決定に落とし込むやり方を紹介します。
これからの話は、難しく考えずに、身近な例を使って説明します。
最後に、実務で使える整理のコツを3つ提示します。
コアバリューとは何か?なぜ“核”が大切なのか
コアバリューは、組織が「何を一番大切にするのか」を示す根本的な価値観のことです。例としては「正直さ」「顧客第一」「挑戦を恐れない心」など、日々の選択を支える“核”になります。
この核は一度決まると長い時間、行動や判断を左右します。
なぜ長く影響するのかというと、短期的な利益よりも継続的な信頼を生む力があるからです。仕事の現場では、ミスが起きたときにも、コアバリューが手がかりになります。たとえば顧客第一が強い企業なら、問題解決の優先順位は常に「顧客の立場から最善の解を探すこと」になります。
またコアバリューは、組織の雰囲気や日常のやり方を決める指針にもなります。新しい人材が入ってきたときにも、どう動くべきか悩んだときにも、核となる価値観が道しるべになります。
理念とは何か?組織の方向性と信念の結びつき
理念は「どこへ向かうのか」という長期的な方向性と信念を示します。夢や目標、そしてそれをどう達成するかという道筋が含まれており、組織が成長するための大きな設計図にもなります。理念はただの目標設定ではなく、組織の存在意義を説明する言葉です。たとえば「世界をより良くするために製品を届ける」という理念があれば、全員の努力はその方向性に合わせて調整されます。現場の細かなルールは理念を実現する手段に過ぎず、信念がぶれない限り、行動は連携して進みます。
違いを日常の意思決定に落とすための具体的な見方
コアバリューと理念の違いを日常の意思決定に落とすには、まず「適用の場面」を分けることが大切です。
コアバリューは、毎日の小さな選択の軸になります。「この行動は核となる価値観に合うか?」と自問する習慣をつくるのが近道です。
一方理念は「この長期的な方向性を達成するために今何を優先するか」という戦略的判断に使います。つまり短期の効率よりも長期の影響を見据える判断の基準として機能します。
実践のコツと日常への落とし込み
最後に、学校の部活やクラブ活動、部門のプロジェクトで使える実践のコツを3つ挙げます。
1つ目は“言葉の共有”です。コアバリューと理念を全員が短い言葉で説明できる状態にします。例を作って壁に貼ると効果的です。
2つ目は“意思決定の振り返り”です。会議の終わりに“この決定は価値観と一貫していたか”を確認します。
3つ目は“継続の力”です。初めはうまくいかなくても、試行・修正を繰り返すことで、徐々に組織の動きが揃います。
友だちと部活の話をしていて、コアバリューという言葉が出たとき、私はこう考えました。コアバリューは“その部活の心臓の芯”のようなもの。朝の準備で遅刻をしそうなときこそ、正直さや仲間を大切にする姿勢が試されます。理念は長い道のりの羅針盤。つまり部活のビジョンを示す地図であり、今この練習をする意味を説明してくれます。だから、部員みんなが同じ方向を向いて練習するためには、日々の小さな行動と長期の目標がリンクしていることが大事です。





















