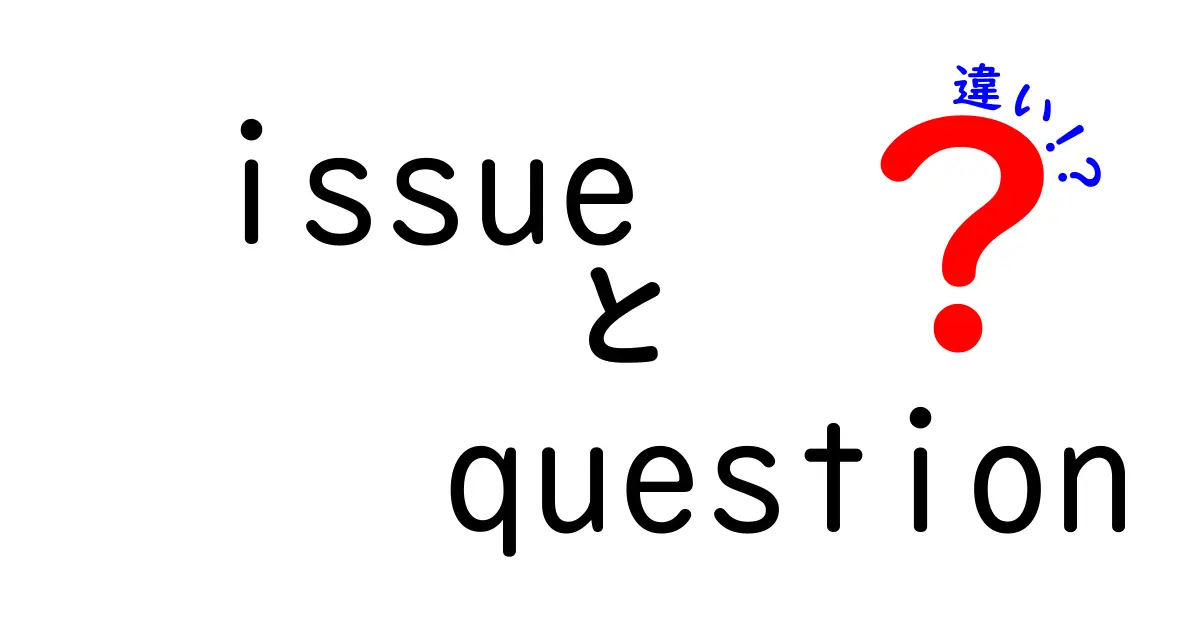

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
issueとquestionの違いを正しく理解するための基本
「issue」と「question」は、英語の会話や文章で頻繁に出てくる言葉ですが、日本語訳を決めるときに迷うことが多い語です。まず基本を押さえると、issueは“問題・論点・話題”を指す語であり、解決策を検討したり、議論の中心になる事柄を表す語です。次にquestionは“質問・問い”を意味し、相手に情報を求めたり、答えを引き出す目的で使われます。この違いを日常会話に置き換えると、issueは議題のような大きな話題、questionは誰かに確認したいこと・知りたいこと、というイメージになります。
この違いを理解しておくと、相手に伝えたい意図がはっきり伝わり、誤解を減らすことができます。
次にニュアンスの違いを見てみましょう。issueには複数の関係者や時間軸を含むことが多く、ある程度の長さや深さを持つ話題として扱われることが多いです。対してquestionは個別の情報に焦点を当て、答えが一つまたは限られた範囲で出てくることが多いです。
この点を意識すると、文章の構成も変わってきます。例えば「この件のissueを整理しましょう」という表現は、問題点や論点を洗い出して整理する意味であり、「この件について質問があります」という表現は、特定の情報を求める意図を明確に示します。
使い分けのコツとしては、まず意図を自分だけでなく相手にも伝えることを最優先に考えることです。情報を探すときはquestionを使い、議論の焦点や課題を示すときはissueを使うと理解しやすくなります。さらに、困ったときの簡単な判断基準として、動詞としての使い方を見れば分かりやすいです。質問を作るときは動詞を中心に考え、表現を短く具体的にします。論点を提示するときは名詞としての「issue」を用い、複数の観点を並べるときは「issues」という複数形を使います。これらのポイントを押さえると、英語の文章だけでなく、日本語の文章表現も整理され、伝わりたい意味が伝わりやすくなります。
下の表は、日常でよく使われる表現の比較です。用語 意味 例文 issue 問題・論点・話題 この周辺にはいくつかの重要なissueがあります。 question 質問・問い この点について質問があります。 topic 話題・テーマ 新しいtopicをみんなで話し合いましょう。
日常での使い分けと英語学習のコツ
日常での使い分けは、実は練習次第でぐっと楽になります。このセクションでは、実用的な練習を説明します。まず、文章を書くときには、issueを使う場面とquestionを使う場面を分ける癖をつけると良いです。例えば、あるプロジェクトの進行状況を話すときには論点を挙げ、進捗を確認する質問を併せて用意することで、読み手に目的が伝わりやすくなります。対して、誰かに情報を尋ねるときや、原因を問うときにはquestionを使います。ここで重要なのは、読者が話の流れを追いやすくするため、情報の出し方と求め方を分けることです。文章の導入部でissueを掲げ、本文でそれを解決するための質問を設けると、読み手は話の全体像を理解しやすくなります。
他にも、質問の作り方にはコツがあります。具体的には、5W1Hを意識して「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」「どうやって」という要素を明確にします。これにより、質問があいまいになるのを防ぎ、相手も答えやすくなります。
また、学習の場面では、与えられたテキストや文章の中で、どの語がissueとして扱われ、どの語がquestionとして扱われているかを分析すると、言語感覚が身につきます。これは中学生にもできる練習で、毎日少しずつ取り組むと、英語のニュースや教科書の読み取りにも役立ちます。最終的には、場面を想像しながら使い分ける力が身につき、文章の伝わり方が変わります。
実践のコツを短いリストでまとめます。
- 情報を求めるときにはquestionを選ぶ
- 論点や話題を提示するときにはissueを提示する
- 長い議論には複数のissueを取り上げ、要点を並べる
- 質問文と断定文を混ぜず、役割を分けて明確にする
さらに練習として、日常の会話や授業中の発言を録音して、「この場面で使った語が本当に適切だったか」を自分で評価するのがおすすめです。自分の発言を客観的に聞き直すと、どこで混同が起きやすいかが分かります。
友だちとチャットで、issueとquestionの違いについて雑談した。結論だけど、issueは“解決をめざす論点や話題”で、議論の土台になる。questionは“情報を集める問い”で、答えを引き出すための道具。二つを混ぜると混乱することが多いので、会話の流れを見て使い分けると伝わりやすくなる。
前の記事: « dipとsopの違いを徹底解説!意味・使い方・誤解を一発で解く





















