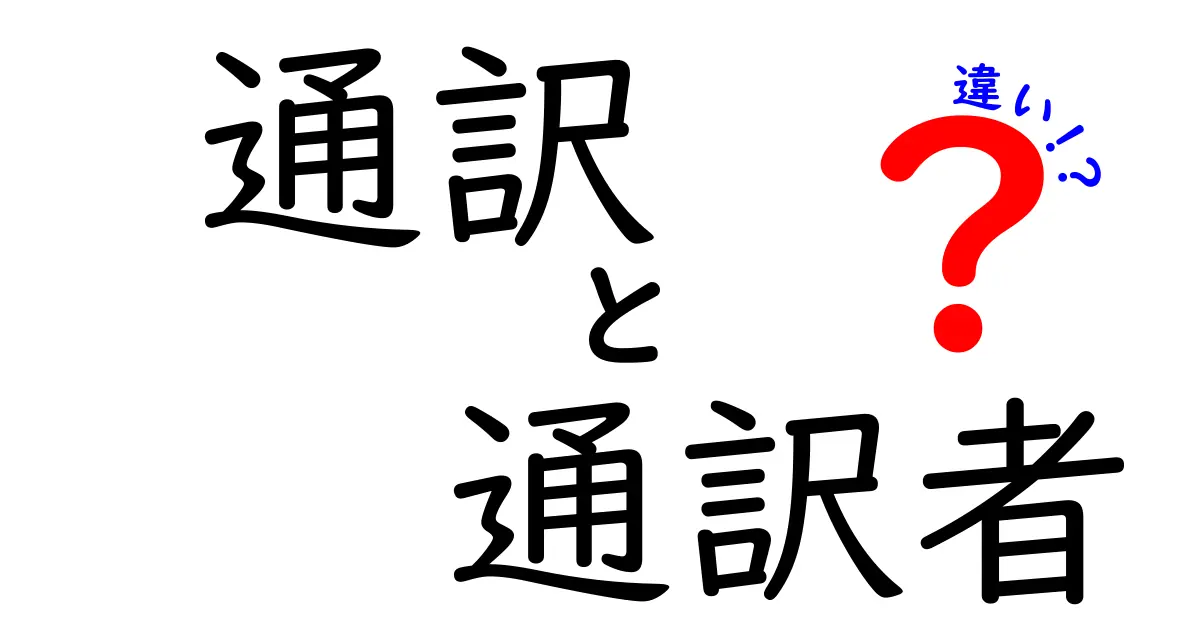

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
通訳と通訳者の基本的な意味の違いを知ろう
通訳と通訳者の違いを正しく理解するためにはまず基本用語の意味をはっきりさせることが大切です。通訳とは話された言語を別の言語にリアルタイムで変換して伝える行為そのものを指します。つまり発言を聞いてすぐに別の言語に直して伝える作業の総称です。場面は会議やイベント、取引の場面などさまざまです。では誰がこの通訳を実際に行うのかというと、それを担う人が通訳者です。通訳者は通訳という行為を実行する職業的な人を指し、専門の訓練を受けて語学力だけでなく聴く力や理解力を鍛えています。日常会話の場面でも通訳をすることはあり、学校行事の国際交流や外国人の案内役などでその存在感を発揮します。一方で通訳者と似た言葉として翻訳者がありますが翻訳者は主に紙の文章や文字情報を別言語に写す仕事を指します。通訳は「話す場」での言語変換、翻訳は「書く場」での言語変換というように役割の場面が異なるのです。
この違いを頭の中に入れておくと日本語の会話でも混乱が減ります。たとえば「私は通訳をしています」の場合は今この場で話の理解と伝達を行っていることを指します。逆に「私は通訳者です」と言うと自分がその職業の人であるという意味が強くなり、肩書きや専門性を示す表現になります。こうした違いは場面のウェイトの差にもつながり、フォーマルな場では通訳者という呼び方が適切で、カジュアルな場では通訳で十分ということもあります。
さらに実務の世界では同時通訳と逐次通訳といった言葉の違いも重要です。同時通訳は発言者の話と同時に別言語へ伝える高度な技術で、会議室の裏方で機材を使いながら進められることが多いです。逐次通訳は発言者が区切って話すたびに通訳するスタイルで、ノート取りのコツや話の構成を把握する力が役立ちます。通訳者という職業を考えるときにはこの2つの違いを理解しておくと現場での適切な対応が見えてきます。
このように通訳と通訳者は場面と役割の違いを意識するだけで、日常の会話や公式な場面での表現の使い分けがぐんとやさしくなります。
実務での使い分けと場面別の表現
実務の場では言語の専門性だけでなく場の雰囲気を読み取る力も必要です。以下のポイントを覚えておくと場面に合わせた適切な表現が選べます。
まず公式な場では自分の肩書きを強調したいときは通訳者という表現が自然です。自己紹介の際には私は通訳者ですと伝えると信頼感が生まれやすくなります。一方でカジュアルな場面では通訳という言い方でも十分伝わります。
次に通訳の種類を理解しておくと準備がスムーズです。同時通訳は専門の機材とチームワークが欠かせません。逐次通訳は発言内容を正確に拾うためのメモ取りと内容把握が不可欠です。
場面を想定しておくと緊張も減り、適切な言い回しが自然に出てきます。例えば公式の会議で自己紹介をする場合は「私は通訳者としてこの会議をサポートします」といった表現が丁寧です。友好的なイベントでは「私は通訳をします」で十分なケースもあります。
- 公式な場面では通訳者という肩書きを使うと信頼性が高まる
- 同時通訳と逐次通訳の違いを理解して準備を整える
- 普段の会話では通訳という言い方で十分な場合が多い
まとめとして、通訳は言葉の変換する行為そのものであり、通訳者はその行為を実際に行う人です。翻訳者は別言語に書かれた文章を変換する人であり、役割は異なります。これらの違いを把握しておくと、場面に応じた適切な言い回しや表現の選択が自然にできるようになります。
友達と喋っているみたいな感じで話しますね。実は通訳と通訳者は似ているけど意味がぜんぜん違うんです。通訳は“話すことそのもの”で、瞬間的に別の言語へ言い換える作業のこと。通訳者はその作業を実際にやる人のこと。だから会議で私は通訳をしますと伝えると今この場で実際に言葉を変換して伝える人だと伝わります。一方私は通訳者ですと言えば専門職としてその人を示す肩書きになります。覚え方のコツは、通訳=行為、通訳者=人、翻訳者=文章の変換、という三つのイメージをセットで覚えることです。実務では同時通訳と逐次通訳の違いも大事。前者は話しながら同時に訳す高度な技術、後者は話を区切って逐次訳すスタイル。どの場面で何を求められているのかを読み取る力が鍛えられれば、難しい場面でも落ち着いて適切な言い回しが選べるようになります。





















