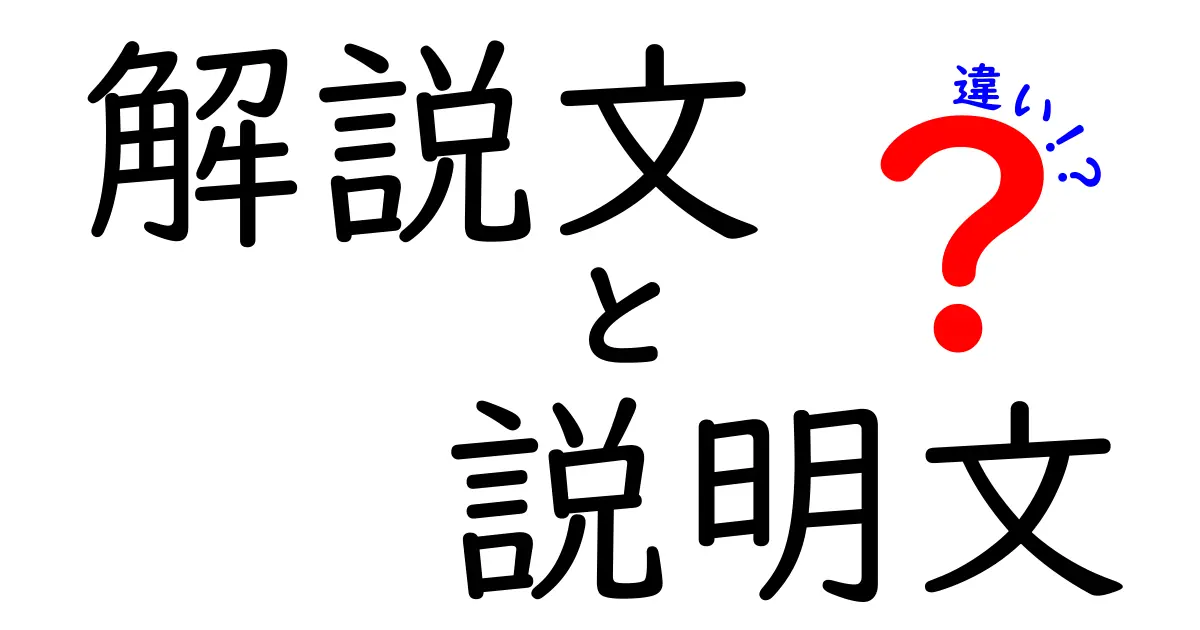

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
解説文と説明文の違いを徹底解説!読者を動かす文章設計のコツと実例
解説文と説明文は、日本語の文章を書くときに頻繁に出会う二つの言葉ですが、実際には役割と狙いが異なります。この記事では「解説文」「説明文」「違い」という三つのキーワードを軸に、どの場面でどのタイプを使うべきかを整理し、読者の理解と行動を促す文章づくりのヒントを分かりやすく紹介します。
まず前提として、解説文は背景やしくみを深掘りして説明するタイプ、説明文は実務的な手順や方法を明確に伝えるタイプです。
この違いを知ることで、同じテーマでも読者に刺さる導入・構成・表現を選べるようになります。
さらに、違いをはっきりさせる工夫として、見出しの使い方・段落の分け方・具体例の挿入・読み手の目的を意識した設計が重要です。
解説文と説明文の基本的な意味の違い
解説文はまず概念の定義を提示し、その後に要素を分解して関連する理論や背景を結びつけます。
因果関係や仕組みの流れを図解的に示すことで、読者が頭の中で“どうしてそうなるのか”を追体験できるように設計します。
読み手が専門用語で迷わないよう、最小限の語彙で丁寧に説明し、事例を用いて理解を定着させます。
対して説明文は手順・条件・前提を整理し、読者がその情報を使って実際に行動できるように導きます。
段階を番号付きリストや箇条書きで示し、短く明確な文で要点を伝えるのが特徴です。
この二つを使い分けると、教育的効果と実務的効果の両方を狙える文章が作れます。
文章を書くときのコツと注意点
文章を書くときは、まず読者の目的と背景を明確にします。
誰に伝えたいのか、読ませたい成果は何かを決めると、文体も自然と決まってきます。
次に、導入で関心を引くこと、要点を最初に示すこと、そして具体例と統計で裏付けることを意識します。
長い説明は分割して段落を細かく、読みやすさを高めるために適度に改行を入れましょう。
難解な語を避け、専門用語を使う場合は初出で簡潔に定義します。
読者の記憶に残るよう、重要なポイントは太字で強調し、目次的な役割を果たす見出しを作ります。
また、結論を最初に示す「逆ピラミッド」や、要点をリスト化する「箇条書き」も有効です。
文章が長くなると伝わりづらくなるため、適度な長さを保つ練習を重ね、読み手のペースに合わせて調整します。
読者の動機を理解する構成と見出しのつけ方
読者が最も関心を持つのは「どのように役立つのか」「何を学べるのか」という点です。
そのため、導入では読者の課題を直接提示し、本文では解決策を段階的に示します。
見出しは質問形式や具体的な数字を盛り、クリックしたくなる魅力を作ると良いでしょう。
例として「解説の核となる3つのポイント」や「初心者が最初に知っておくべき前提条件」など、読者の手を止めさせない工夫を取り入れます。
さらに、読み進める際の視覚的設計として、本文と見出しの間にブレイクを挟み、
要点を強調して読みやすさを高めます。
今日は解説文という言葉の奥深さについて、ただの説明ではなく雑談のような形で深掘りしてみます。私が思うに、解説文とは専門家の考えを一般の読者に“つなぐ橋”のような役割を果たします。難しい概念をいかに分かりやすく並べ替え、読者が自分の頭の中でその仕組みを再現できるように設計するかが命です。例えば、世の中に出回る用語を一句一行に並べるだけでは不十分で、背景の歴史、関連する理論、現場での応用を連携させることが大切です。読み手の立場に立って、何を知りたいのか、どの順番で知りたいのかを考え、必要な情報だけを整理して提示します。そうすることで、読者は新しい知識を自分のものとして取り込み、次の学習へ進む踏み台を得られるのです。
前の記事: « 指示詞と指示語の違いを徹底解説! 中学生にもわかる使い分けのコツ





















