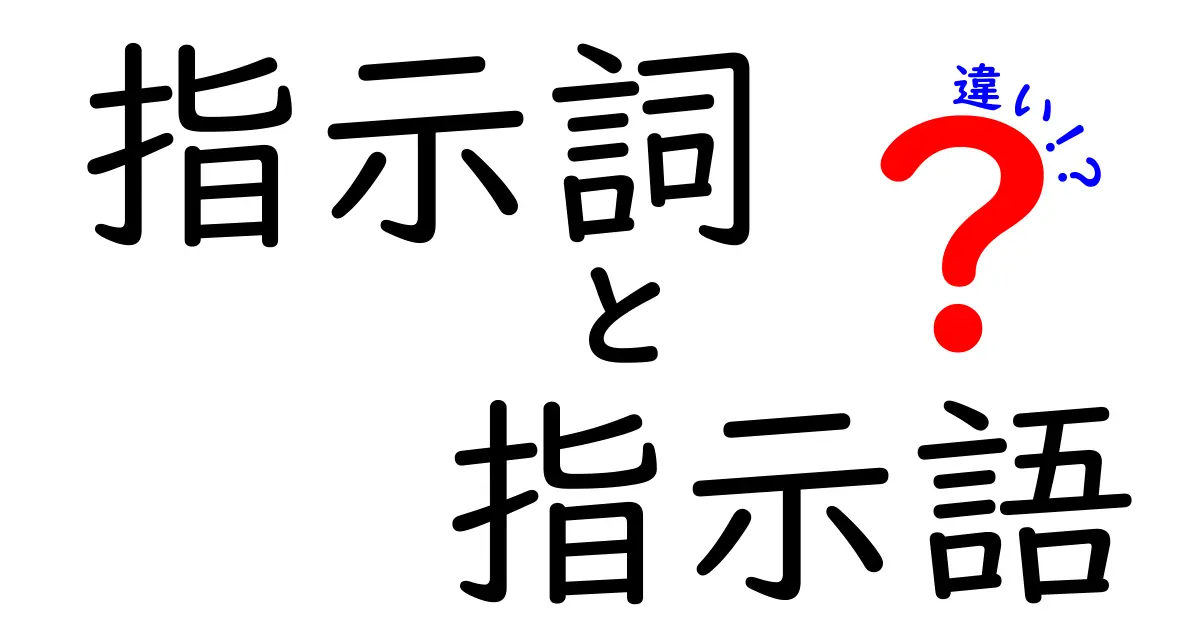

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
指示詞と指示語の違いを徹底解説! 中学生にもわかる使い分けのコツ
このガイドでは指示詞と指示語の違いをわかりやすく解説します。まず結論から言うと指示詞と指示語は似ているようで役割が少し違います。指示詞は文法の品詞の総称として使われ、名詞の前につくことでその名詞を指し示す働きをします。一方で指示語はもっと広い範囲を指す言葉のグループであり、代名詞としても形容詞としても用いられ、指示対象を具体的に示す役割を担います。日常の会話や文章作成ではこの微妙な差を意識することで読みやすさや伝わり方が変わります。以下の段落では具体的な例と使い分けのコツを詳しく見ていきます。
まず覚えておきたいのは使い分けの基本原則です。近くのものを指す時にはこのこのこのなどの指示語を使い、遠くのものや話題を指し示す時にはそのそのあのなどの語を使うと整理しやすいです。さらに代名詞的に使う場合と名詞を修飾する場合では選ぶ語が変わることを知っておくと文章が自然になります。
次に、混同しやすいケースをいくつか挙げます。説明の中で同じ言葉を何度も繰り返すと読みにくくなることがあります。その時指示語を使って代替する、あるいは指示詞の中で最も自然な形を選ぶと読みやすさが増します。例えば近さを示す場合はこれやこのを使い、距離が離れている時はそれやあのを使います。
このような考え方を日常の文章や作文に取り入れると、情報の指し示し方がはっきりして伝わりやすくなります。ここからはさらに具体的な使い分けのポイントと実践例を見ていきましょう。
本稿の目的は難しい専門用語を避けつつ、指示詞と指示語の違いを日常的な言葉で理解することです。理解のコツは、まず自分がどの役割を担っている語を選んでいるのかを意識すること、そして指し示す対象との距離感や文のつながりを意識することです。これらを意識するだけで、文章の流れは格段に良くなります。最後に、練習として身近な文章を自分で作ってみるとより効果的です。
この先の表と例を見れば、指示詞と指示語の違いが一段とクリアになります。
指示詞と指示語の基本をおさえる
以下のポイントを押さえておけば、初学者でも扱いやすくなります。指示詞は名詞の前に置かれてその名詞を指し示す働きをし、指示語はその名詞自体を代替する語や名詞を指し示す役割を担います。実生活の会話でよく使われるのはこのこのこのやそのそのといった語で、遠くを示す際にはあのという語が使われることもあります。文章を組み立てる時には、同じ語を連続して使わずに指示語で置き換えると読みやすくなります。
同じ語を多用すると冗長になり、伝えたい情報がぼやけてしまうことがあります。そのため適切な距離感を意識して使い分けることが大切です。練習として、日常の場面を思い浮かべて指示詞と指示語を入れ替えた文を書いてみると、自然な違いを体感できます。
要点は次の3つです。1) 指示詞は名詞を指し示す役割が強い 2) 指示語は指し示す対象を指し示す役割を広く持つ 3) 距離感と文脈で使い分ける これらを覚えておくと、文章の意味がはっきりと伝わります。
実例と使い分けのポイント
実用的な例を用いて具体的に見ていきましょう。
例1 この本はおもしろい。 この本を読み終えたら次はその本の映画版を見に行く予定だ。ここでは指示詞のこのとそのが使われています。
例2 この指示語は文章の中で何を指しているのかを示します。例えば それ は前に出てきた話題を受けて使われる語で、読者が理解しやすいように前文と結びつけます。
表と実例を照らし合わせるだけで、指示詞と指示語の使い分けはぐんと分かりやすくなります。
日常での練習と注意点
日常の会話や作文で練習する際は意識的に距離感を決めて使うと効果的です。近い対象にはこのこのこのを遠い対象にはあの あの というように使い分ける習慣をつけましょう。指示詞と指示語は混同しがちですが、文の意味を一度自分で言い換える練習をすると正しく使えるようになります。子ども同士の会話でも失敗を恐れず積極的に修正していくことが成長につながります。
この知識は文章作成だけでなく、プレゼンや発表の原稿作成にも役立ちます。聞き手が理解しやすい文章を作るためには指示対象を明確にすることが欠かせません。練習を重ねれば、自然と読み手や聞き手に伝わる文章が書けるようになります。
友達と雑談しているとき、指示語のこのはとても自然に耳に入るが、指示詞のこのは文中の名詞をすぐ前に置くことで語順が安定する。ある日 話題が変わるとき この本を指すとき 彼は指示語を使い分けたおかげで会話の流れが止まらず続いていった。結局、言葉の距離感と文のつながりを意識する練習を重ねれば 読み手にとって理解しやすい文章になるのだと実感した。
次の記事: 解説文と説明文の違いを徹底解説!読者を動かす文章設計のコツと実例 »





















