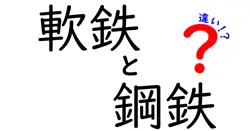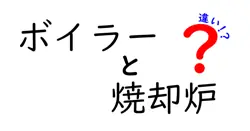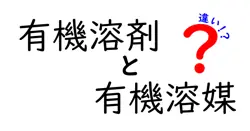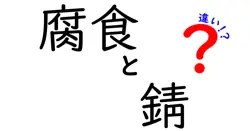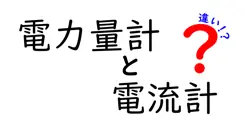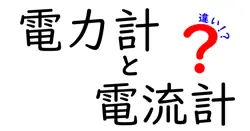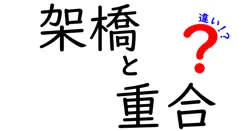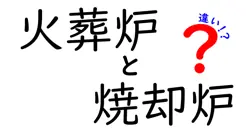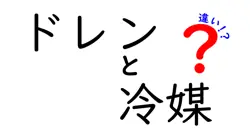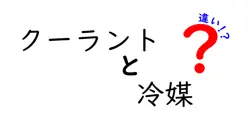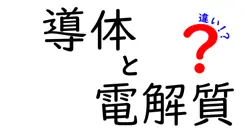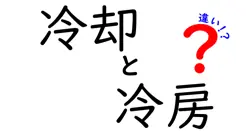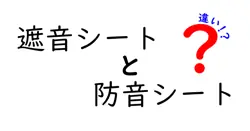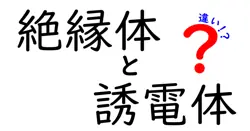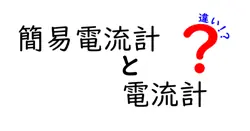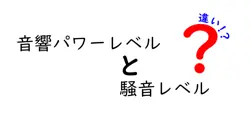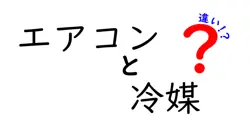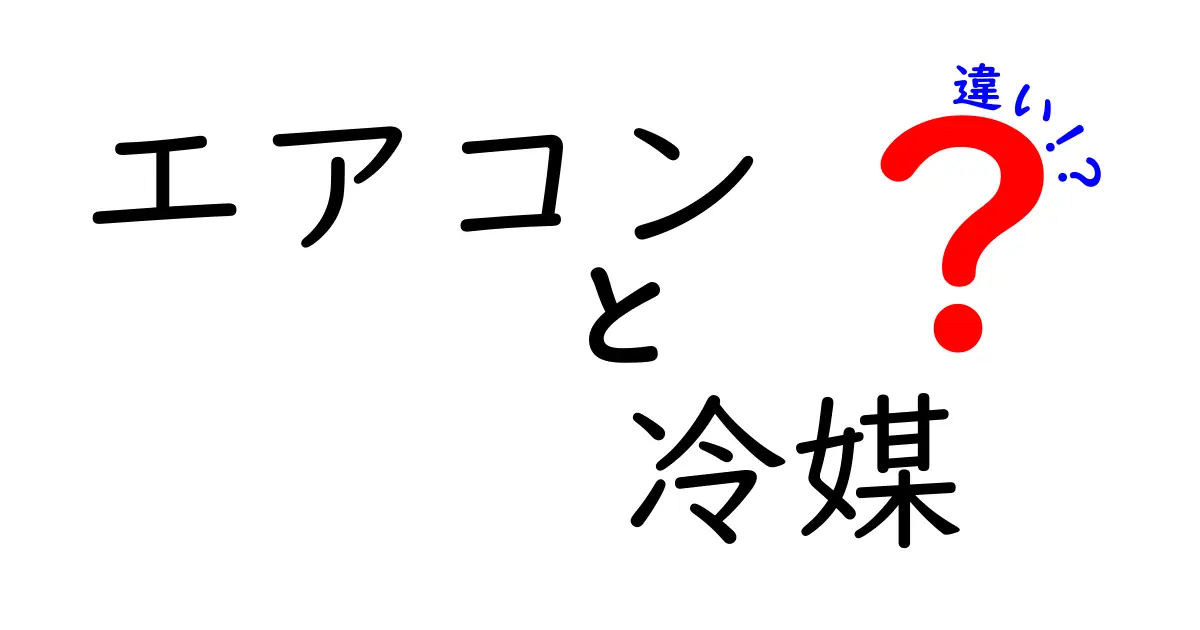
エアコンの冷媒とは何か?その役割を解説
エアコンの冷媒とは、エアコン内部で熱を運ぶための特別な液体や気体のことです。冷媒は、外の熱を室内に持ち込まないために、熱を運び出す役割をしています。これがなければ、エアコンは部屋の温度を下げることができません。
冷媒はエアコンの中で液体と気体の状態を何度も変えながら、熱を吸収したり放出したりしています。これによって室内の空気が冷たくなり、快適な温度を保てるのです。
しかし、冷媒には様々な種類があり、それぞれ性能や環境への影響が違います。どの冷媒を使うかによってエアコンの効率や環境負荷が変わるため、正しく理解することが大切です。
代表的な冷媒の種類とその違い
冷媒にはいくつかの種類がありますが、代表的なものを表で比較してみましょう。
| 冷媒名 | 特徴 | 環境への影響 | 現在の使用状況 |
|---|---|---|---|
| フロン(R22など) | 冷却効果は高いがオゾン層破壊の原因となる | オゾン層破壊物質で規制対象 | 製造中止、古いエアコンに使用 |
| HFC(R410Aなど) | オゾン層破壊はないが温室効果が高い | 温室効果ガスで規制強化中 | 現在主流の冷媒 |
| 自然冷媒(CO2、プロパンなど) | 環境負荷が非常に低い 安全性の問題もある | 低環境負荷 | 徐々に普及拡大中 |
このように冷媒ごとに環境への影響や性能が異なります。フロンは環境に悪いため使用が減り、HFCが主に使われていますが、地球温暖化を抑えるために自然冷媒への切り替えも進んでいます。
冷媒の違いがエアコン性能に与える影響
冷媒の種類が変わると、エアコンの性能や効率にも影響します。例えば、R410Aという冷媒は従来のフロンより高い圧力で動くため、エアコンの冷却効率が良くなり省エネにもつながります。
一方で、自然冷媒は環境に優しい反面、取り扱いが難しかったり安全面で注意が必要なものもあります。
また、冷媒の種類によってはエアコンの設計やメンテナンス方法も異なり、故障のリスクや寿命にも影響が出ます。
そのため、冷媒の種類を理解していると、エアコンを選ぶときに性能や環境面でより良い選択ができるようになります。
冷媒の中でも特に興味深いのが自然冷媒のCO2です。CO2は普段私たちが呼吸で吐き出すガスですが、実はエアコンの冷媒にも使われています。環境に優しいのが特徴ですが、高圧で動くため機械の設計が難しいんです。だからまだ普及は進んでいませんが、未来のエアコンには欠かせない存在かもしれませんね。
前の記事: « ブラインと冷媒の違いとは?わかりやすく徹底解説!
次の記事: フロンと冷媒の違いとは?身近な冷却技術を分かりやすく解説! »